遺留分侵害額請求
亡くなった母の遺言書が見つかりましたが「長女には生前贈与があるので全財産を次女に譲る」と書いてあり、長女の私としては納得いきません。どうにかして、私も財産を受け取れる方法はありませんか?

- 相談者
-
年代:50代性別:女性
亡くなった母の遺言書が見つかりましたが「長女には生前贈与があるので全財産を次女に譲る」と書いてあり、長女の私としては納得いきません。どうにかして、私も財産を受け取れる方法はありませんか?

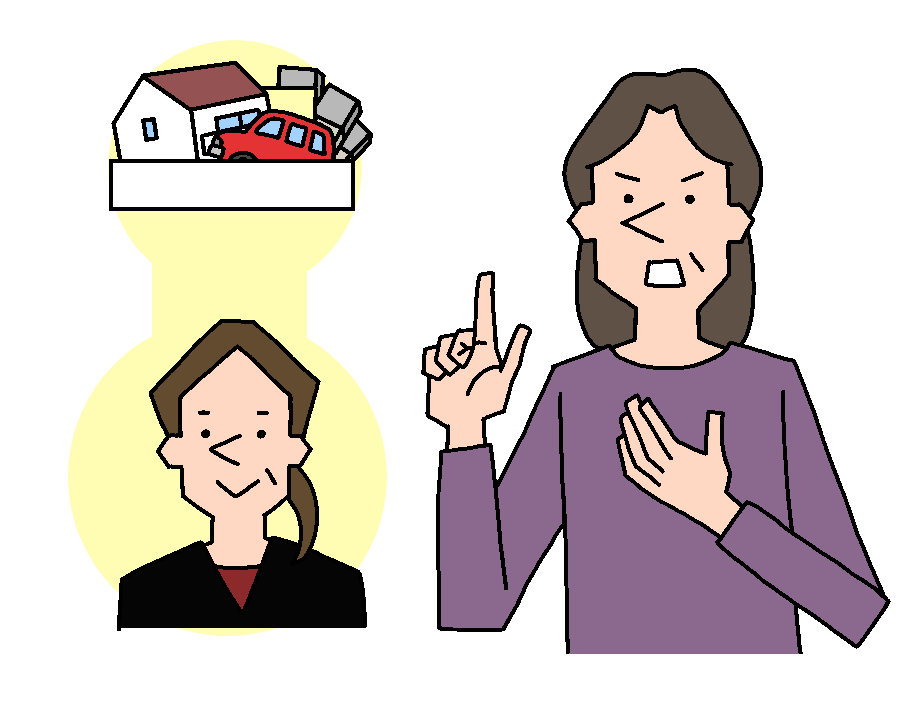
長女のDさんと妹は亡くなった母の遺言を見つけました。遺言書には「生前贈与として姉には既にお金を渡したので、妹にすべての財産を相続させる」と書かれていました。事実と異なる内容もあり、Dさんは遺言書に納得がいきませんでした。Dさんは「自分にも少しくらいは財産を受け取る権利があるのでは」と思い、当事務所に相談に来られました。
事前の話し合いは、不調に終わり、裁判での解決を図るほかありませんでした。
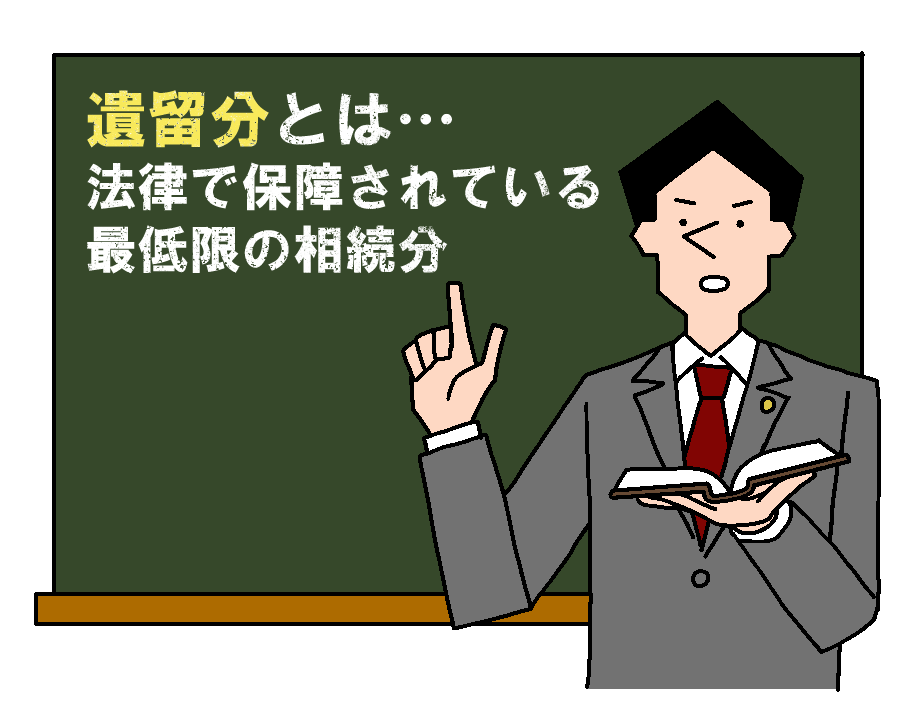
遺言書に書かれた内容が不平等なものであった場合、不利な立場の相続人としては納得がいかないものです。まず、遺言書が自筆証書遺言だった場合は、遺言の形式が法的に正しいか、作成時の被相続人に認知症の症状はなかったかなどの観点から、遺言書の有効性を検証する余地があります。遺言書に問題があった場合は無効となり、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。
遺言書が有効だった場合でも、今回の「全財産を妹に相続させる」というような内容であればDさんが妹さんに対して遺留分侵害額請求を行うことで、法律で保障された最低限の遺産は受け取ることができます。

「遺言作成時、母は認知症だったのではないか」というDさんの言葉を裏付ける証拠を見つけるため、介護等級の認定記録、カルテや介護記録を探しました。しかし、既に亡くなられてから5年が経過しており、記録は残っておらず、証明するものはありませんでした。
次に、遺言書にあったDさんへの生前贈与の問題を検証しました。ずいぶん昔のことでしたが、Dさんが古い通帳をお持ちだったことから、送金は受けたものの大部分が返金されており、実際にDさんが受け取った金額は大した額ではなかったことが確認できました。また、生前、お母様の銀行口座からは不正出金と思われる履歴が残っており、出金された地域を調べると、一部は妹さんによる出金と思われるものが見つかりました。
そうした調査を積み重ねて証拠を裁判所に提出し、裁判所からの和解勧告によって、事実上、Dさんへの生前贈与はなく、一部の不正出金は妹によるものを前提とした遺留分侵害額を算定いただくことができました。

できるだけ早く動いて証拠収集を
今回のケースは、お母様が亡くなってから既に年月が経っていたこともあり、証拠収集に苦労しました。なかでも介護記録は3年から5年ほどで破棄されることが多く、亡くなってからすぐに動き出さないと間に合わない場合もあります。裁判所での主張には証拠が必要です。口でどれだけ言っても取り合ってくれないので、どれだけ証拠を集めて裁判官に認めてもらえるかが主張を通すためには重要なポイントとなります。
今回も、もう少し早くご相談いただけていたら遺留分ではなく、遺言書の有効性を争点にして違うアプローチが選べたかもしれません。