海外資産の相続
妻が海外で得た財産の相続や税申告についても、日本の法律が適用されるのでしょうか?

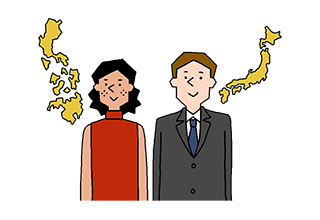
ご相談者は、自身が起業した貿易会社を営んでおられる経営者でした。外国国籍の奥様と国際結婚されており、奥様はシンガポールに拠点を置いて貿易事業を展開されていました。日本とシンガポール、二つの国でそれぞれが別の会社の経営者として活躍を続けておられたご夫婦でしたが、突然、奥様が亡くなられてしまいました。ご相談者は哀しみに暮れる間もなく、妻名義の遺産相続の手続きをこなす必要がありました。
ご相談者の会社には顧問税理士がいました。当初はその税理士に一任するつもりでしたが、遺産相続や保険金についての相談を持ちかけたところ、対応が適切でなかったため(保険金について所得税として申告すべきものを相続財産として申告するなど)、これでは安心して任せられないと判断。私たちの事務所に相談に来られました。

亡くなられた奥様もご主人も、日本と海外とで活躍されていたため、相続税の納税義務の範囲の判定(国内財産のみか、海外財産も対象か等)や海外にある財産の評価などが問題となる国際相続の事案でした。また、亡くなる前に海外の会社からの配当があるなど所得税の修正申告を要するかも検討する必要がある事案でした。

外国籍の被相続人の申告に関しては、被相続人と相続人の生前の住所地や国籍が問われます。このケースでは、奥様の営業活動の場は海外でしたが、パスポートの出入国記録では日本に183日(半年)以上滞在していたことや海外と日本の居住の状況を聞き取り、家族も全員日本に住所があったと判断でき、日本国内財産のみならず海外財産についても課税の対象となると結論づけました。

日本国内には、預金程度でしたので、海外における奥様の資産内容、特に経営されていた会社の株式の価値を把握することが重要になりそうでした。ご主人に依頼して、シンガポールの会社(死亡直後に閉鎖されました)の顧問会計士から、出資状況に関する資料や過去3年分の決算資料を取り寄せてもらいました。取寄せてもらった決算書から、亡くなった時点での会社の純資産額を算出したほか、亡くなる前後の資金の流れを確認しました。 評価額の算定に手間暇を要する不動産や有価証券などが無かったため、比較的スムーズでしたが、もし不動産などの場合には、現地での査定書の取り付けの要否のほか、名義変更のために現地の法律に従って手続をする必要があるため煩雑な手続きと現地の弁護士に依頼するためかなりの費用が掛かったと思われます。

また、相続に関して適用される法律は、亡くなった人の国籍の法律に従うことになっており、法定相続割合も国によっていろいろです。もっとも、遺産分割協議で話し合うことで、どう分けるかの裁量が認められていることもあり、国籍国法の法定相続割合を参考にしつつ、ご相談者と二人の子供を相続人とする遺産分割協議書を作成しました。

日本の相続税法の基礎控除額の算定などは、日本法における法定相続人の範囲を前提としておりますので、相続税の計算における相続人の範囲と実際に遺産分割協議に参加する相続人の範囲や割合については、異なることがありますので、混同しないように注意が必要です。
英文の決算書の確認・読解作業には時間がかかりましたが、ご相談から半年後には、相続、所得税・相続税の申告に関わるすべての作業が完了。ご相談者からも相続という大きな問題が法律的に片づいたことで、気持ちの上でも一区切りがついたと満足していただけました。

生前の住所地が日本なら、納税の義務あり
国際相続に関するよくある質問として
「被相続人が外国籍の場合は、どちらの国の法律が適用されるのか?」
「相続人が外国籍の場合はどうなのか?」
「海外にある財産も課税の対象になるのか?」
などがあげられます。
おしなべていうと、国籍に関係なく、被相続人が日本に住んでいたか、相続人が日本に住んでいたかなど過去の住所の有無が重要となってきます。
ただし、相続税の課税対象になるとしても、実際に相続できるかどうかは、資産の存する国の法律が適用されますので、相続税の算出と実際に承継できるかどうかは別々に検討しなければならず、慎重に対処する必要があります。