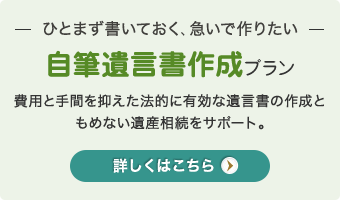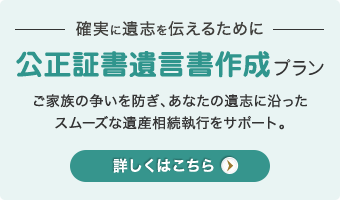大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言書を公証役場で作成する場合の流れと費用
あなたの大切な財産を確実に後世へ引き継ぐために、公正証書遺言の作成は非常に有効な手段です。
よく利用されている遺言書として、公証人と証人の立ち会いのもと公証役場で作成される公正証書遺言があります。
この方式は紛争防止にもつながり、法的効力が高いという大きな利点があります。
本記事では、その作成手順や必要な書類、さらには費用について具体的に解説します。
なお、当事務所では公正証書遺言を作成するための、遺言書案の作成、公証役場とのやり取り、相手方となる他相続人との代理交渉などのサポートをおこなっています。
初回無料相談(電話相談対応)もおこなっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
1. 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人の立ち会いのもとに作成される法的に確実性の高い遺言です。
この方式を選ぶ理由は、遺言の内容が公証役場において正確に記録・保管されるため、偽造変造や紛失の恐れが無く、将来的な争いを防ぐ効果があるためです。
1-1. 公証役場で公証人が作成
公証役場で公証人によって作成される遺言書は、法的な安全性を高めるという大きな利点があります。
元々裁判官、弁護士、検察官などの法律の専門家としての経歴を持つ方が公証人となることが多く、法的に有効性の高い公的な文書として作成されます。
公証人が関与することで、遺言書の内容が法律的に正確に扱われ、内容に法的な問題がないかどうかを専門的にチェックしてもらえます。
これにより、遺言の有効性に関する後日生じる可能性のあるトラブルを未然に防ぐことができるのです。
たとえば、当事者で作成する自筆証書遺言書では表現が不明瞭だったり、遺言書として有効に成立するために法律上必要とされている法的要件を満たしていないケースも見られ、遺言書は書いたものの法的効力が無く相続人間で遺産分割をめぐってトラブルになるリスクがあります。
しかし、公証人の関与により、このようなリスクを大幅に減少させることが可能です。
公証役場で公証人が作成する遺言書は、正式な法的手続きを踏んでいるため、遺言の有効性が高まるというわけです。
1-2. 2人以上の証人の立ち会いが必要
公正証書遺言の有効性を保証するためには、2人以上の証人が必ず必要です。
これは、遺言内容が遺言者の真意に基づく自由意志で作成されたものであると証明するため不可欠なプロセスです。
証人の立ち会いにより、遺言の信頼性が担保され、将来的に遺言の有効性について争いが生じた時に、その争いを最小限に抑えることが可能になります。
例えば、遺言書にサインをする際、証人がその場にいて遺言者がサインをする様子を目撃することにより、後日遺言の真偽が問われた際に、遺言内容が遺言者によってなされたものであることの強力な証明となります。
証人の存在は、公正証書遺言の信頼性を高め、遺産に関する将来の争いを防ぐために重要な役割を果たします。
ただ、実際には、証人になれない次の方を除いて、誰でも証人になることは可能です。
当事務所では、遺言書作成の依頼にあたり証人が用意できない場合も、当方でサポートが可能です。
・未成年者
・推定相続人(相続人となる予定の人)と配偶者及び直系血族
・受遺者(遺言で贈与を受ける人)と配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
2. 公正証書遺言の作成に必要な書類とは
公正証書遺言の作成には、遺言者の身分を証明する書類や遺産を受け取る相続人の情報を明確にするために戸籍謄本などの書類が必要となります。
・遺言者本人の確認資料(次の①から⑤のいずれか)
① 実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
② 認印と運転免許証
③ 認印とマイナンバーカード
④ 認印と住民基本台帳カード(写真付き)
⑤ 認印とパスポート、身体障害者手帳または在留カード
・その他の必要資料
① 戸籍謄本(遺言者と法定相続人との続柄が分かるもの)
② 受遺者の住所の記載のある住民票など
※ 遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合
※ 法人に遺贈される場合、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書
③ 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)および
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
※ 遺言者の財産に不動産がある場合
④ 預貯金等の通帳またはそのコピー等
※ 遺言者の財産に預貯金がある場合
⑤証券会社などの発行の取引報告書
※ 遺言者の財産に株式などの有価証券がある場合
⑥ 証人の本人確認資料(運転免許証の写し等)
⑦ 遺言執行者の特定資料
上記の書類が必要になる理由は、遺言者や遺産を受け取る権利を持つ人物の身元や、遺言者本人の遺志確認をおこないます。
具体的には、遺言者の運転免許証やパスポート、住民票などの身分を証明する書類が必要です。
また、遺産受け取り手の身分を証明する書類も準備しなければなりません。
そして、遺産に関する詳細情報を記載した書類の準備も大切です。
これは、遺産時の財産内容や価値を明確にしておくことで、死亡後の相続財産調査を容易にし、遺産の取込みなどの将来のトラブルを防ぐためです。
これらの書類をしっかりと準備することで、遺言の作成過程がスムーズに進行し、遺言の内容が遺族間でのトラブルを避ける一助となります。
当事務所では、税理士資格を持ち、相続税申告の実務をおこなっている弁護士が相続問題全般をトータルサポートしています。
相続トラブルの絡む相続税申告の問題は、ぜひ当事務所までご相談ください。
3. 公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成は遺産争いを防ぎ、あなたの意志をその死後に明確に伝える有効な方法です。
この遺言書作成の流れにおいては、準備から公証人認証まで、いくつかの重要なステップがあります。
まず、遺言の内容について検討を行い、必要な書類を集めます。
重要な書類には、遺言者と相続人の戸籍謄本や財産に関する証明書が含まれます。
証人の選定も重要で、2人以上の証人が必要です。
さらに、公証役場での文案の確認、予約日の設定、そして予約日当日に公証役場を訪問し、遺言書の作成と認証を行います。
これらの手順を理解し適切に準備することで、スムーズに公正証書遺言の作成が可能となります。
3-1.遺言の内容を検討する
遺言の内容を検討する際には、どの財産を誰に渡すか具体的に決めることが重要です。
この検討が曖昧だと、遺言者が亡くなった後に遺族間でトラブルの原因になることがあります。
例えば、持ち家を息子に残すという場合には具体的に対象不動産の地番を指定して財産を特定する記載があれば、家族間での解釈の相違や意見の対立を防ぐことができるでしょう。
そこで、遺言作成にあたっては、想定できる全ての財産に対して、誰がどのように相続するのかを具体的に検討することが大切です。
また、兄弟姉妹を除く相続人には、法律上最低限保障された相続分があります。
これを「遺留分」と言います。
他相続人の遺留分を侵害するような場合、後日相続人の間で裁判などのトラブルに発展することがあります。
遺言書で1人の相続人に全財産を相続させたい場合には注意が必要です。
こうしたケースにおける生前対策や、遺留分侵害の事実が発覚した際の相続トラブルにも弊所は強みをもっております。
ぜひ、当事務所までご相談ください。
3-2.公証役場へ事前相談に出向く
公正証書遺言を作成する前に、公証役場での事前相談をしておくと手続きがスムーズに進めることができます。
この相談を通じて、遺言の作成手続の流れや必要書類、作成手数料の費用などの具体的な情報を確認することができます。
3-3.必要書類を収集する
公正証書遺言を作成する際、遺言者の身分証明書や相続人の戸籍謄本などの書類が必要となります。
これらは、遺産分割の正確性を保証し、手続きを円滑に進めるために不可欠です。
3-4.公正証書遺言の作成に必要な主な書類
公正証書作成にあたって必要な書類は先ほど「2. 公正証書遺言の作成に必要な書類とは」の図表で示したものになります。
ここで、それらの資料について補足説明いたします。
3-4-1.遺言者に関する書類
公正証書遺言の作成に際しては遺言者の身分を証明する書類の提出が必須となります。
① 実印および印鑑登録証明書
② 認印と運転免許証
③ 認印とマイナンバーカード
④ 認印と住民基本台帳カード(写真付き)
⑤ 認印とパスポート、身体障害者手帳または在留カード
本人にしか取得できない、保有することができない本人確認資料を提示することで、公正証書遺言が遺言者本人の最終的な意志にもとづいて作成されたことを証明することになります。
そのため法的に有効と判断される上記書類や印鑑が必要になります。
またこうした書類をもって遺言者の名前、住所、生年月日などが証明され、公正証書に正確に記載されることになります。
3-4-2.遺産を渡す相手に関する書類
遺産を受け取る人を特定するためには、身分証明書や戸籍謄本など、その人が遺言に記載された相続人であることを明確にする書類が必要です。
これは、相続人や遺言によって指定された受遺者が法的にその遺産を受け取る権利を持つことを証明するためです。
遺産を渡す相手に関する書類は公正証書遺言の作成過程で極めて重要な役割を果たします。
・その他の必要資料
① 戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄が分かるもの)
② 受遺者の住所の記載のある住民票など
※ 遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合
3-4-3.遺産に関する書類
公正証書遺言を作成する際には、遺産に関する詳細な書類が不可欠です。
・その他の必要資料
① 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)および
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
※ 遺言者の財産に不動産がある場合
② 預貯金等の通帳またはそのコピー等
※ 遺言者の財産に預貯金がある場合
具体的には、遺産として挙げられる不動産の場合、登記事項証明書が必要になります。
預貯金を遺産とする場合は、その残高証明書が求められ、株式やその他の証券に関しては、保有している証券の詳細を示す証明書が必要となります。
これらの書類によって、遺産の具体的な価値を反映することができます。
なお、公正証書遺言の場合は特に問題となりませんが、遺言書はあなたの死後に相続人などが遺産整理手続き(相続した財産の名義変更や処分のための手続き)において重要な書類となります。
そのため、相続人などがあなたの死後に遺産整理手続きをスムーズに進めることができるように、それら財産の処分時のことを考えた記載をしておく必要があります。
(A)不動産
相続登記申請時に法務局へ提出します。
相続不動産を特定するための記載は、登記事項証明書通り正確に記載します。
(B)預貯金口座
遺産に関連する書類の収集は、公正証書遺言を作成する上での基礎となります。
遺言を正確に、かつトラブルなく実行するためには、これらの書類が非常に大切となるため、遺言を作成する際には十分な注意を払うべき点です。
3-5.証人を検討する
公正証書遺言の作成に立ち会う証人の選定は大切なポイントです。
公正証書遺言の正式な成立には2人以上の証人の立ち会いが法律上必須であり、万が一証人が不適格だった場合、遺言の効力が失われるリスクがあるためです。
① 未成年者
② 推定相続人(遺言者の相続人となる方)
③ 遺贈を受ける人(遺言により贈与を受ける人)
④ ②推定相続人・③ 受遺者の配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
⑤ 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人
未成年者や遺言内容によって直接的な利益を得る可能性がある者、例えば、遺言によって財産の分配を受ける相続人などは証人になることはできません。
中立的な立場の友人や職場の同僚などに証人を依頼することもできますが、遺言書の内容を知られてしまうため、よくよく考えて信頼できる方に証人を依頼しましょう。
当事務所でも公正証書遺言の作成をサポートしており、証人の手配も可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
3-6.文案を確認する
公証人は、遺言者との打ち合わせで確認した、遺産内容、誰にどの財産を、どの割合で相続あるいは遺贈させるのかなどを書いたメモや提出資料などをもとに、公正証書遺言案を作成します。
これらの処理は、電子メール、ファックス、郵送、持参などの方法により公証人に提出します。
遺言の内容に誤解や曖昧な表現がある場合、遺言の実効性を保証し、遺言の意図を明確にするために正確な文言を用いる必要があります。
例えば、「すべての遺産を子どもに残す」と一見シンプルに記されていた文言でも、それが遺言者の実の子どもか養子を含むか、またはすべての子どもに均等に分けるのか、特定の子どもだけに遺産を残すのかという明確な指定がなければ、解釈の違いで後々トラブルの原因となる可能性があります。
このような例からも分かるように、文案の不明確さが後のトラブルに繋がる恐れがあるため、文案を事前にしっかりと確認し、遺言者の意図を正確に反映させることが、遺言に関するトラブルを未然に防ぐための非常に大切なステップです。
なお、公証役場の公証人に遺産分割内容についてゼロからの遺言書案の作成を依頼することはできません。
どのような財産があり、誰にどのように分けるのかについてはご自身か法律の専門家に依頼し素案を作成し準備する必要があります。
3-7.作成日を予約する
必要書類が揃い、遺産分割の内容などについて準備ができれば公証役場へ予約の連絡をいれて、日程調整をおこないます。
この際、公証役場を訪問する際に持参すべき書類について合わせて確認しておきましょう。
3-8.予約当日に公証役場へ出向く
公証人に依頼する場面における初回訪問時には、遺産分割内容のメモや必要書類を提出します。
これを受けて、公証人は遺言公正証書(案)を作成し、遺言者との間でメールやFAX等により、(案)の修正し確定していきます。
遺言書の内容が確定したら、公証人と話をして遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します。
遺言当日は①遺言者が公証役場に訪問するか、②公証役場に訪問するのが難しい場合には、遺言者の自宅・病院等に出張をして遺言をおこないます。
その際、証人2名の面前で、遺言者として遺言公正証書(案)の内容を口頭で告げて、遺言内容があなたの真意であることを確認します。
間違いがなければ、遺言者と証人2名は遺言公正証書の原本に署名押印し、その後、公証人が職印を押捺し、遺言公正証書を完成します。
公証人から正本と謄本を受け取ったら、大切に保管します。
4. 法律の専門家による作成サポート
公正証書遺言の作成を専門家に依頼することで、遺言書の作成にあたってプランや方針の検討など原案作成を任せられ、相続時のトラブルを回避しリスクを減らすことができる点が大きなメリットです。
弁護士などの関与がなくても、公正証書による作成は可能です。
しかし、専門家が間に入り一緒になって、希望を最大限踏まえて具体的に考えてもらうことができるので安心して遺言書を作成することができます。
5. 公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言を作成することには、相続トラブルを回避し遺言の信頼性を担保する大きなメリットがありますが、一方で費用の負担や公証人への遺言内容の相談ができないなどのデメリットも存在します。
遺言作成の選択肢として公正証書遺言を検討する際には、これらの利点と限界を十分に理解し、自身の状況や遺言に込める意図を踏まえた上で、最適な方法を選ぶことが重要です。
5-1.メリット
公正証書遺言を作成する最大のメリットは次のとおりです。
② 偽造変造、紛失がない
③ 家庭裁判所の検認が不要
法的に有効性が高い遺言書を作成できる点がメリットです。
「1-1. 公証役場で公証人が作成」でも解説したように、専門家である公証人により作成されるため、法律がもとめる形式に違反する可能性は低いと言えます。
また作成された遺言書は、公証役場でも保管されるため、推定相続人による隠匿や偽造変造、遺言者による紛失の心配がありません。
遺言書作成の過程において、公的な公証役場が関与するため、遺言書の保管者や発見した相続人に法律上義務付けられている家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
家庭裁判所の検認手続きとは、偽造変造を防止するために遺言書が存在することや形式や形状を確認する手続きです。
5-2.デメリット
公正証書遺言のデメリットについて説明します。
5-2-1.費用(手数料)がかかる
公正証書遺言の作成には、一定の手数料が発生します。
この手数料は、公証人による遺言書の作成手続きに専門的な知識と時間が必要であるためです。
遺言書の内容や遺産の価値に応じて手数料が変動します。
したがって、公正証書遺言を作成する際には、事前に手数料を確認し、その準備をしておくことが大切です。
具体的な手数料については、「6.公正証書遺言の作成手数料」で具体的に解説します。
5-2-2.公証人に遺言内容は相談できない
公証人は、法律上、遺言内容に関するアドバイスを行いません。
公証人の役割は、遺言書が法的な形式にのっとっているかを証明することです。
遺言内容の妥当性やバランスについてアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談することが一般的です。
6.公正証書遺言の作成手数料
公正証書遺言の作成費用は、政令「公証人手数料令」により定められています。
そのため、全国どの公証役場で作成しても公証人手数料に違いはありません。
6-1.公証人手数料の計算方法
基本、遺言の目的となる財産価格に応じ、次の表を基準に手数料を計算します。
なお、目的となる財産の価額が算定できない場合は、目的の価額を500万円とみなして算出します。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
平成五年政令第二百二十四号 公証人手数料令
上記の財産価格から算定した手数料をもとに、さらに具体的な手数料を算出します。
6-2.具体的な公証人手数料算出方法
具体的な公証人手数料の算出方法と注意点は次の通りです。
① 相続財産の評価
相続財産の評価をおこない、その価格を算出します。
財産の評価方法は、例えば「不動産(土地・建物)」は、市区町村役場で取得できる固定資産税額証明書記載の「固定資産評価額」となり、「預貯金」「その他金融資産」は、口座残高や時価により算定します。
これらの評価時点は、公証人が公正証書遺言の作成に着手した時の額です。
② 受遺者・相続人ごとに算出し合算
相続人(または受遺者)が承継する財産価格を算出し、それぞれに公証人手数料を求めます。
その後、対象となる公正証書遺言でおこなう遺言全体の手数料を合算します。
なお、全体の財産が1億円以下の場合、前記①で算出した手数料額に、1万1000 円が加算されます(「遺言加算」)。
③ 公正証書遺言の原本、謄本の交付費用を加算
公正証書遺言は、通常、原本、正本および謄本を各1部を作成します。
原本は公証役場で保管され、正本および謄本は、遺言者に交付されます。
なお、平成26年以降作成の公正証書遺言書は、公証役場で電磁的記録(PDF)でも保存されており、原本とPDFで二重保存されているため紛失・滅失した場合でも復元が可能なため安心です。
ただ、この保存期間は遺言者の死亡後50年、公正証書作成後140年または遺言者の生後170年間となっています(公証人法施行規則27条 特別の事由)。
公正証書の交付に係る手数料は次のとおりです。
・原本 縦書き4枚(横書き3枚)を超えるとき
超える1 枚ごとに250円加算
(公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令)
・正本および謄本 枚数1枚につき250円
④ その他の加算
遺言書作成は公証役場以外で「入院中の病院」「介護施設」「自宅」などでもおこなうことができます。
たとえば、入院中の病院へ出向き病床で行われたときは、①で算出した手数料額に、50 %加算されます。
また、公証人が、病気で入院中の「病院」、高齢で外出困難な場合の「自宅」「老人ホーム・介護施設」へ出向き作成する場合には公証人の日当(往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超えると2万円)、現地までの交通費(実費)がかかります。
7.公正証書遺言作成時の注意点
いざ公正証書遺言書を作成したものの、その効果を正しく発揮できなければ意味がありません。
また、正しく作成された遺言書が、のちに相続トラブルへと発展するような内容であれば、その予防策を検討し、おこなうことが必要になります。
7-1.遺留分に配慮しなければならない
公正証書遺言を作成する際は、遺留分の存在に注意する必要があります。
遺留分とは、法律で定められた兄弟姉妹を除く相続人に保障された「最低限の相続分」のことです。
たとえば、相続人となる子どもが2人いる場合、遺言で全財産を一方の子に渡すことは他方の子の遺留分を侵害します。
特定の推定相続人(自分の死後相続人となる予定の人)に、財産を多く渡したい場合には、生前贈与や生命保険の活用、養子縁組など遺言によらない対策を事前にとっておくことも有効です。
7-2.遺言書の見直し
遺言書には有効期間はありませんが、ご自身の希望に近い形での相続を実現したい場合には、定期的な見直しをおすすめします。
・法制度の改正
遺言書作り直しで出来なかったことができるようになる
例 2019年7月1日以降作成以降の遺言執行から、遺言執行者単独で相続登記などができるようになりました。
・財産状況の変化
財産内容に基づき、遺産分割方法などの見直し
・推定相続人(相続予定者)の変化
離婚、死亡などにより家族関係が変わった
遺言書作成の前提となった当時の事情や、あなたの意思の変化に応じて、適切な内容に見直していくことが大切です。
なお、遺言の取消し(法律上の「撤回」)も、変更の見直しと同様に、いつでも、何度でもできます。
7-3.相続税の納付
相続税には申告期限があり、納付期限があります。
どちらの期限も「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」です。
「No.4205 相続税の申告と納税」
原則として現金一括で納めることになるため、遺言書作成にあたり相続税の試算をおこない、納付期限までに支払うことができるよう検討しておくことが大切です。
当事務所では、税理士実務をおこなう弁護士が在籍しています。
生前対策はもちろん、相続時に発生するリスクを踏まえた相続対策をおこなっています。
ぜひお気軽に当事務所までお問合せください。
8. まとめ:「難しい」と感じたら専門家へ
公正証書遺言の作成は、将来の紛争を防ぎ、遺産分配の意志に沿った形で手続きを進めるための有効な手段です。
しかし、手続きの複雑さや法的知識の必要性から、個人での作成が難しい場合も少なくありません。
このような場合、遺言作成をサポートする法律専門家への相談が有効です。
証券会社や信託銀行等による遺言書作成をサポートするサービスもありますが、直接弁護士に依頼するよりも費用面で高く、相続時の遺産整理(名義変更などの手続き)に重点を置いていることがあります。
弁護士に相談することで、遺言書の法的な有効性を確保し、あなたの希望を最大限かなえる遺言を作成することができます。
当事務所では、法律のみならず税務に精通した弁護士・税理士が在籍しているため、両方の視点から問題点を洗い出し、具体的な解決策をご提案いたします。
遺産相続問題は初回相談無料です。
また、ご依頼により面倒な生前対策・相続手続きを代行いたしますので、負担を大幅に軽減できます。
ぜひお気軽に、たちばな総合法律事務所までご相談ください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.6.16
- 腹違いの兄弟(異母兄弟・異父兄弟)の相続。相続分、トラブル事例、手続きを徹底解説
- 2025.6.12
- 保証債務の相続はどうなる?基本から具体的対策まで徹底解説
- 2025.6.11
- 内縁の妻(夫・パートナー)は財産を相続できる?法律から見る確実な相続対策と生活保障
- 2025.6.10
- 遺産相続で誰も何も言ってこない…放置は危険!理由と今すぐできる対処法を弁護士が徹底解説
- 2025.5.22
- 養子縁組の条件を徹底解説!普通養子縁組・特別養子縁組の違いから手続き・費用まで