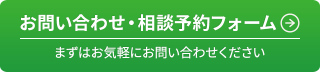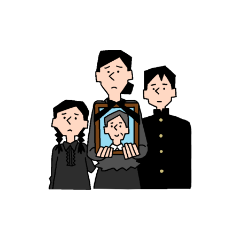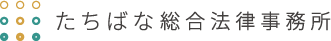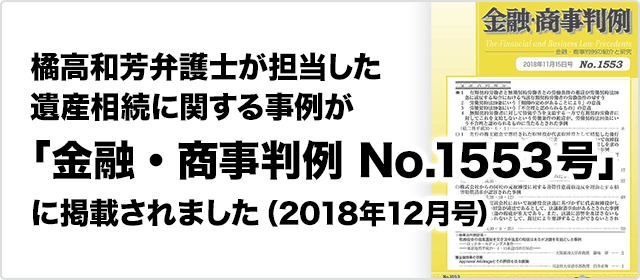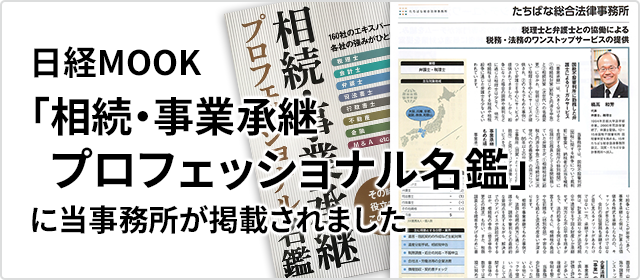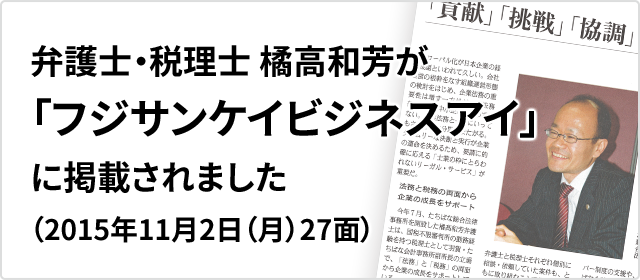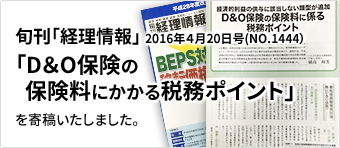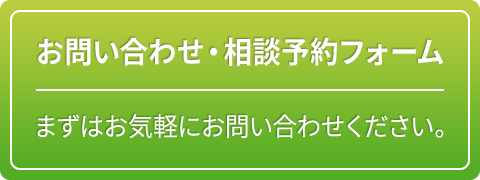大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
中小企業の会社支配をめぐる紛争(その4)
第3 少数派株主からみた会社攻略の前に~まずは株主であることの立証~
1 最初にするべきこととは?
株主権の確認(株式を保有していることのフィックス)が最初の出発点となります。商事部裁判所は、法人税申告書の別表二(又は役員変更登記の際などに添付する株主リスト)を出しても、それのみで証拠価値があるとは認定する例は少ない実感があります(株主総会の招集通知がある、配当があったなどの事実と組み合わせてようやく意味を持つという位置づけと思われます。)。
つまり、法人税申告書別表二や株主リストは、会社法が定める株主名簿ではないことに注意をし、株式保有の立証が可能かを判断する必要があります。
2 まずは株主であることの立証が出発点
⑴ 株式保有の立証方法の違い
会社は、株主がいわば共有しているものですので、株式を保有してなければ、会社に対する各種請求権を行使できません。
そのため、株主である、株式を保有しているということを立証しなければなりませんが、株式の保有や何株を保有しているかの立証は、現実の裁判では、突き詰めていくと難しい立証を要求される場合があります。どう難しいかは、裁判所の商事部と租税部の認定の手法を比較するとわかりやすいと言えます。
⑵ 商事専門部の認定手法(大阪地裁では第4民事部)
裁判所は、要件事実的発想から、①原被告とで当該株式の所有者として争いが無いところまで遡り(要件事実的には「もと所有」と表現されます。設立時の出資者までさかのぼることもよくあります)、②そこから所有権が契約や相続で移転したかの立証を求められます。
そして、証拠(書証)裁判主義より、②は契約書が要求され、書類という名の「直接証拠」があるか否かという極めて形式的な判断になる可能性を考慮しなければなりません。「直接証拠型」が特徴と言えます(なお、直接証拠が無い場合には、間接事実を積み上げての立証を目指すことになりますが、ハードルは高いです)。
要件事実
① もと所有(会社設立時に払込をした者までに遡ることも)
② 株式の所有権の権利移転に係る契約(売買・贈与など)
②の契約書が無くて苦労する場合が多いので、アクションを起こす前にこの点について慎重に検討する必要があります。
⑶ 租税専門部の認定手法(大阪地裁では第2民事部、第7民事部)
租税部(税務署も租税部の認定手法に拠って株主権を判断します)は、以下の諸要素を総合考慮して、相続開始時点(又は現時点)での株主(所有者)が誰かを判断することになります。
これは、預金の実質的所有者(出捐者が誰か)について、間接事実を積み上げて認定していく構造と同じものとなっております。「間接事実推認型」が特徴と言えます。
a:出資者(上記①の払込者とほぼイコール)
b:管理者(住所・氏名の変更があった場合に届けをしたか)
c:利益を誰が得たか(配当の送金を得た者は誰か)
d:名義
e:真の所有者(出資者)と名義人との関係
f:名義人の名義に至った理由・経緯
(上記②の贈与や売買契約のほかに、名義を借りる理由など)
⑷ 認定に差異が生じる理由
裁判官の独立という憲法の条項から、裁判官によって判断を異にすることは当然ですが、上記の差異は、事実認定の手法の差異としか言いようがない面があります。
裁判では、直接証拠(契約書など)があればその信用性を吟味して要件事実を認定し、直接証拠がない場合には間接証拠を総合考慮して要件事実を認定するという段階を踏むためと思われます。
さらに、租税訴訟では、納税者が自らが不利な直接証拠の提出を期待できないという点、仮に贈与契約書や売買契約書が納税者から証拠提出されても(多くの場合は納税者に有利な場合に提出されます)、経済合理性が乏しく租税回避が主目的であるか吟味を要する点で、通常の民事訴訟とは異なる考慮要素があらからと思われます。
例えば、死亡時点から10年以上前の日付の不動産の贈与契約の公正証書を提出された裁判例では、契約直後に移転登記手続がないことなどを理由に贈与の存在を認めなかった裁判例があります。
確かに通常の第三者間取引であれば、契約と同時に移転登記手続をするのが通常であること、肉親間の取引で通謀虚偽による契約書の作成が容易であること、贈与税の回避以外に経済合理性が乏しいという点が考慮されたものと思われます。
3 支配権争奪 ~経験ある弁護士兼税理士でないと非常に困難~
直接証拠の有無の検討、間接証拠の積上げは、裁判経験を積んだ弁護士でないと、非常に難しい業務です。また、裁判は、目標達成のための手段に過ぎないところが、支配権争奪戦の特徴です。株式を保有していると判断できても、最終目標の設定と確認、その目標を達成するために株主権を行使しての情報収集、交渉や裁判の選択について事前に検討しなければならず、その点でも経験が要求されます。
さらに、最終目標を株式譲渡に設定する場合には、譲渡先が法人か個人か、また、譲渡価額の設定等によって思わぬ税金が発生する場合があります。
そのため、税理士の経験もないと、そもそも問題点が見えず、落とし穴にはまる危険が高くなってしまいます。
そのため、会社紛争については、少数派も多数派も、早い段階から弁護士兼税理士に相談をしなければ、取り返しがつかないことになることが多い紛争類型といえます。
事業承継・相続 に関する解決事例
- 2022.11.4
- 閉鎖会社による少数株式の取得と分配(入口と出口)~流れと税務~
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その3)
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その2)
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その1)
- 2019.7.15
- バツイチ社長の相続問題