大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
親の借金問題に直面した時の具体的な対処方法を解説
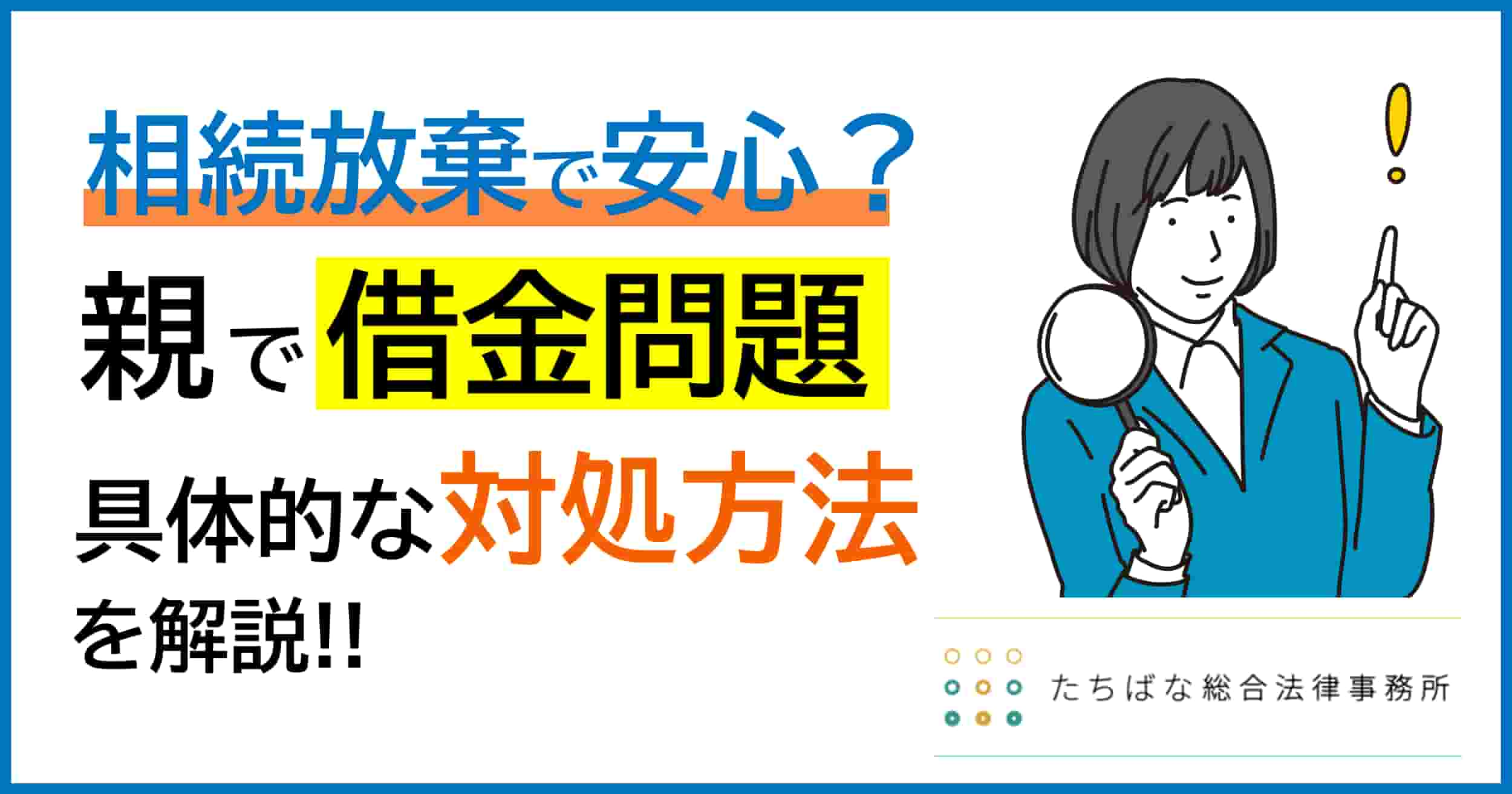
親の借金問題に突然直面した時、多くの方がどう対処すればいいのか悩むことでしょう。
しかし、基本的な知識と具体的な対応策を知っていれば、冷静に対処することができます。
この記事では、親の借金問題に直面した際の具体的な対処法を解説します。
相続による返済義務から、親の生前の借金調査、さらには身を守るための具体的な対策法まで、詳細に徹底解説いたします。
1.親の借金問題のパターン
親の借金問題には、いくつかのパターンがあります。
借金の状況によって取るべき対策が変わるため、まずはそのパターンを把握しましょう。
親の借金問題のパターンとしては、相続による返済義務、親の借金の連帯保証、親が勝手に子の名義で借金などが挙げられます。
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1-1.相続による返済義務
相続は、亡くなった親族の方の資産、負債、契約書上の地位などを引き継ぐことを言います。
負債が資産を上回る場合、相続することで負債を負担することになります。
相続の際に、相続人として取れる選択肢は3つあります。
② 相続放棄(相続しない)
③ 限定承認(資産の範囲で負債を引き継ぐ)
相続する選択をすると、親が抱えていた借金が残っている場合、その借金は相続人に引き継がれ、相続人には返済義務が発生します。
たとえば、親が多額のローンを抱えたまま亡くなった場合、相続人はそのローンを返済しなければなりません。
したがって、親が亡くなると親の借金も相続の対象となるため、相続時にその負債を確認することが重要です。
一般的には、相続財産調査といって、金融機関、個人信用情報機関への照会や不動産(登記事項証明書)や郵便物の確認などをおこなうことで、土地建物を担保に借入をしていないか、消費者金融から返済の督促が届いていないかなどを確認します。
負債の確認を怠り、判断を誤って相続をしてしまうと、後になって多額の返済義務に悩まされるため注意が必要です。
相続による親の借金を相続しないための具体的な対処法については、この後で解説します。
1-2.親の借金の連帯保証
親の借金に限らず、連帯保証人として契約書に署名することは重大なリスクがあります。
連帯保証人は主債務者と同じ責任を負い、親が借金を返済できない場合、その返済義務が連帯保証人にもおよびます。
なお、「連帯保証人」とよく似た「保証人」があります。
言葉は似ていますが、借入れに対する責任の内容が大きく異なります。
保証人には、「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」「分別の利益(ぶんべつのりえき)」と呼ばれる権利があります。
「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人に対して支払い請求をしてきた際に「まずは主債務者に支払いを請求して欲しい」と主張し求めることができる権利です。
「検索の抗弁権」とは、主債務者が返済を拒否し、債権者が保証人に請求してきた際に、「主債務者に返済能力があり、差押え可能な預貯金があるう」と証明し主張することで、債権者に対して、まずは主債務者から取り立てることを求めることができる権利です。
「分別の利益」とは、保証人が複数人いる場合、主債務をその頭数で割った額について返済義務を負うにとどまることを言います。
つまり、300万円の借入れに対して保証人3名の場合、保証人1人あたり100万円を支払えば済むことになります。
上記、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益は、連帯保証人はもっておらず、連帯保証人は主債務者と同じく直接返済義務を背負うことになります。
つまり、親が借金の返済を滞納した場合、債権者は借入れ時の契約に基づいて、連帯保証人として支払いの請求を受ける可能性があります。(期限までに返済をしない場合、残債務の一括返済を求められることが一般的です。)
したがって、親の借金の連帯保証人にはならないことが、最も効果的な対処法です。
1-3.親が勝手に子の名義で借金
親が勝手に子の名義を使ってクレジットカードやローンの名義として子供の名前を無断で使用し借金をするケースがあります。
子どもが未成年のうちは、親権者である親が法定代理権を持ちます。
そのため、子どもの利益のためにした、子どもの名義で借入れは、子ども本人に返済義務が発生する場合があります。
未成年の子の親権者は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代表しておこないます(民法第824条)。
そのため、借入れに際しておこなった署名も有効となります。
ただ、未成年の子どもの利益を無視するような親権の濫用にあたる場合には、借入れの効力は子どもに及びません(最高裁平成4年12月10日判決)。
そのため、借入の効力が未成年の子どもにおよばなかった場合には、無断借入れをおこなった親は借入先に対して損害賠償責任または返済の履行義務を求められることになります。
親が勝手に、成年である子どもの名義で契約をしていた場合には、借金返済の義務はありません。
事実上、親が借金返済をおこなっているケースでは、滞納した場合に初めて子ども名義で借入れをしていたことが発覚することがあります。
ただ、返済義務を負わないためには、債権者からの請求を受けた場合には「親が無断で署名押印し契約したこと」を証明する必要があります(民事訴訟法228条4項)。
子供に知らされないまま借金が増え、返済されないでいると信用情報に傷がつき、将来的な金融取引に影響が出る恐れもあります。
無断借入れが発覚した際、個人信用情報期間(CICや全国銀行個人信用情報センターなど)に問い合わせて自身の個人信用情報を確認することで、取引先の情報を知ることができる場合があります。
また、考えられる法的対処としては、無断での名義使用に対して「無権代理」としての責任を親に問うことが考えらえます。
しかしながら、多くの場合、経済的に困っているからこそ無断借入れを行なっているのであり、無断借入れによって受けた被害を回復するのは事実上難しいと思われます。
なお、上記は民事上の話になりますが、詐欺罪(刑法246条1項)や、成人の子どもの名義で借入れしていた場合には私文書偽造・行使等(刑法159条1項、161条1項)といった刑事上の責任を問われる可能性があります。
2.親の借金を調べる方法
親の生前、死後を問わず、適切な対処を行うためには、まず親の借金状況を正確に知る必要があります。
親の借金を確認する方法はいくつかありますが、それぞれの方法には特有の手順と注意点があります。
ここでは「生前の場合」と「相続する場合」の2つのシナリオについて説明します。
2-1.生前の場合
親の借金を生前に把握することは非常に重要です。
親が健在なうちに問題解決のための支援をおこない、経済的な破綻といった最悪の事態を避けるための準備や対応が可能になります。
具体的には、親の銀行口座やクレジットカードの利用明細を確認します。
定期的に親と対話を持つことや、届いている郵便物から借金の存在を把握できるケースがあります。
・裁判所名記載の封筒
・法律事務所名義の「至急」などの記載がある封筒
金融機関、消費者金融だけではく裁判所から書類が届いていないかもしっかり確認することが大切です。
また、ご自宅など所有不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得して、借入れにあたって抵当権が付けられていないか確認しておくと良いでしょう。
登記事項証明書は、最寄りの法務局で取得することができます。
まれに、金融機関ではなく消費者金融の不動産担保ローンが付いていることが発覚する場合があります。
なお、単なる住宅ローンの場合、団体信用生命保険が掛けられていることが多く、死亡時には住宅ローン残高がゼロになります。
2-2.相続する場合
相続時に、相続人としての選択肢は、① 相続する(単純承認)、② 相続放棄する(相続しない)、③ 限定承認する(資産の範囲で負債を引き継ぐ)の3つがあると先ほど解説しました。
親が借金を抱えている可能性がある場合、それを早期に把握することが重要です。
相続では、基本的にマイナス財産(負債)とプラス財産(資産)、契約上の地位を引き継ぎます。
負債の存在を見逃し、① 相続する選択肢を選んでしまうと、資産を負債が上回っていた場合には、実質的に借金を背負うことと同じです。
また、相続放棄は「自身に相続が発生したことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述(申し立て)しなければなりません。
そのため、親が亡くなった後、すみやかに親の借金の有無をしっかり確認する必要があります。
親の死後に借金を把握する方法としては次の方法があります。
① 個人信用情報機関への照会
貸金業をおこなう銀行、消費者金融、信販会社などで構成される代表的な3団体があります。
これらに相続人として照会し、事故情報などが登録されていないか確認する方法があります。
・株式会社シー・アイ・シー(Credit Information Center CORP. 略称CIC)
・株式会社日本信用情報機構(Japan Credit Information Reference Center Corp. 略称 JICC)
「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」
・一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
「法定相続人による開示のお手続きについて」
② 郵便物、借入れ書類、不動産の担保から把握
生前の場合と同じく、被相続人名義で届く郵便物や、自宅などにある
借入れに関する資料を確認します。
これは、相続時には資産だけでなく借金も相続するため、確認を怠ると予定外の負担が発生する可能性があるからです。例えば、親が大きな借金を抱えていたことを知らずに相続を受け入れた場合、相続人が全ての返済義務を負うことになります。これによって、自身の生活が著しく圧迫されるケースもあります。親が亡くなった後に相続する場合は、必ず債務の確認を行い、必要に応じて法律の専門家に相談することが重要です。
3.親の借金から身を守るための対処法
親の借金問題は、子供にとっても影響を及ぼす深刻な問題です。
しかし、適切な知識と対策を持っていれば、その影響を最小限に抑えることができます。
親の借金から身を守るための具体的な対処方法について解説します。
3-1.【生前】親に借金整理をすすめる
親の借金問題が明らかになった場合、早めに親に借金整理をすすめることが重要です。
早期に対処することで、借金の増加を防ぎ、家族全体の経済的な負担を軽減することができます。
例えば、親が高利率の消費者金融から多額の借金をしている場合、借金整理をすすめることで利息の負担を減らすことができます。
主な借金整理方法は次の3つの種類があります。
● 自己破産(地方裁判所)
免責決定を受けることで、破産決定までの時点の借金の返済義務の免除を受けることができます。
自由財産といって、一定の範囲で自己所有の財産を手元に残すことができます。また、離婚時の養育費など免責決定によっても支払い義務が残るものもあります。
● 個人再生(地方裁判所)
住宅ローンのある自宅・持ち家を手元に残したい場合に利用されることの多い、借金を減額する手続きです。
返済計画に従って支払いをおこなうため、利用にあたって安定した収入があることが必要です。返済が滞ると牽連破産(けんれんはさん)といって、破産手続きに移行する場合や、返済計画に基づく大半の返済をおこなっていた場合には、ハードシップ免責といって残りの返済を免除される可能性があります。
● 任意整理(債権者との任意の話し合い)
借入れしている債権者との任意交渉で、将来利息のカットや返済回数の延長(毎月の返済額を減らす)などの返済条件について契約をまき直すための話し合いです。
話し合い自体や、返済条件にどこまで応じるかは債権者の任意であるため、話し合いがとん挫することがあります。
親が自力での返済が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談させるのも一つの方法です。
早期に親に借金整理をすすめ、家族全体の経済的な安定を図りましょう。
3-2.【生前】成年後見制度の利用(認知症など)
親が認知症などで判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用を検討します。
成年後見制度とは、家庭裁判所で選任された成年後見人が、不動産や預貯金など資産状況に応じて適切な財産管理や、介護サービスや施設入所のための契約締結、遺産分割の協議に参加するなど、本人に代わっておこなう仕組みです。
判断能力が低下すると、借金問題への対応や財産管理が十分に行えなくなる可能性が高いためです。
例えば、親が認知症になってしまい、契約内容を理解せずに新たな借金を重ねてしまう可能性があります。
成年後見制度を活用することで、不適切な借金の防止が期待できます。
成年後見人は、親の財産を管理し必要な支払いを行い、親が不必要な契約を結ぶリスクを排除します。
また、法的に認められた代理権を持つため、金融機関や契約相手との交渉がスムーズに行えます。
この制度を利用することで、親の生活を支えつつ、経済的なリスクを最小限に抑えることが可能になります。
司法書士や弁護士などの専門家と相談しながら、最適な対応策を講じることが推奨されます。
成年後見制度は、親の将来の生活を守り、借金問題から家族を守るための有効な手段です。親の判断能力の低下を感じたら、早めにこの制度の利用を検討しましょう。
3-3.【生前】治療(ギャンブル依存症)
ギャンブル依存症の治療は、親の借金問題を根本から解決するために必要不可欠です。
この症状を治療しない限り、親が借金を繰り返す可能性が高いため、問題を永続的に解決することができません。
ギャンブル依存症の治療を受けることで、借金の根本原因であるギャンブル行為自体を抑制することができます。
例えば、専門家のカウンセリングや治療プログラムを通じて、ギャンブルへの依存を減少させることが可能です。
また、こうした治療プログラムは親子関係の修復にも寄与することが期待されます。
ギャンブル依存症は専門性が高く、治療には専門家の介入が不可欠ですので、早めに適切な医療機関や支援機関に相談することをお勧めします。
3-4.【生前】連帯保証人にならない
親の借金問題に対処するためには、絶対に連帯保証人にはならないことが最重要です。
その理由は、連帯保証人になると借金の全額を肩代わりする義務が生じ、自身の生活にも大きな影響を及ぼすからです。
連帯保証人は、主債務者と同じ地位にあります。
簡単に言うと、返済の滞納があった時に債権者から一括返済を求められ、最悪は訴訟を起こされ財産を差し押さえられる可能性があります。
その際に、連帯保証人である家族が返済できない場合、先ほど挙げた3つの債務整理の方法をとる必要が出てきます。
親の借金の連帯保証人にならないことは、簡単にできるリスクコントロールのひとつです。
なお、連帯保証人でもなく、借金を相続していない場合、貸金業者から親の借金の返済を求められることはありません。
貸金業法において、貸金業者は「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること」を禁止しています。(貸金業法 第21条7号 取立て行為の規制)
3-5.【生前】親の管理権
未成年の子どもの親において、浪費癖やこの名義での無断借入れがあるような、親権者による子供の財産管理が困難または不適当である場合には、家庭裁判所の審判手続きにより管理権を奪うこともできます。
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
この審判は、家庭裁判所の審判であり、親権のうち財産管理権のみを失わせるものです。
3-6.【死後】相続放棄
相続放棄は、親の借金を相続せずに済む法的な手段です。
親が多額の借金を抱えて亡くなった場合、家庭裁判所に相続放棄手続きをとることで、その借金を引き継がなくて済みます。
相続放棄にかかる費用は、申立書に貼る収入印紙800円、裁判所に納める連絡用の郵便切手として数千円、必要書類である戸籍謄本等の収集にかかる費用(相続人の数により変動します)などがかかります。
申立先(管轄は被相続人(親)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。)の家庭裁判所により、連絡用の郵便切手の内訳は異なるため、いくらかかるか予め裁判所に確認しておくと良いでしょう。
申立必要書類の収集から受理までフルサポートしています。
相続放棄できる期間は、原則として相続があったことを知ってから3か月以内に申述(申し出る)ことが必要です。
この期間を経過すると、相続放棄することができなくなります。
そのため、相続を知ってすぐ財産調査にとりかかる必要があります。
相続放棄しようとする場合、相続人全員の同意は必要なく、単独で手続きすることが可能です。
なお、この期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)と言いますが、負債を含めた財産調査に時間がかかり相続放棄するべきかの判断が出来ない場合には期間延長の申し出が可能です(相続放棄期間伸長の審判申立)。
相続放棄の申し出(申述)が家庭裁判所に受理されると、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。
他方、親の借金が資産を上回っている場合、相続放棄など何もしないでいると事実上借金を引き継ぐことになります(単純承認)。
相続放棄のメリットは、借金を引き継がないことですが、一切の相続権を失うため、引き継ぎたい相続財産をもらえないことがデメリットとしてあります(他相続人の相続分が増えます)。
また、相続放棄の撤回は難しいので、慎重な判断が求められます。
なお、相続放棄の熟慮期間中に、被相続人である親名義の預貯金口座から勝手に出金し消費したり、相続不動産の名義を変更したりすると「相続する」ものとみなされ、家庭裁判所に相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄が選択肢にある場合、早めに弁護士に相談し、今後の進め方や流れについてしっかり確認しておくことをおすすめします。
4.親の借金を相続した場合の対処法
親の借金を相続してしまったとき、その対処法は非常に重要です。
適切な対応をしないと自分自身の生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
このセクションでは、親の借金を相続した場合の具体的な対応方法について解説していきます。
自己破産や個人再生、任意整理の各手続きの詳細をご紹介します。
4-1.ご自身の債務整理
親の借金を相続した場合、自分自身の債務整理を行うことで負担を軽減することができます。
親の借金を相続すると、法的には自分の債務となりますが、適切な手順を踏むことで返済負担を減らすことが可能です。
法的な手続きを通じて、返済条件の緩和や減額が見込めるためです。
債務整理には、任意整理や自己破産、個人再生などの方法があります。
これらを活用することで、法的に借金の一部または全部を減額することができます。
債務整理を通じて、親の借金問題による生活への悪影響を最小限に抑えましょう。
4-2.自己破産(借入れをゼロ)
自己破産は、免責決定を受けることで破産手続き開始決定までの借金の返済免除の法的手続きです。
〇 メリット
・非免責債権(養育費など)を除き、返済義務が免除
✕ デメリット
・所有財産の処分
※ 一定の範囲の財産は手元に残せます。
・官報に掲載される
・破産後の借入れ、クレジットカードの作成が難しくなる
(個人信用情報機関:ブラックリストに10年程度登録される)
・一定の職業の場合、影響がある(生命保険外交員、警備員など)
4-3.個人再生(自宅を守り、負債減額)
個人再生は、自宅を手放さずに負債を大幅に減額できる手段です。
裁判所を通じて住宅ローン以外の債務を圧縮し、住宅ローンは従前の契約通り返済を継続します。
現実的な返済計画を立てることが可能な制度であり、この制度を活用することで自宅を守り、生活基盤を保つことができます。
こうしたメリットがあるものの、返済総額がいくらになるかは、所有財産の評価(清算価値)によって変わるため、財産価格が高いと返済額が多くなるため注意が必要です。
また、個人再生には利用条件があります。
① 将来的に継続収入があること
② 負債総額が5000万円以下(無担保の再生債権額)
個人再生を行うためには、裁判所に対して適切な書類を提出し、収入の安定性と一定の返済能力があることを証明する必要があります。
個人再生手続きは、債権者や裁判所とのやり取り、書面提出など複雑で手間が多く、債務整理の専門家である弁護士や司法書士のサポートを受けることが一般的です。
4-4.任意整理(将来利息のカット)
任意整理は将来利息や遅延損害金のカットや返済回数を増やすことで毎月の返済負担を軽減する手続きでです。
任意整理は、裁判所を通さない債権者との交渉です。
返済に関する柔軟な話し合いが期待できる反面、債権者は交渉に応じる義務がないため話し合い自体ができない可能性があります。
任意整理による話し合いが難しく、約定通りの返済ができない場合には、自己破産、個人再生といった裁判所の手続きの利用を検討することになります。
5.まとめ
本記事では、親の借金に関連するさまざまな問題とその対処法について詳しく解説しました。
具体的な対策を講じた後も、定期的に状況を見直し新たな問題が発生しないように注意が必要です。将来的には親の生活設計を見直し、借金の再発を防止するよう心がけましょう。
また、親の借金問題に直面している場合は、まず現状をしっかり調査し、適切な対策を講じてください。
法律専門家や家庭裁判所への相談も重要です。
問題を放置せず、早めの対策でリスクを回避しましょう。
たちばな総合法律事務所では、遺産相続問題、借金問題について初回無料相談を実施しています。
メール、電話、LINEなどでご予約ください。
なお、現在「無料電話相談(10分)」もおこなっています。
弁護士がご事情を丁寧にお伺いし、① 一緒になって問題点を整理し、② 具体的な解決策の提案、③ 個別のご質問へのアドバイスなどおこなっております。
相続、借金について不安やお悩みのある方は、ぜひお気軽にお問合せください。
相続財産の調査、家庭裁判所における相続放棄の申立や、後見制度の利用手続きといった相続トラブルへの対応や、借金の整理手続きもサポート可能です。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説























































