大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「親の介護をしない兄弟」との相続問題を解決するための完全ガイド
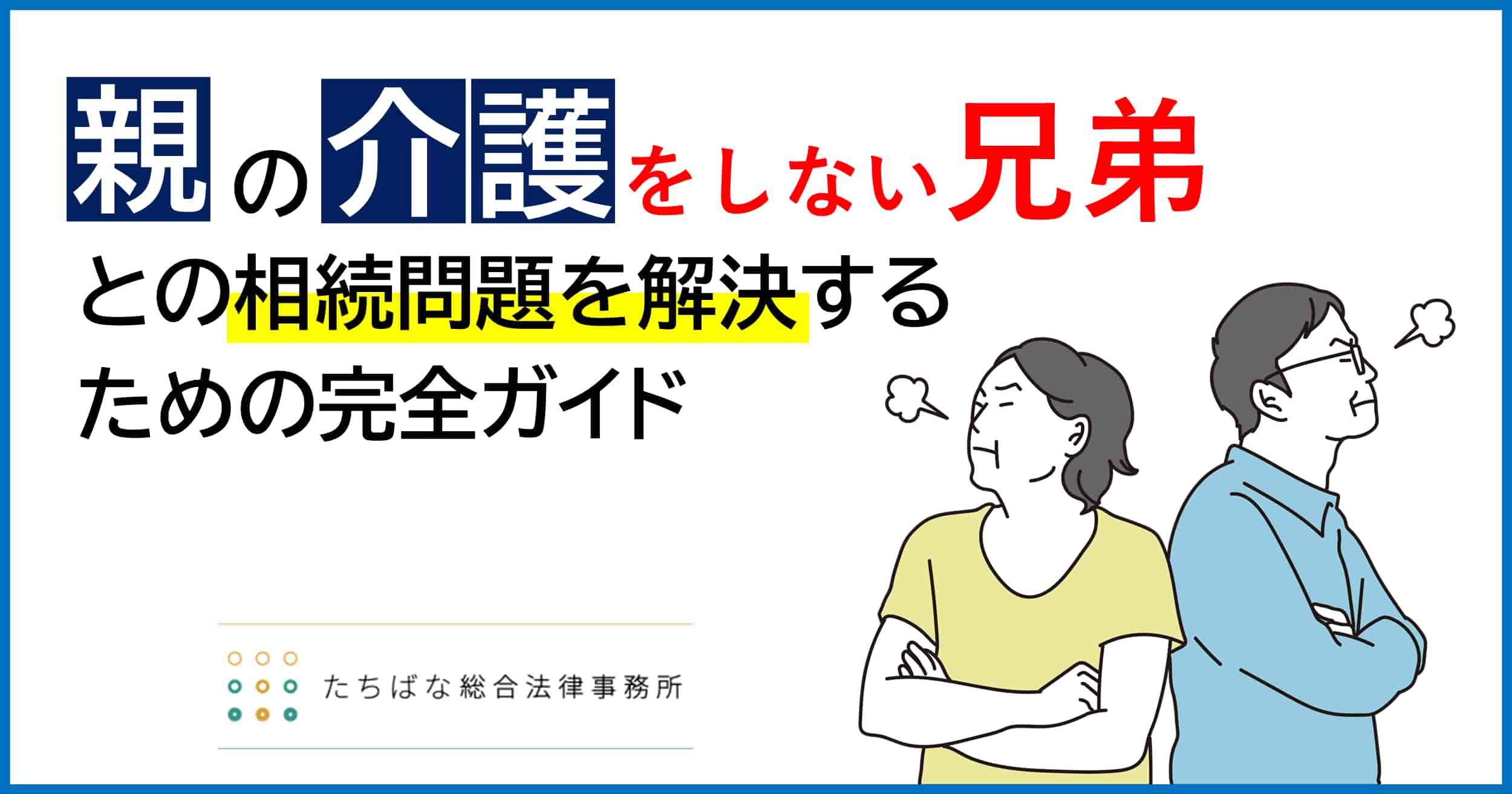
親の介護をしない兄弟との相続問題を解決するための完全ガイド
「長年、親の面倒は自分ばかりが見てきたのに、介護をしない兄弟と同じ相続分なのは納得できない…」
親の介護問題は、相続トラブルの最も根深い原因の一つです。
実際に金銭的、時間的な負担を一身に背負ってきた方にとって、貢献度が考慮されない相続は大きな不満と悲しみを伴います。
本記事では、以下の点について紹介しています。
💡 本コラムの重要ポイント
- ✅ 介護をしない兄弟でも相続できる理由(法定相続分の原則)
- ✅ あなたの介護の苦労を法的に「価値」として認めてもらうための制度(寄与分・特別寄与料)
- ✅ 将来のトラブルを避けるために、親が元気なうちにできる効果的な対策(遺言・生前贈与など)
- ✅ 万が一、相続が発生してしまった後からでも、あなたの貢献を主張するための対処法
専門家の視点から、あなたの長年の貢献が正当に評価され、納得のいく遺産相続を実現するための道筋を分かりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
1. 親の介護は法定相続分に影響する? 介護しない兄弟でも相続できる理由
親の看護や介護に尽力したからといって、当然に相続分が増えるわけではありません。
相続においては、被相続人(亡くなった親)の子どもは、全員が法定相続人として平等な相続分を持つことが法律で定められています(民法第900条)。
これは、親子関係そのものに基づく権利です。
そのため、介護への関与度合いによって自動的に変動するものではありません。
しかし、介護を一身に背負ってきた方からすれば、「ほとんど何もしなかった兄弟が同じ額を相続するのは不公平だ」という感情を抱くのは当然です。
法律もこうした不公平を調整する制度(後述する寄与分など)を用意していますが、原則として「介護をしなかった」という理由だけで、兄弟の相続権を一方的に奪うことはできません。
この法的な大原則を理解しないまま感情論で話し合いを進めると、兄弟間の溝が深まるばかりです。
まずは冷静に法律のルールを把握し、その上でご自身の貢献をどう主張していくかを検討することが大切です。
1-1. 親の介護をしない兄弟を相続から除外できないワケ
法定相続の原則があるため、介護に関わらなかった兄弟を相続から完全に排除することは極めて困難です。
読者の中には、「親に対する兄弟の仕打ちがひどいので、相続させたくない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
法律には、特定の相続人の権利を失わせる「相続欠格」(民法第891条)や「相続人の廃除」(民法第892条)という制度が存在します。
しかし、これらが認められるのは、以下のような極めて限定的な事例に限られます。
参照 特定の相続人の権利を失わせる制度
相続欠格(民法891条)
殺人や詐欺、脅迫によって遺言を書き換えさせるなど、重大な非行があった場合。
被相続人(親)に対して虐待や重大な侮辱を加えた、または著しい非行があった場合に、親自身が家庭裁判所に請求して認められる制度。
「親の介護をしない」「実家に寄り付かない」といった理由だけでは、残念ながらこれらの制度の対象とはなりません。
相続権は、親子という法的なつながりに基づく権利です。
そのため、介護への貢献度が相続権そのものを左右する要因になることは、原則としてありません。
これが、感情的な不満と法的な現実の間に大きなギャップが生まれる原因となっています。
1-2. 法定相続分と実際に受け取れる遺産の差
法定相続分は法律で定められた相続割合の目安です。
ただ、これが最終的な取り分となるわけではありません。
遺言書が残されている場合、遺言書記載の分割内容が優先されます。
反対に、遺言書が残されていなかった場合、遺産の分け方は相続人全員による遺産分割協議(話し合い)で決定します。
この協議で全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
例えば、あなたが親の介護にかけた費用や労力を具体的に示すことで、他の兄弟の理解を得て、あなたの取り分を多くすることに合意してもらうことも可能です。
そのためには、あなたの貢献度を客観的な証拠で示すことが極めて重要になります。
介護にかかった費用の領収書や、日々の介護内容を記録した日記などは、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めるための強力な材料となります。
もし、相続手続きで兄弟の合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停へと進むことになります。
2. 介護により相続分が増える可能性のある「寄与分」とは
あなたの介護による貢献を法的に金銭評価し、相続分に上乗せできる可能性のある制度が「寄与分」(民法第904条の2)です。
これは、共同相続人の中に、被相続人(親)の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合、その貢献度を金銭的に評価し、本来の法定相続分に上乗せして取得できる制度です。
「特別の寄与」とは、通常の家族間の協力や扶養義務の範囲を超えるような、特別な貢献を指します。
例えば、親の事業を無給で手伝って財産を増やした場合や、親の借金を肩代わりして財産の減少を防いだ場合などが典型例です。
介護もこの寄与分に該当する可能性がありますが、「通常の扶養の範囲」と判断されやすく、認められるためのハードルは高いです。
2-1. 寄与分が認められるための具体的要件
寄与分が認められるには、単に「介護が大変だった」というだけでは不十分で、いくつかの具体的な要件を満たす必要があります。
裁判実務上、介護を理由とする寄与分が認められるためには、主に以下の要件が必要です。
介護が寄与分として認められる要件(裁判実務)
特別の寄与であること
親族間の通常の扶養義務(民法第877条)を超えるレベルの貢献である必要があります。
「身の回りの世話をしていた」程度では認められにくく、例えば、要介護度が極めて高く、本来であれば介護サービスや施設に頼らざるを得ない状態だったにもかかわらず、相続人が同居し無償で介護を担った、といった事情が求められます。
無償性(またはそれに近い状態)であること
親から介護の対価として給料や十分な生活費の援助を受けていた場合、寄与分は認められません。
継続性と専従性
一時的な手伝いではなく、長期間にわたって継続的に介護を行っていたこと、また、その介護のために仕事を辞めざるを得なかったなど、自身の生活を犠牲にしていた事実も考慮されます。
被相続人の財産の維持・増加との因果関係
あなたの介護によって、親が本来支払うはずだった介護費用(施設利用料、ヘルパー代など)が支出されず、結果として親の財産が維持された、という関係が明確に説明できる必要があります。
これらの要件を、客観的な証拠(介護記録、診断書、領収書など)をもって主張することが必要です。
2-2. 親の介護で寄与分が認められにくい理由と計算方法
家庭内での介護は、法律上「家族間の協力義務の範囲内」と見なされやすく、寄与分の主張が認められにくいのが実情です。
裁判所が介護による寄与分に慎重なのは、夫婦や親子の間には互いに協力し扶助する義務があるからです。
そのため、「特別な寄与」であったことを証明する責任は、主張する側にあります。
なお、寄与分が認められる場合、その金額は具体的に計算されます。
介護による寄与分の計算方法は一律ではありませんが、一般的には以下の計算式が用いられることがあります。
寄与分の計算式(一例)
介護報酬相当額
介護保険制度で定められている要介護度に応じた介護報酬基準額などが参考にされます。
裁量割合
0.5〜0.8程度で調整されることが多いです。
これは、親族間の扶養義務などを考慮し、専門の介護職と同等とは評価されないためです。
例えば、日当8,000円相当の介護を5年間(1,825日)行い、裁量割合が0.7とされた場合、1,825日 × 8,000円 × 0.7 = 10,220,000円 というように、かなり高額な寄与分が認められる可能性もゼロではありません。
上記の計算額が確実に認められる保証はありませんが、主張してみる価値はあります。
2-3. 「寄与分」と「特別寄与料」との違いと配偶者が請求できるケース
2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族も、介護の貢献分を金銭で請求できる「特別寄与料」(民法第1050条)の制度が新設されました。
これは、例えば「長男の嫁」のように、法定相続人ではないものの、被相続人の介護に尽力した親族の貢献に報いるための制度です。
寄与分と特別寄与料の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 法定相続人のみ | 相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族) |
| 貢献の内容 | 財産形成や維持への貢献 | 療養看護その他の労務の提供 |
| 主張する場面 | 遺産分割協議・調停・審判 | 相続人に対して金銭を請求 |
| 請求の期限 | 相続開始時から10年 | 相続開始及び相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年以内 |
特に注意すべきは、特別寄与料については請求期限が非常に短い点です。
相続が開始したら、速やかに手続きを検討する必要があります。
計算方法は寄与分に準じますが、これも他の相続人との話し合いや、まとまらなければ家庭裁判所への申立てが必要です。
3. 親の生前にできる対策(介護をする子がより多く相続するための方法)
ここまで解説したとおり、親が亡くなった後に介護の貢献を主張するのは、精神的にも手続き的にも大きな負担がかかります。
解決策のひとつとして、親が元気なうちに意思表示をしてもらうことが挙げられます。
生前対策は、相続が「争続」になるのを防ぐための最も効果的な手段です。
親自身が「介護をしてくれた子に多く財産を渡したい」という意思を明確な形で残すことです。
ここでは、代表的な3つの生前対策を紹介します。
3-1. 親に遺言書を作成してもらうメリットと注意点
遺言書は、親の最終的な意思を示す最も強力な法的文書です。
遺言書で「介護をしてくれた長男に自宅不動産を相続させる」といったように、財産の分け方を具体的に指定しておけば、原則として、遺言書の内容が優先されます。
これにより、その内容通りに遺産相続がおこなわれ、相続開始後の兄弟間での無用な争いが起こるリスクを大幅に減らすことができます。
特に、法的な不備で無効になるリスクが低い「公正証書遺言」の作成がおすすめです。
法律のプロである公証人が内容を確認し、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。
ただし、遺言書も万能ではありません。
兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の相続分を確保する権利「遺留分」が保障されています(民法第1042条)。
例えば、「全財産を長男に」という遺言は、他の兄弟の遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という形で、財産を多く受け取った人に対して金銭の支払いを求めることができます。
トラブルを避けるためには、他の兄弟の遺留分にも配慮した遺言書を作成することが大切です。
3-2. 生前贈与や負担付死因贈与契約の活用
親が元気なうちに、介護の対価として財産を贈与してもらう「生前贈与」も有効な手段です。
年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」を活用する方法などがあります。
しかし、生前贈与は、相続時に「特別受益」とみなされる可能性があります。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益のことで、相続財産の前渡しと扱われます(民法第903条)。
特別受益とみなされると、その贈与額を相続財産に加算した上で各相続人の相続分を計算し直し(持ち戻し計算)、贈与を受けた人はその分を差し引かれるため、結果的に他の兄弟との不公平が是正されることになります。
これを避けるためには、親が贈与をする際に「この贈与は介護への感謝の気持ちであり、相続財産とは別にする(持ち戻しを免除する)」という意思を明確に書面で残しておくことが重要です。
また、「私が亡くなるまで面倒を見ることを条件に、この不動産をあなたにあげる」といった「負担付死因贈与契約」も一つの方法です。
これは契約であるため、双方の合意が必要ですが、介護する子どもの権利を守ることができます。
3-3. 生命保険を使った相続対策のポイント
生命保険の活用は、非常に効果的な相続対策の一つです。
親が自身を被保険者、保険料負担者とし、介護をしてくれた子どもを死亡保険金受取人に指定します。
生命保険金には、以下のような大きなメリットがあります。
生命保険金を利用した相続対策(特定の人に財産を贈与したい)
-
遺産分割の対象外
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされます。
そのため、遺産分割協議の対象になりません。
他の兄弟に分配することなく、指定された受取人が全額を受け取れます。 -
特別受益に該当しにくい
よほどの不公平がない限り、生命保険金は特別受益にも該当しないとされるのが判例の傾向です。
-
非課税枠がある
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
-
手続きが簡単
複雑な相続手続きを経ずに、比較的迅速に金銭を受け取れるため、当面の生活費や葬儀費用にも充てられます。
親の状態(健康状態や年齢)によっては加入が難しい場合もありますが、介護をしてくれた特定の人に対して確実に財産を残すための有効な手段と言えるでしょう。
3-4.養子縁組をする
例えば、法定相続人ではない「長男の嫁」などが介護に尽力した場合、被相続人と養子縁組をすることで、実子と同等の相続権を得るという方法もあります。
これにより、法定相続人ではない人も実子と同等の相続権を獲得します。
4.寄与分の主張手続き(親が亡くなってからの対策)
親が生前に対策を講じられなかった場合でも、あきらめる必要はありません。
相続開始後、あなたの貢献を主張する「寄与分」の手続きを進めることになります。
4-1. 遺産分割協議で合意を得るための進め方
まずは、相続人全員でおこなう遺産分割協議の場で、寄与分を主張し、合意を目指します。
この段階で最も重要なのは、感情論を排し、客観的な証拠に基づいて交渉することです。
遺産分割協議のなかで「寄与分」の交渉をおこなうためのステップ
1. 証拠の準備
介護にかかった費用の領収書、介護サービスの利用明細、要介護認定通知書、医師の診断書、そして日々の介護内容を記録した詳細な日記など、あなたの貢献を裏付ける資料を全て揃えます。
2. 希望額の提示
証拠に基づき、前述の計算式などを参考に、あなたが主張したい寄与分の金額を具体的に算出します。
なぜその金額になるのか、論理的に説明できるように準備しましょう。
3. 冷静な対話
「自分だけが苦労した」という不満をぶつけるのではなく、「この期間、これだけの費用と時間をかけて親の生活を支えてきた。その結果、これだけの財産が維持できた。この点について、少し考慮してもらえないか」といった形で、冷静に事実を伝え、理解を求める姿勢が大切です。
もし当事者同士での話し合いが難しい場合は、早い段階で弁護士などの専門家に代理人として交渉を依頼するのも一つの有効な手段です。
第三者が入ることで、お互いに冷静になり、建設的な話し合いが進むことが期待できます。
4-2. 家庭裁判所での調停・審判を利用する流れ
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。
決して、一方的に勝ち負けを決める場ではありません。
遺産分割調停の流れ
1 申立て
家庭裁判所に申立書と必要書類(戸籍謄本、財産目録など)を提出します。
2 調停期日
申立人と相手方が別々の日に、または同日でも別室で待機し、調停室に交代で入室して調停委員にそれぞれの主張を伝えます。
調停委員が双方の意見を聞きながら、解決案を探っていきます。
3 調停成立・不成立
話し合いがまとまれば「調停調書」が作成され、法的な効力を持ちます。
まとまらなければ調停は不成立となり、自動的に「審判」手続きに移行します。
審判では、裁判官が全ての事情を考慮し、寄与分を含めた具体的な遺産分割方法を決定します。
5. 介護をしない兄弟とのトラブルを防ぐコツ
相続トラブルは、一度こじれると修復が困難になります。
最も大切なのは、問題が深刻化する前に対策をとることです。
5-1. 介護内容や費用負担の可視化とその重要性
親の面倒を見ているあなたの負担は、他の兄弟からは見えにくいものです。
「大変だろう」とは思っていても、その具体的な中身は伝わっていません。
だからこそ、介護の負担を「可視化(見える化)」することが極めて重要です。
介護日記をつける
いつ、どのような介護をしたか(食事、排泄、入浴の介助、通院の付き添いなど)、親の状態はどうだったか(認知症の症状、体調の変化など)を具体的に記録します。
これは後の寄与分の証拠になるだけでなく、兄弟に状況を説明する際の客観的な資料にもなります。
費用の記録
介護にかかった費用(おむつ代、医療費、交通費、介護サービスの自己負担分など)は、必ず領収書を保管し、一覧表にまとめておきましょう。
親の預金から支出した場合は、その使途も明確にしておきましょう。
これにより、他の兄弟姉妹から財産の使い込みを疑われるリスクを防げます。
これらの記録は、あなたの貢献度を客観的な事実として示すためのものであり、感情的な水掛け論を避けるための最大の防御策となります。
5-2. 兄弟間のコミュニケーションを円滑にする方法
介護の負担を一人で抱え込まず、兄弟間で情報を共有し、コミュニケーションを取ることが不可欠です。
「どうせ何もしてくれない」とあきらめて連絡を絶ってしまうと、溝は深まる一方です。
もし兄弟姉妹間の関係が許すのであれば、次のことを検討してみてはいかがでしょうか。
定期的な状況報告
月に一度でも良いので、電話やメール、グループLINEなどで親の近況や介護の状況を報告する方法です。
写真や動画を送るのも効果的です。
状況が伝われば、他の兄弟も「自分にできることはないか」と考えるきっかけになります。
具体的な役割分担の依頼
「週末だけ様子を見に来てほしい」「手続き関係の書類管理を手伝ってほしい」「金銭的な援助をしてほしい」など、相手ができる範囲で具体的なサポートをお願いしてみる方法です。
具体的な役割分担を依頼することで、当事者意識が芽生える可能性があります。
感謝を伝える
たとえ小さな協力でも、「助かったよ、ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることが、良好な関係を維持する上で非常に重要です。
介護は一人で背負うにはあまりにも重い負担です。
専門家や公的なサポート機関(地域包括支援センターなど)も積極的に活用し、あなた自身が追い詰められない環境を整えることも大切です。
6. まとめ
親の介護と遺産相続の問題は、法律論だけでは解決できない、家族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
結論として、介護の負担に不公平を感じているなら、決して一人で抱え込まず、問題が深刻化する前に専門家である弁護士に相談することが、最善の対処法です。
介護をしたあなたの貢献は、法的に正当な権利として主張できる可能性があります。
寄与分・特別寄与料に関する専門サポート
- あなたの状況で、どの程度の寄与分が主張できるかの見通し
- 法的に有効な証拠の集め方に関するアドバイス
- 他の兄弟との冷静な交渉の代理
- 調停や審判になった場合の法的手続きのサポート
問題が長引くほど、家族の絆は傷つき、あなた自身の心身の負担も増大します。
簡単なことではないかもしれませんが、勇気を出して一歩を踏み出し、公正で納得のいく相続を実現しましょう。
たちばな総合法律事務所では、遺産相続問題、生前対策、相続税申告などの問題について、初回無料相談をおこなっています。
ご事情、財産状況をお伺いし、具体的な解決方法や、不安・悩みについてアドバイスいたします。
電話、メール、LINEでご予約を承っております。
ぜひ気軽にご相談ください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説






















































