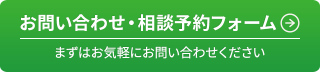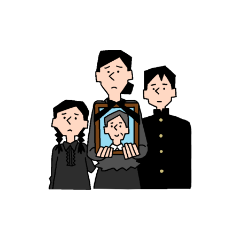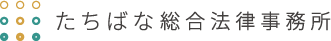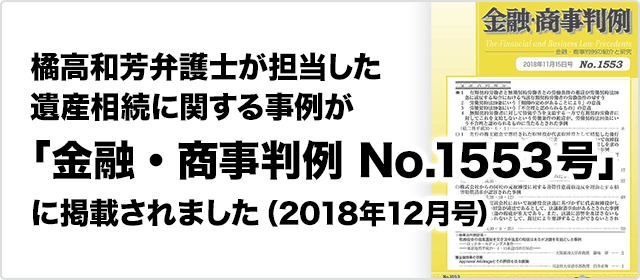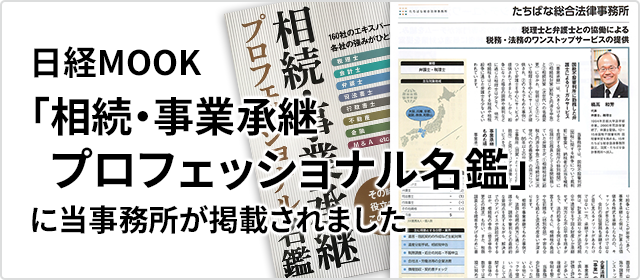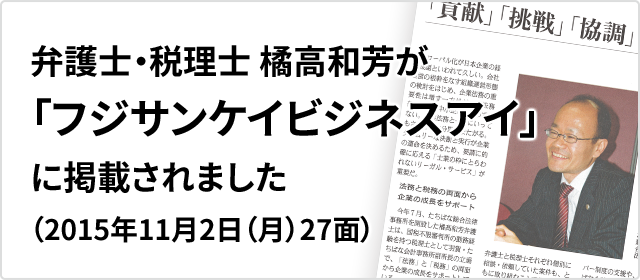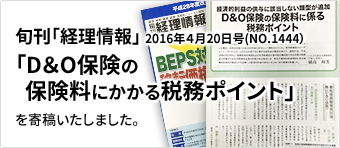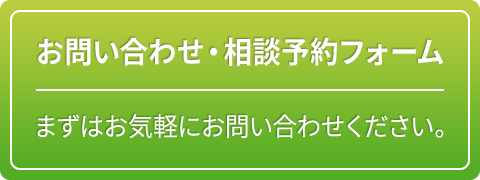大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税はいくらまで無税?基礎控除の仕組みと申告の判断ポイント

相続税はいくらまで無税?基礎控除の仕組みと申告の判断ポイント
相続は、多くの方にとって人生の大きな節目の一つです。
「実家を相続するけど、税金はかかるのだろうか?」
「相続税はいくらまで無税なの?」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。
適切な知識を持って早めに対策を立てることで、ご家族の税負担を大きく軽減できる可能性があります。
周囲の家族とも情報を共有しながら計画を進めることで、思わぬトラブルを回避しやすくなるでしょう。
大切な財産を正しく次世代に引き継ぐための最初のステップとして、この記事をお役立てください。
この記事では、相続税がいくらまで無税になるのかを決める「基礎控除」の仕組みを中心に、各種特例や申告手続きの流れまで、相続税の基本をわかりやすく解説します。
まずは基礎的な仕組みから確認し、具体的な事例をもとにシミュレーションをして、理解を深めていきましょう。
1. 相続税の基礎控除とは?いくらまでなら無税になるのか
相続税がかかるかどうか、つまり「いくらまで無税か」を判断する上で最も重要なのが「基礎控除」です。
ここでは、その仕組みや控除額の計算方法を確認してみましょう。
相続税が発生するかどうかは、まず遺産の総額がこの基礎控除額を上回るかで判断します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
遺産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
国税庁の統計によれば、実際に相続税が課税されているのは亡くなった方全体の1割未満であり、多くのケースでこの基礎控除の範囲内に収まります。
ただし、遺産総額が基礎控除額を下回っていても、後述する特例を適用するためには申告が必要になる場合があります。
相続税制度は法改正も行われるため、最新の情報を基に判断することが重要です。
「基礎控除額以内だから大丈夫」と自己判断せず、正確な財産評価と家族構成の確認をきちんと行いましょう。
2. 法定相続人の数による非課税枠の変動
「いくらまで無税か」は、法定相続人の人数によって大きく変わります。
ご家族の構成を正確に把握することが、相続税を試算する第一歩です。
法定相続人の数が増えれば、その分だけ基礎控除額も「1人あたり600万円」ずつ加算されます。
そのため、配偶者や子どもの人数によって非課税枠が大きく変動します。
まずは民法で定められたご自身の家庭の「法定相続人」が誰で、何人いるのかを正確に把握することが重要です。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
2-1. 配偶者や子どもの人数が基礎控除に与える影響
配偶者は必ず法定相続人となるため、基礎控除の計算には必ず含まれます。
そして、子どもの数が増えれば、その分だけ600万円ずつ控除額が増加します。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人のご家庭では、法定相続人は合計3人です。
この場合の基礎控除額は『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』となり、遺産総額がこの金額を下回れば相続税はかかりません。
2-2. 相続のケース別・具体的な基礎控除額シミュレーション
それでは、代表的な家族構成別に、相続税が無税となるボーダーライン(基礎控除額)を見てみましょう。
| 法定相続人の構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額(いくらまで無税か) |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 子1人のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者と子1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 子2人のみ | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者と子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 子3人のみ | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者と子3人 | 4人 | 5,400万円 |
例えば、被相続人が夫で、妻と子ども1人というケースでは、『3,000万円+600万円×2人=4,200万円』までは相続税がかからない計算になります。
ただし、これはあくまで遺産総額が基準であり、実際の納税額は、被相続人が遺した借入金(ローン残高)や利用できる特例の適用によって大きく変わるため、詳細な計算を行うことが重要です。
また、法定相続人の人数をカウントする際には、特に注意すべき点が2つあります。
相続放棄があった場合
相続人の一人が家庭裁判所で相続放棄をしても、税法上の基礎控除額の計算においては、その放棄がなかったものとして相続人の数に含めて計算します。
養子がいる場合
養子の人数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができません(相続税法第15条第2項)。
このように民法上のルールと税法上のルールが異なる場合があるため、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。
3. 相続税がかからない場合と課税対象財産の範囲
「うちは預貯金も少ないし、基礎控除以下だろう」と考えるのは危険です。
相続財産には、ご自身が把握していないものも含まれる可能性があります。
相続税がかからない主なケースは、遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合です。
しかし、相続財産には現金や預貯金、不動産だけでなく、株式や投資信託、生命保険金など多岐にわたる資産が含まれるため、まずは財産の全体像を正しく把握する必要があります。
非課税財産といっても、墓石や仏壇・仏具などごく限られたものであり、ほとんどの財産は課税対象になると考えましょう。
特に、死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象となりますが、これらには非課税限度額が設けられています。
また、生前に贈与を受けた財産でも、相続税の計算の上で遺産として考えられるものもあるので注意が必要です。
財産の一部を見落としたり、非課税枠の計算を誤ったりすると、後から税務署に申告漏れを指摘され、本来の税金に加えて過少申告加算税や延滞税といったペナルティが科されるリスクがあります。
3-1. 課税対象となる財産、非課税財産の違い
相続税の計算対象となる財産を整理すると、以下のようになります。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 本来の相続財産 | 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、投資信託、自動車、ゴルフ会員権、著作権など |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金(それぞれ非課税限度額を超える部分) |
| 生前贈与財産 | 相続開始前3年(令和6年以降は段階的に7年)以内の贈与財産 |
| 非課税財産 | 墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産、国や地方公共団体への寄附財産など |
| 控除できるもの | 借入金、未払金などの債務、葬式費用 |
たとえ形のない財産であっても、金銭的価値のある権利(特許権など)は課税対象となるため、見落としがないよう注意が必要です。
3-2. 死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金には、遺族の生活保障という観点から、それぞれに非課税枠が設けられています(相続税法第12条)。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が3人いれば、死亡保険金と死亡退職金それぞれで1,500万円までは非課税となり、それを超える部分のみが他の相続財産と合算され、課税対象に含まれます。
この非課税枠は、相続人が受け取った場合にのみ適用され、相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った場合には適用できない点に注意が必要です。
4. 相続税の計算方法:基礎控除から申告書提出までのステップ
遺産総額が基礎控除を超えそうな場合、実際にいくら納税が必要になるのか、計算の流れを理解しておきましょう。
相続税の計算は、まず遺産総額を求め、そこから借金や葬式費用などを控除して課税対象額を算出します。
その後、法定相続分で遺産を分割した場合の相続税総額を計算し、実際の分割割合に応じて最終的な納税額を配分するという、少し複雑な流れをたどります。
計算過程で適用可能な特例や控除を適用し、税額を調整した上で、最終的に相続開始から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税することが法律で義務付けられています。
4-1. ステップ1:遺産総額の算出
被相続人が生前に保有していたすべてのプラスの財産を洗い出し、それぞれの相続税評価額を合計することからスタートします。
この段階では、不動産の評価や株式・投資信託などの金融資産の時価など、正確な数値を把握することが大切です。
小さな預金口座や骨董品なども見落としがちなため、丁寧にチェックすることが求められます。
4-2. ステップ2:債務や葬式費用の控除
ステップ1で算出した遺産総額から、被相続人が残した借入金やクレジットカードの未払金などの債務、そして葬式費用を差し引きます。
これにより、「正味の遺産額」が確定します。
お墓の購入費用は、生前に購入した場合は非課税財産となりますが、亡くなった後に購入した場合は葬式費用として控除することはできません。
このように、控除対象になる費用とならない費用があるため、領収書や明細をきちんと管理しておくことが重要です。
4-3. ステップ3:法定相続分による相続税総額の計算
正味の遺産額から基礎控除額を引いた「課税遺産総額」を、仮に法定相続分どおりに分割したと想定して、各相続人の取得額を計算します。
そして、それぞれの取得額に相続税の税率を掛けて、各人の仮の税額を算出します。
最後に、全員の仮の税額を合計したものが「相続税の総額」となります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
| 出典: 国税庁 No.4155 相続税の税率 | ||
4-4. ステップ4:各相続人の負担額を確定
最後に、ステップ3で算出した「相続税の総額」を、遺言や遺産分割協議で決まった実際の財産の取得割合に応じて、各相続人に割り振ります。
そして、各人が適用できる税額控除(配偶者控除など)を差し引いた金額が、最終的な個人の納税額となります。
5. 配偶者控除や未成年者控除などの使える特例・控除
相続税には、納税者の負担を大きく軽減できる多様な特例や控除制度があります。
これらを活用できるかで納税額が大きく変わります。
相続税をできるだけ軽減したい場合には、これらの特例や控除制度を漏れなく検討することが不可欠です。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)、未成年者控除、障害者控除など、適用要件を満たせば税負担を軽減できる手段は多岐にわたります。
特例や控除は一つだけでなく、複数を組み合わせて適用できる場合もあるため、全体の相続税額を大きく下げられる可能性があります。
ただし、これらの特例を受けるには、原則として申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに相続税の申告が必要となる点に注意が必要です。
5-1. 配偶者の税額軽減 — 1億6,000万円までが無税に
配偶者の税額軽減は、相続税の特例の中でも特に効果が大きく、配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額まで、相続税がかからないという制度です(相続税法第19条の2)。
これは基礎控除とは全く別の制度で、併用が可能です。
この特例により、配偶者が多くの財産を受け取っても、配偶者自身の相続税は0円となるケースが少なくありません。
5-2. 未成年者控除・障害者控除
未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用され、「(18歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円」が控除されます(令和4年4月1日以降の相続)。
障害者控除は、相続人が障害者の場合に適用され、「(85歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円(特別障害者の場合は20万円)」が控除されます。
どちらも相続人の生活保障を目的としており、家族構成によっては大きな節税につながります。
5-3. 相次相続控除
相次相続控除は、10年以内に相次いで相続が発生した場合(例:父の相続の後、数年で母の相続が発生)に、前回の相続で課された相続税の一部を今回の相続税額から差し引ける制度です。
短期間に相続が重なることによる過大な税負担を調整するために設けられています。
6. 小規模宅地等の特例と不動産評価額の圧縮
ご自宅など居住用や事業用の宅地を相続する場合、この特例を使えるかどうかで納税額が劇的に変わることがあります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅(居住用)や事業用の宅地を相続する際に、一定の要件を満たせばその土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる、非常に節税効果の高い制度です(租税特別措置法第69条の4)。
特に、都心部など土地の評価額が高額になりやすい地域では、この特例の適用可否が相続税の納税の有無を分けることも少なくありません。
また、土地の評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に計算しますが、土地の形状(不整形地)や接道状況などによって評価額を下げられる場合があります。
専門家と連携しながら適切な評価を行うことで、相続税負担を軽減することが可能です。
6-1. 小規模宅地等の特例の適用条件
この特例が適用されるためには、相続開始時に被相続人が居住用として使用していたことや、相続人が申告期限までその土地を所有し、かつ居住または事業を継続することなど、複数の細かい要件があります。
例えば、別居していた親族が相続する場合(いわゆる「家なき子特例」)は、さらに厳格な要件が課されます。
自宅を引き継ぐ場合は、まずこの特例の適用を検討すべきでしょう。
6-2. 土地の評価を下げるための具体的なポイント
土地の相続税評価額は、国税庁が定める路線価や固定資産税評価額に対する倍率を基に算出されます。
しかし、例えば敷地の形がいびつである(不整形地)、道路に面していない(無道路地)などのマイナス要因がある場合は、評価額を減額できる可能性があります。
これらの評価は専門的な知識を要するため、相続財産に土地が含まれる場合は、相続専門の税理士に相談することが不可欠です。
7. 生前贈与の活用:年間110万円の非課税枠と生前贈与加算の注意点
生前贈与を計画的に行うことで相続財産そのものを減らし、将来の相続税を軽減できますが、注意すべきルールも存在します。
生前贈与は、相続税対策の最も代表的な方法の一つです。
特に「暦年贈与」では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないため、この非課税枠を利用してコツコツと財産を移転していくことで、大きな節税効果が期待できます。
一方、相続が迫ってから急いで贈与を行っても、相続税の計算上、その贈与がなかったものとされてしまう「生前贈与加算」というルールがあるため注意が必要です。
これは、亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を防ぐための制度で、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算して計算されます(相続税法第19条)。
計画的に贈与を実行してこそ、本来の節税効果が得られる点を押さえておきましょう。
7-1. 暦年贈与でコツコツ減らす方法
暦年贈与は、毎年1人あたり110万円までなら贈与税がかからない制度を活用し、長期間にわたって少しずつ財産を移転していく手法です。
例えば、子ども2人に対して10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与すれば、合計2,200万円の財産を非課税で移転できます。
ただし、形式的に子どもの名義にしただけの「名義預金」とみなされると、贈与が認められないケースもあります。
贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を客観的に証明できる形で行うことが重要です。
心配な方は弁護士に相談して、生前贈与を進めると良いでしょう。
7-2. 相続時精算課税制度によるメリット・デメリット
相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与において、累計2,500万円までの特別控除が使える制度です。
まとまった財産を早期に移転できるメリットがありますが、この制度を選択すると暦年贈与の110万円非課税枠は原則使えなくなります。
また、この制度で贈与した財産は、全額が相続時に相続財産に加算されるため、直接的な相続税の節税にはなりにくい側面もあります。
ただし、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与からは、この2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が創設され、その範囲内であれば相続財産への加算も不要となるなど、制度が複雑化しています。
どちらの制度が有利かは、ご家庭の状況によって異なるため、専門家への相談が不可欠です。
8. 相続税申告の流れと期限:10ヶ月以内にすべきこと
相続が発生してから申告・納税までの期限は10ヶ月です。
この期間内に多くの手続きを完了させる必要があります。
相続が開始してから、相続税の申告と納税を行うまでの期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
10ヶ月というと余裕があるように見えますが、相続人の確定、財産調査・評価、遺産分割協議、書類の準備など、やるべきことは山積みで、実際にはあっという間に過ぎてしまいます。
提出が遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。
余計な税金を払うことにならないよう、相続が発生したらすぐに全体のスケジュールを立て、計画的に進めることが大切です。
8-1. 申告に必要な書類と取得方法
相続税の申告には、被相続人や相続人全員の戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金の残高証明書など、多岐にわたる書類が必要になります。
これらは市区町村役場や法務局、金融機関などで取得しますが、収集に時間を要することも多いため、早めに着手することが重要です。
8-2. 納税方法と分割払い(延納・物納)の概要
相続税の納付は、原則として申告期限までに現金で一括納付します。
しかし、納税額が多額で現金での一括納付が困難な場合には、一定の要件のもとで「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納付)という制度を利用できる場合があります。
ただし、延納には利子税がかかり、物納は適用要件が非常に厳しいため、利用できるケースは限られます。
9. 相続税対策に税理士や弁護士は必要?専門家に頼むメリット
相続税は制度が非常に複雑なため、専門家のサポートを得ることでミスやトラブルを防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。
相続税の計算や申告は、専門家でなければ判断が難しいポイントが数多くあります。
税理士や弁護士に依頼すれば、正確な財産評価、適用可能な特例の見極め、複雑な申告書の作成まで、一貫してサポートを受けることができます。
結果として、ご自身で申告するよりも納税額を抑えられたり、将来の税務調査のリスクを減らせたりするのが大きなメリットです。
とくに、相続人間で意見が対立している、あるいはその可能性がある場合には、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、円満な遺産分割協議を進める手助けとなります。
9-1. 相続財産の洗い出しから計算までのサポート
税理士は財産評価のプロフェッショナルであり、特に不動産や非上場株式といった評価が難しい財産の相続税評価額を、法律に則って適正に算出します。
正確な財産目録の作成や相続税シミュレーションを依頼することで、ご自身で行うよりも信頼性が高く、手続きにかかる時間も大幅に短縮できます。
9-2. トラブル回避のための遺産分割調整
弁護士は、相続人間の意見が対立した場合に、法律の専門家として中立的な立場から調整を行い、円満な遺産分割協議をサポートします。
協議が難航するケースでも、法的な落とし所を迅速に見つけ、家庭裁判所での調停や審判に発展する前段階での解決を目指します。
財産分割で揉めることは、精神的にも時間的にも大きな負担となるため、専門家の関与は非常に大きな意味を持ちます。
10. まとめ:早めの準備が相続税リスクを軽減する
相続税の負担は、遺産の総額だけでなく、ご家族の構成や事前の対策によって大きく変わります。
「相続税はいくらまで無税か」という問いへの答えは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下かどうかが最初の判断基準です。
まずはご自身の家族構成で基礎控除額がいくらになるかを確認し、おおよその財産額と比べることから始めましょう。
そして、もし基礎控除を超える可能性があるなら、生前贈与や生命保険の活用、あるいは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった制度を正しく理解し、活用できるかを検討することが重要です。
「まだ先の話」と思わず、早めに情報を収集し、必要であれば専門家のアドバイスを受けながら、ご家族にとって最適な相続プランを立てておくことが、円満な相続と無用な税負担を避けるための最善の策と言えるでしょう。
たちばな総合法律事務所には、元国税審判官の経歴を持ち、税理士登録もしている弁護士が在籍しています。
そのため、遺産分割でトラブルになっている複雑な案件でも、税務と法務の両面からワンストップで最適なサポートをご提供できるのが大きな強みです。
当事務所は、こうした相続トラブルのある、相続税申告に強みがあります。
弁護士・税理士の視点からアドバイス、サポートをおこなっています。
また、初回無料で、相続問題の法律相談をおこなっています。
ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、電話での相談も実施しておりますが、相続税に関してはご事情、資産状況などをお伺いしなければアドバイスが難しいため、相続税額のシミュレーションなどについては来所でのご相談をお願いしております。
事前のご予約を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2026.2.24
- 相続放棄を検討中の方必見!不動産の管理義務と手続きの基本を総まとめ
- 2026.2.16
- 【弁護士監修】兄弟の遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点(割合・順位・トラブル対策)
- 2026.2.16
- 遺産相続でもめる原因・対策・解決法を徹底解説
- 2026.2.16
- 子なし夫婦の相続はどうなる?相続先・相続割合・トラブル回避策まで詳しく解説
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント