大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法を徹底解説
- 相続税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法を徹底解説
- 1. 相続税の概要:そもそもどんな仕組み?
- 2. 相続税はいくらからかかる?基礎控除の基本を押さえよう
- 3. 相続税の対象となる財産・対象外の財産
- 4. 相続税はどう計算する?課税遺産総額から納付額までの流れ
- 5. 相続税がかからない・減額される主な特例
- 6. 相続税の申告は必要?不要?判断のポイント
- 7. 生前贈与がある場合の相続税はいくらからかかる?
- 7-1.【令和5年度税制改正】3年から7年に延長された生前贈与加算に注意
- 8. 実際に相続税がいくらから発生するのか?シミュレーション事例
- 9. 相続税の申告手続きと期限
- 10. 税理士・専門家への相談はいつ必要?メリットと選び方
- 11. まとめ:相続税はいくらからかかるのか正しく把握して安心を
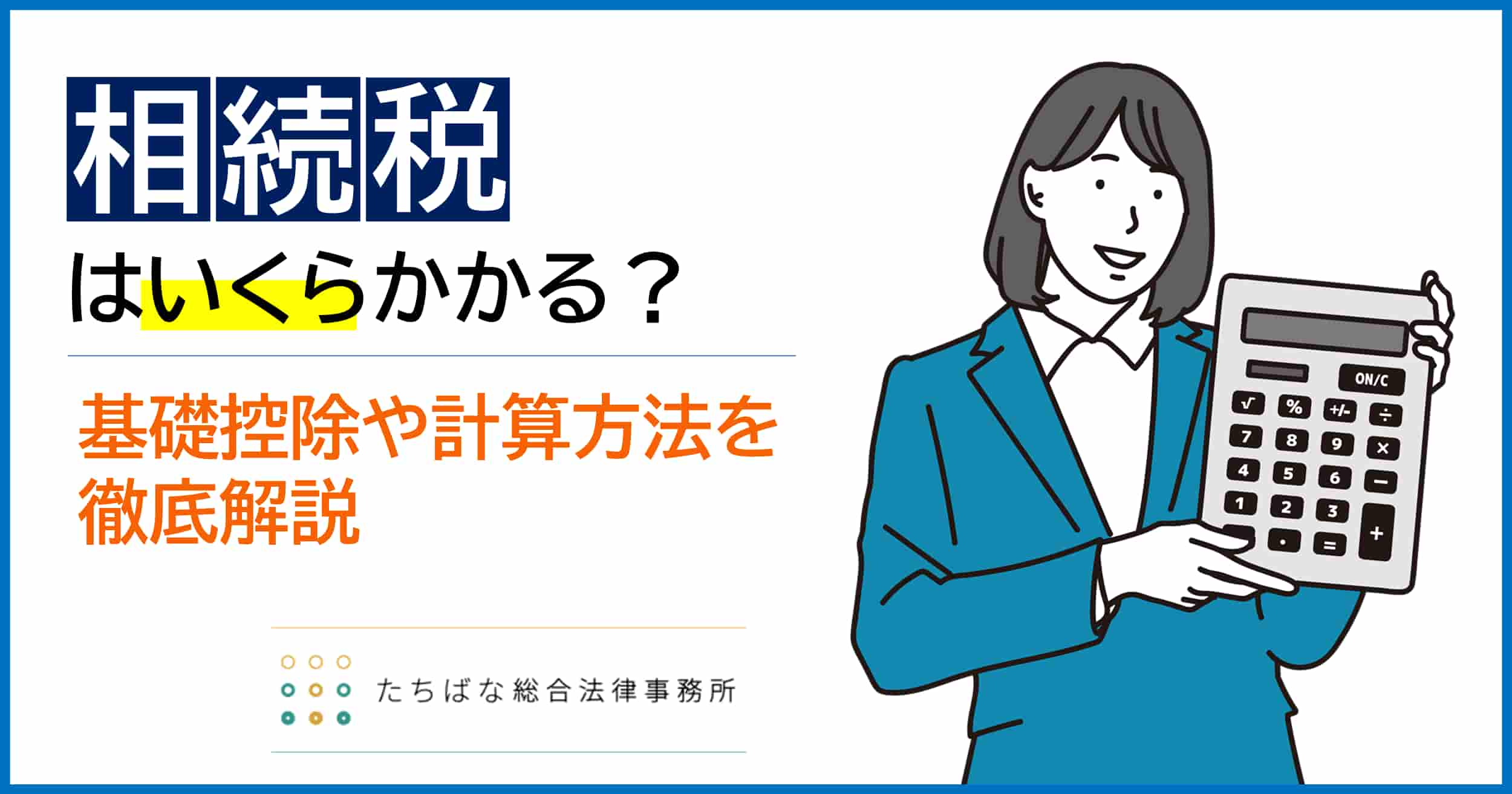
相続税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法を徹底解説
相続税は、大切なご家族が遺した財産を受け継ぐ際に課される税金です。
「うちは財産家ではないから関係ない」
「一体いくらから相続税がかかるの?」
という考えや疑問をお持ちの方は非常に多いでしょう。
国税庁の令和4年分の統計によれば、亡くなった方のうち相続税の申告書が提出された割合は9.6%と、実際に相続税が課税されるのは約10人に1人です。
しかし、都心に不動産をお持ちの場合など、財産の種類は少なくても評価額が高くなるケースでは、相続税申告が必要になることも少なくありません。
本記事では、相続税の仕組みや、「いくらからかかるか」の基準となる基礎控除の計算方法、対象財産の範囲、そして申告手続きまで、法律と税務の専門家が分かりやすく徹底解説します。
基本的な考え方を押さえ、ご自身の状況と照らし合わせながら、適切な相続への備えを進めましょう。
1. 相続税の概要:そもそもどんな仕組み?
まずは相続税の基本的な仕組みを理解しましょう。
対象となる財産や課税の流れを押さえることで、具体的な対策が立てやすくなります。
相続税とは、親や配偶者などの亡くなった方(法律用語で「被相続人」といいます)が遺した財産を受け取る人(相続人)が支払う税金です。
相続によって取得した財産の総額(課税価格)をベースに、借入金などの債務を差し引き、後述する基礎控除を引いた残りの金額に対して課税されます。
財産には、不動産(土地・建物)や預貯金、有価証券のほか、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金も「みなし相続財産」として一部含まれる点がポイントです。
実際には、多くのご家庭で相続税を支払う必要はありません。
それは、相続税の計算において、非常に大きな非課税枠である「基礎控除」が設けられているからです。
2. 相続税はいくらからかかる?基礎控除の基本を押さえよう
相続税がかかるかどうかの最初の判断基準となるのが「基礎控除」です。
遺産総額がこの基礎控除額を超えた部分に対してのみ相続税が課税されるため、この仕組みを正しく理解しておくと、ご自身の相続における納税額の見通しが立てやすくなります。
2-1. 基礎控除の計算式
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます(相続税法第15条)。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 ×法定相続人の数)
この計算式で最も重要なのが「法定相続人の数」です。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことで、配偶者と、以下の順位で決まる血族です。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) |
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
たとえば、配偶者と子どもが2人いるご家庭では、法定相続人の合計は3人です。
この場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
相続財産の総額がこの4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も原則として不要です。
2-2. 最低ラインは3,600万円?実際の注意点と誤解
しばしば「相続税はいくらから? 3,600万円以下ならかからない」と言われますが、これは法定相続人が1人(例えば子1人のみ)の場合(=3,000万円+600万円×1人=3,600万円)を想定したものです。
実際には法定相続人が増えれば基礎控除額も大きくなり、そのぶん相続税が課されるボーダーラインも上がります。
法定相続人の人数を誤ってカウントすると、不要な申告をしてしまったり、逆に本来必要な申告を見逃して後からペナルティを受けたりする可能性があるので、正確に確認することが重要です。
例えば、相続人の一人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしても、税法上の基礎控除額の計算においては、その放棄がなかったものとして相続人の数に含めて計算します。
このように、民法上の考え方と税法上の考え方が異なるケースもあるため、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。
3. 相続税の対象となる財産・対象外の財産
相続税はすべての財産に課税されるわけではありません。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた上で、さらに非課税となる財産を除外して計算します。
相続税のかかる財産には、土地や家屋などの不動産、預貯金や株式などの金融資産がまず挙げられます。
さらに、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金なども「みなし相続財産」として課税対象に含まれる場合があるため注意が必要です(相続税法第3条第1項第1号・同2号)。
一方で、お墓や仏壇・仏具といった祭祀財産は非課税であり、これらは相続税を計算する際の課税対象からは除外されます。
どの財産がどのように評価されるのかを把握することで、相続税がいくらから発生しそうかをより正確に予測できます。
3-1. プラスの財産:不動産・預貯金・有価証券など
相続税の課税対象となるプラスの財産には、不動産のほかに、預貯金や株式、投資信託、国債などの有価証券が含まれます。
これらは国税庁が定める財産評価基本通達に基づき、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価で評価され、相続税評価額が算出されます。
特に不動産は、土地であれば路線価や倍率方式、建物であれば固定資産税評価額など、評価方法が複雑なため、専門知識が求められます。
【見落としやすい「みなし相続財産」】
被相続人が亡くなったことで受け取る生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金は、厳密には相続財産ではありませんが、実質的に相続と同じ効果があるため「みなし相続財産」として課税対象になります。
ただし、これらには遺族の生活保障という側面から、以下の非課税限度額が設けられています。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が3人なら、生命保険金と死亡退職金それぞれで1,500万円までが非課税となります。この非課税枠を超える部分だけが課税対象です。
3-2. マイナスの財産:債務や葬式費用はどう計上する?
相続ではプラスの財産だけでなく、被相続人が遺した借入金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産も引き継ぎます。
これらの債務は、相続税の計算上、プラスの財産の合計額から差し引くことができます(債務控除)。
さらに、被相続人の葬式費用(通常、葬儀本体の費用やお布施などが対象で、香典返しや法事の費用は含まれません)も控除対象となるため、支払いに関する領収書は必ず保管しておきましょう。
4. 相続税はどう計算する?課税遺産総額から納付額までの流れ
基礎控除額を理解したら、次に実際に相続税を計算する手順を見ていきましょう。
相続税の計算は少し複雑ですが、以下の3ステップで進みます。
この流れは、まず「相続全体でかかる税金の総額」を算出し、それを「各相続人が実際に相続した割合で分け合う」という考え方に基づいています。
4-1. 遺産総額の計算と課税遺産総額の出し方
まず、相続税計算の元となる「課税遺産総額」を算出します。
課税遺産総額 = (プラスの財産の合計額 – マイナスの財産・葬式費用の合計額) – 基礎控除額
計算式の前半部分(プラスの財産 – マイナスの財産)が「正味の遺産額」です。
この正味の遺産額が基礎控除額を上回った場合に、その超えた部分が課税遺産総額となります。
小さい額であっても対象となる資産はもれなく計上が必要となるため、専門家である税理士などと協力しながら財産の洗い出しを慎重に行うことが重要です。
4-2. 相続税の総額と各相続人が負担する税額
課税遺産総額が確定したら、次に税額を計算します。
仮の按分
課税遺産総額を、いったん法定相続分で分割したと仮定して、各相続人の取得金額を算出します。
税額の算出
各人の仮の取得金額に、定められた税率を掛けて、それぞれの仮の相続税額を計算します。
総額の計算
全員の仮の相続税額を合計します。これが「相続税の総額」です。
実際の按分
最後に、この相続税の総額を、実際に財産を相続した割合に応じて各相続人に割り振り、それぞれの最終的な納税額を確定させます。
配偶者には後述する「配偶者の税額軽減」という非常に大きな控除が適用されるため、この最終段階で税額が0円になるケースも珍しくありません。
5. 相続税がかからない・減額される主な特例
相続税には、納税者の負担を軽減するための各種特例が用意されており、要件を満たせば納税額を大きく減額できる場合があります。
相続税をできるだけ軽減したい場合には、これらの特例や控除制度を漏れなく検討することが不可欠です。
特に「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」は節税効果が絶大です。
ただし、これらの特例の適用には厳格な要件があるため、税理士や弁護士といった専門家のアドバイスのもと、慎重に判断する必要があります。
5-1. 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、遺族のその後の生活を守るため、非常に手厚い税額軽減制度が設けられています(相続税法第19条の2)。
具体的には、配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、相続税はかかりません。
このため、多くの場合、配偶者の相続税は0円となります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、納税額が0円でも期限内に相続税の申告手続きが必要な点に注意が必要です。
相続税の申告書を税務署に提出し、「この特例を適用して、税額が0円になります」と正式に意思表示と計算過程を示すことによってはじめて、その適用が認められる仕組みになっています。
つまり、相続税申告書が、この特例の「申請書」の役割を兼ねています。
手続名相続税の申告
概要配偶者の税額軽減の規定の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書(その申告書に係る期限後申告書および修正申告書を含みます。)に、戸籍謄本など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
根拠条文等相法19の2、32、相令4、相規1の6、16、措法69、70の2の2、措令40の4
5-2. 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅(居住用)や事業用の宅地など、一定の要件を満たす土地の相続税評価額を最大で80%減額できるという制度です(租税特別措置法第69条の4)。
例えば、評価額5,000万円の居住用の土地にこの特例が適用できれば、評価額は1,000万円(5,000万円 × 80%減)にまで圧縮され、相続税を劇的に減らすことができます。
ただし、相続する親族の居住要件や事業継続要件など、適用ルールが非常に細かく複雑なため、専門家に相談して誤りなく適用することが極めて重要です。
5-3. 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除
上記2つの代表的な特例のほかにも、個別の状況に応じて利用できる控除があります。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合に適用され、成人するまでの年数に応じた額が控除されます。
障害者控除
相続人が障害者の場合に適用され、85歳になるまでの年数に応じた額が控除されます。
相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生した場合に、前回の相続で課された相続税の一部を今回の相続税から差し引ける制度です。
6. 相続税の申告は必要?不要?判断のポイント
遺産総額が基礎控除額以下に収まれば、相続税の申告は原則として不要です。
ただし、最も注意すべきなのは、5-1で解説した「配偶者の税額軽減」や5-2の「小規模宅地等の特例」を適用する場合です。
これらの特例を使った結果、納税額が0円になるケースでも、「特例を適用します」という意思表示のために相続税の申告が義務付けられています。
「基礎控除の範囲内だ」と思い込んでいても、生命保険金など見落としている財産がある可能性も考慮し、申告の要否は専門家に相談して正確に判断するのが最も安全です。
7. 生前贈与がある場合の相続税はいくらからかかる?
生前贈与は有効な相続税対策ですが、亡くなる直前の贈与は相続税の計算に影響を与えるため注意が必要です。
贈与税の暦年課税(年間110万円まで非課税)を利用して資産を移転していく生前贈与は、相続税対策として広く知られています。
しかし、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた贈与については、相続税の課税対象に加算される(持ち戻される)仕組みがあります。
7-1.【令和5年度税制改正】3年から7年に延長された生前贈与加算に注意
亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を防ぐため、相続開始前の一定期間内の贈与はなかったものとみなされ、相続財産に加算されます。
この期間が、令和5年度税制改正により、従来の3年から段階的に7年に延長されることになりました。
具体的には、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与がこの新しいルールの対象となります。
延長された4年間の贈与については合計100万円の控除がありますが、今後の生前贈与は、より長期的かつ計画的に行うことが重要になります。
この贈与財産について既に贈与税を支払っている場合は、相続税額からその贈与税額控除を受けることができ、二重課税はされません。
8. 実際に相続税がいくらから発生するのか?シミュレーション事例
実際の事例を挙げながら、どのくらいの財産額で相続税がいくら発生するのかをイメージしやすく解説します。
ここでは、代表的な家族構成における相続税の概算額を早見表で紹介します。
ご自身の状況に近いものを参考にしてください。
※以下の金額は、法定相続分で分割し、配偶者の税額軽減を適用した後の、相続人全体の合計納税額の目安です。個別の特例は考慮していません。
なお、次のコラムで、相続人のパターン別で遺産総額に対する相続税の早見表を掲載しています。
【ケース1:相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)】
基礎控除額:4,800万円
遺産総額5,000万円未満であれば、相続税はかからない可能性が高いです。
| 遺産総額 | 相続税の合計額(目安) |
|---|---|
| 6,000万円 | 60万円 |
| 8,000万円 | 175万円 |
| 1億円 | 315万円 |
【ケース2:相続人が子2人のみ(法定相続人2人)】
基礎控除額:4,200万円
遺産総額4,000万円未満であれば、相続税はかからない可能性が高いです。
| 遺産総額 | 相続税の合計額(目安) |
|---|---|
| 6,000万円 | 180万円 |
| 8,000万円 | 470万円 |
| 1億円 | 770万円 |
このように、相続人の構成によって納税額は大きく変わります。
また、これはあくまでシミュレーションであり、不動産の相続税評価額や特例の有無で実際の負担額は変動するため、正確な金額は専門家にご相談ください。
9. 相続税の申告手続きと期限
相続税の申告には厳格な期限があり、手続きに必要な書類も多岐にわたります。
全体の流れを把握してスムーズに進めましょう。
9-1. 相続開始から10か月が期限!申告の流れと必要書類
相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期限は、遺産分割協議が長引いている等の理由があっても原則として延長されません。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生するため注意が必要です。
一般的な申告の流れは以下の通りです。
申告には、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、財産評価に関する書類など、非常に多くの書類が必要です。
不備があると手続きが滞るだけでなく、特例を受けられなくなる恐れもあるため、専門家と協力しながら細心の注意を払って進めましょう。
10. 税理士・専門家への相談はいつ必要?メリットと選び方
相続に関する手続きや税金の計算は非常に複雑なため、少しでも不安があれば専門家への相談が有効です。
小規模宅地等の特例や生前贈与の加算など、相続税の計算には専門的な判断が求められる場面が数多くあります。
早い段階で専門家に相談することで、申告書の作成ミスを防ぎ、適用できる特例を漏れなく活用し、将来的な税務調査のリスクを回避できる可能性が高まります。
10-1. 相談先の種類と費用相場
相続税に詳しい専門家としては、税理士が第一の相談先となります。
税務申告の代理は税理士の独占業務です。
もし遺産分割で親族間の争いがある場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野です。
費用は案件の規模によって変動しますが、一般的には遺産総額の一定割合を目安に報酬が設定される場合が多いです。
10-2. 依頼前に確認しておきたいこと
専門家を選ぶときは、相続税申告の実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。
料金体系やサービス内容を事前に明確に提示してくれる、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。相続税の申告には10か月というタイトな期限があるため、相続が発生したらなるべく早い段階で相談を開始することをおすすめします。
11. まとめ:相続税はいくらからかかるのか正しく把握して安心を
相続税の仕組みや控除、特例、申告手続きの流れを理解し、適切な相続対策に役立てましょう。
「相続税はいくらからかかるのか」という問いの答えは、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
このボーダーラインを正しく理解し、ご自身の財産状況と照らし合わせることが、相続対策の第一歩です。
相続が発生した場合でも、落ち着いて財産を整理し、適用できる特例や控除を漏れなく活用すれば、過度な税負担を避けることができます。
10か月という限られた時間の中で、複雑な手続きをミスなく完了させるためにも、必要に応じて相続を専門とする税理士などの専門家のサポートを活用することを強くおすすめします。
たちばな総合法律事務所には、元国税審判官の経歴を持ち、税理士登録もしている弁護士が在籍しています。
そのため、遺産分割でトラブルになっている複雑な案件でも、税務と法務の両面からワンストップで最適なサポートをご提供できるのが大きな強みです。
当事務所は、こうした相続トラブルのある、相続税申告に強みがあります。
弁護士・税理士の視点からアドバイス、サポートをおこなっています。
また、初回無料で、相続問題の法律相談をおこなっています。
ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、電話での相談も実施しておりますが、相続税に関してはご事情、資産状況などをお伺いしなければアドバイスが難しいため、相続税額のシミュレーションなどについては来所でのご相談をお願いしております。
事前のご予約を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
税トラブル に関する解決事例
- 2025.10.22
- 生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ
- 2025.10.20
- 『土地相続税』を徹底解説:評価額・計算方法・控除やトラブル対策まで
- 2025.10.17
- 相続税の申告期限を徹底解説!押さえておくべきポイントと対処法
- 2025.10.17
- 相続税はいくらまで無税?基礎控除の仕組みと申告の判断ポイント
- 2025.10.15
- 相続税早見表で一目でわかる!相続税の概要と計算の流れ






















































