大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税早見表で一目でわかる!相続税の概要と計算の流れ
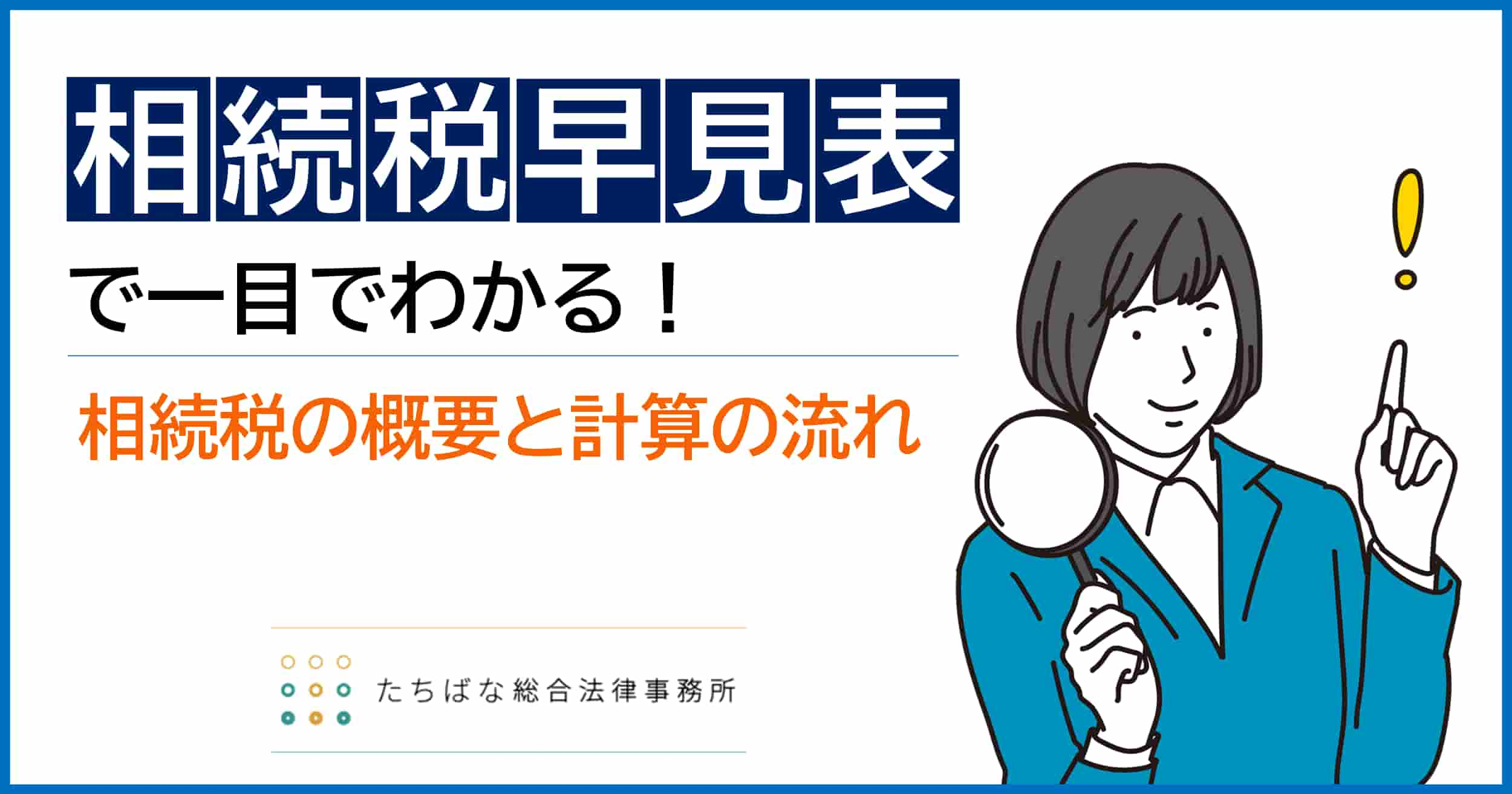
相続税早見表で一目でわかる!相続税の概要と計算の流れ
相続は、多くの方にとって人生でそう何度も経験することではありません。
いざその場面に直面したとき、
「相続税は一体いくらかかるのだろう」
「手続きはどうすればいいのか」
といった不安を感じる方は非常に多いです。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産を受け継ぐ際に課される税金ですが、その計算や手続きは非常に複雑です。
預貯金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も考慮し、さらには生命保険金や死亡退職金のような「みなし相続財産」も課税対象に含まれます。
一方で、お墓や仏具などの非課税財産や、様々な税額控除・特例も存在するため、全体像を正確に把握するのは簡単ではありません。
こうした知識が不足していると、申告が必要にもかかわらず見落としてしまい、後から追徴課税などのペナルティが課される、あるいは適用できたはずの特例を使えず、本来より多くの税金を納めてしまうといったリスクが生じます。
相続税を正しく計算する基本的な流れは、以下の3ステップです。
課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)を求める
法定相続分で分けたと仮定して、相続税の総額を計算する
実際の分割割合に応じて各人の納税額を算出し、控除や特例を適用する
この手順を踏むことで、実際の納税額を導き出せますが、ご家族の構成や財産の種類によって結果は大きく異なります。
本記事では、まず「相続税早見表」を使ってご自身のケースのおおよその税額を把握する方法を紹介します。
その上で、早見表だけではわからない正確な計算ステップ、有利な特例、そして見落としがちな注意点まで、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
最後までお読みいただくことで、相続税の全体像を理解し、来るべき相続に備えるための具体的な第一歩を踏み出せるはずです。
1. 相続税早見表の基本:どんな場面で使うのか
相続税早見表は、遺産の総額(遺産額)やご家族の状況に応じて、おおよその相続税額を手軽に把握できる便利なツールです。
まずは、この早見表がどのような場面で役立ち、どのように活用すべきかを解説します。
早見表のメリットと使い方
相続税の計算が複雑なのは、「基礎控除」という非課税枠があるためです。
財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が奥様と子供2人(合計3人)の場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
このように、相続税額は相続人の数によって変動します。
相続税早見表は、遺産総額と相続人の構成という2つの要素から、概算税額を素早く確認できる点に最大のメリットがあります。
親族の相続が近い将来に想定される場合、まず早見表で「我が家の場合は、税金がかかりそうか」「かかるとしたらいくら位か」という当たりをつけることで、漠然とした不安を解消し、具体的な対策を考えるきっかけになります。
【重要】早見表の注意点と限界
手軽で便利な早見表ですが、あくまでシミュレーションツールの一つであり、いくつかの重要な注意点があります。
多くの早見表は、民法で定められた「法定相続分」通りに遺産を分割したと仮定して計算されています。
しかし、遺言があったり、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で分割割合が変わったりすれば、各人が実際に負担する税額も変動します。
したがって、早見表は「我が家の相続税を考えるための第一歩」と位置づけ、あくまで大まかな目安として活用しましょう。
正確な税額を知るためには、この記事で後述する正式な計算方法を理解することが不可欠です。
2. 相続人の人数と関係別早見表:配偶者・子・親・兄弟姉妹など
相続税額は、誰が相続人になるかによって大きく変動します。
ここでは、相続の基本ルールである「法定相続人」と、代表的な家族構成ごとの早見表を具体的に見ていきましょう。
誰が相続人になる?法定相続人の順位と相続分
誰が財産を相続する権利を持つか(法定相続人)と、その取り分(法定相続分)は、民法で定められています。
亡くなった方の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、以下の順位で相続人になります。
| 順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(子が既に亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 直系尊属(親、親が亡くなっている場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪) |
上位の順位の人が1人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません(例:子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にならない)。
2-1.【早見表】 相続人が「配偶者と子ども」の場合
最も一般的な相続パターンです。
このケースの最大のポイントは「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度が使えることです。
これにより、配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までであれば、配偶者の相続税はかかりません。
そのため、多くの場合、相続税の負担は主に子どもにかかってきます。
以下の早見表は、遺産を法定相続分(配偶者1/2、子ども全体で1/2)で分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税の合計額の目安です。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人「配偶者+子」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |||
| 4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 | 0 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
| 1億2,000万円 | 580万円 | 480万円 | 403万円 | 350万円 |
| 1億4,000万円 | 780万円 | 655万円 | 577万円 | 500万円 |
| 1億6,000万円 | 1,070万円 | 860万円 | 767万円 | 675万円 |
| 1億8,000万円 | 1,370万円 | 1,100万円 | 993万円 | 900万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
| 4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 5億5,000万円 | 8,730万円 | 7,617万円 | 6,899万円 | 6,437万円 |
| 6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,837万円 | 7,375万円 |
| 6億5,000万円 | 1億1,000万円 | 9,745万円 | 8,774万円 | 8,312万円 |
| 7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,884万円 | 9,300万円 |
2-2. 【早見表】相続人が「子どものみ」の場合
配偶者が既に亡くなっている場合など、子どもだけが相続人となるケースです。
この場合、「配偶者の税額軽減」が使えないため、同じ遺産額でも「配偶者と子ども」のケースに比べて納税額は高くなる傾向があります。
以下の表は、子どもだけが相続する場合の相続税の合計額の目安です。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人「子のみ」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |||
| 4,000万円 | 40万円 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万円 | 0 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万円 | 490万円 |
| 1億2,000万円 | 1,820万円 | 1,160万円 | 930万円 | 790万円 |
| 1億4,000万円 | 2,460万円 | 1,560万円 | 1,239万円 | 1,090万円 |
| 1億6,000万円 | 3,260万円 | 2,140万円 | 1,639万円 | 1,390万円 |
| 1億8,000万円 | 4,060万円 | 2,740万円 | 2,040万円 | 1,720万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,979万円 | 6,080万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979万円 | 7,580万円 |
| 4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
| 5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
| 6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
| 6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
子どもが複数人いる場合、基礎控除額が増えるだけでなく、相続税の総額を計算する際にも税率が低く抑えられるため、合計額は大きく軽減されます。
しかし、遺産に不動産が多く含まれると、子どもたちの間で公平に分けるのが難しく、トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。
2-3. 【早見表】相続人が「配偶者と直系尊属(親)」の場合
亡くなった方に子どもがいない場合、配偶者と親(第2順位)が相続人となります。
この場合も「配偶者の税額軽減」は適用可能です。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人「配偶者+直系尊属(父母・祖父母)」の場合 | |
|---|---|---|
| 両親1人 | 両親2人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |
| 4,000万円 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 26万円 | 6万円 |
| 6,000万円 | 63万円 | 40万円 |
| 7,000万円 | 108万円 | 81万円 |
| 8,000万円 | 156万円 | 125万円 |
| 9,000万円 | 210万円 | 170万円 |
| 1億円 | 271万円 | 222万円 |
| 1億2,000万円 | 400万円 | 340万円 |
| 1億4,000万円 | 571万円 | 500万円 |
| 1億6,000万円 | 749万円 | 666万円 |
| 1億8,000万円 | 926万円 | 833万円 |
| 2億円 | 1,131万円 | 1,005万円 |
| 2億5,000万円 | 1,742万円 | 1,545万円 |
| 3億円 | 2,353万円 | 2,100万円 |
| 3億5,000万円 | 2,982万円 | 2,660万円 |
| 4億円 | 3,705万円 | 3,326万円 |
| 4億5,000万円 | 4,426万円 | 3,993万円 |
| 5億円 | 5,158万円 | 4,662万円 |
| 5億5,000万円 | 5,935万円 | 5,384万円 |
| 6億円 | 6,713万円 | 6,106万円 |
| 6億5,000万円 | 7,495万円 | 6,831万円 |
| 7億円 | 8,301万円 | 7,608万円 |
親が高齢で、今回の相続(一次相続)で親が財産を受け継いでも、遠からずその親が亡くなり、次の相続(二次相続)が発生する可能性がある場合、二次相続まで見据えた遺産分割を検討することが重要です。
2-4.【早見表】相続人が「直系尊属のみ」の場合
亡くなった方に配偶者も子(や孫など)もいない場合、第2順位である親や祖父母といった「直系尊属」が相続人となります。
このケースでは、最も節税効果の大きい「配偶者の税額軽減」を適用することはできません。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合とは異なり、親(父母)は被相続人の一親等の血族にあたるため、相続税額が割増になる「2割加算」の対象外です。
しかし、相続人となるのが祖父母の場合、2割加算の対象となるため注意が必要です。
税額の計算方法は「子どものみ」の場合と似ていますが、相続人となる親の人数(1人か2人か)によって基礎控除額が変わる点がポイントとなります。
相続人である親が高齢なケースも多く、納税資金の準備や次の相続(二次相続)への影響も考慮しておくとよいでしょう。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人「父母のみ」の場合 | |
|---|---|---|
| 親1人 | 親2人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |
| 4,000万円 | 40万円 | 0 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 |
| 1億2,000万円 | 1,820万円 | 1,160万円 |
| 1億4,000万円 | 2,460万円 | 1,560万円 |
| 1億6,000万円 | 3,260万円 | 2,140万円 |
| 1億8,000万円 | 4,060万円 | 2,740万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 |
| 3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 |
| 4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 |
| 5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 |
| 6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 |
| 6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 |
2-5. 【早見表】相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合
亡くなった方に子や親(直系尊属)がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースです。
この場合も「配偶者の税額軽減」は利用できますが、注意すべきなのは兄弟姉妹が負担する相続税です。
兄弟姉妹は「相続税額の2割加算」の対象となるため、計算された税額からさらに2割増しの金額を納税する必要があります。
また、兄弟姉妹は遺留分(最低限の遺産取得を主張できる権利)がないため、被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を遺していた場合、兄弟姉妹は財産を一切相続できません。
このケースは、被相続人の意思(遺言)が特に重要になると言えるでしょう。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |||
| 4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0 | 0 |
| 6,000万円 | 59万円 | 36万円 | 18万円 | 0 |
| 7,000万円 | 100万円 | 76万円 | 51万円 | 30万円 |
| 8,000万円 | 142万円 | 117万円 | 92万円 | 68万円 |
| 9,000万円 | 195万円 | 160万円 | 134万円 | 109万円 |
| 1億円 | 251万円 | 213万円 | 182万円 | 150万円 |
| 1億2,000万円 | 389万円 | 330万円 | 286万円 | 255万円 |
| 1億4,000万円 | 547万円 | 484万円 | 435万円 | 390万円 |
| 1億6,000万円 | 704万円 | 642万円 | 585万円 | 540万円 |
| 1億8,000万円 | 879万円 | 800万円 | 737万円 | 690万円 |
| 2億円 | 1,089万円 | 999万円 | 923万円 | 855万円 |
| 2億5,000万円 | 1,620万円 | 1,505万円 | 1,430万円 | 1,354万円 |
| 3億円 | 2,182万円 | 2,016万円 | 1,936万円 | 1,860万円 |
| 3億5,000万円 | 2,792万円 | 2,581万円 | 2,475万円 | 2,392万円 |
| 4億円 | 3,410万円 | 3,162万円 | 3,038万円 | 2,955万円 |
| 4億5,000万円 | 4,044万円 | 3,747万円 | 3,614万円 | 3,518万円 |
| 5億円 | 4,756万円 | 4,422万円 | 4,246万円 | 4,125万円 |
| 5億5,000万円 | 5,469万円 | 5,097万円 | 4,883万円 | 4,747万円 |
| 6億円 | 6,181万円 | 5,772万円 | 5,521万円 | 5,385万円 |
| 6億5,000万円 | 6,894万円 | 6,447万円 | 6,158万円 | 6,022万円 |
| 7億円 | 7,606万円 | 7,122万円 | 6,830万円 | 6,660万円 |
2-6. 【早見表】相続人が「兄弟姉妹だけ」の場合
亡くなった方に子どもも親もいない場合、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
このケースには2つの重要な注意点があります。
- 配偶者や子と比べて基礎控除以外の優遇措置が少ない。
- 相続税額が2割加算される。(詳細は後述)
これらの理由から、他のパターンに比べて税負担が重くなる傾向にあります。
| 相続財産 (基礎控除前) |
相続人が「兄弟姉妹のみ」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |
| 3,600万円以下 | 相続税はかかりません(基礎控除の範囲内) | |||
| 4,000万円 | 48万円 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 192万円 | 96万円 | 23万円 | 0 |
| 6,000万円 | 372万円 | 216万円 | 144万円 | 72万円 |
| 7,000万円 | 576万円 | 384万円 | 263万円 | 192万円 |
| 8,000万円 | 816万円 | 564万円 | 395万円 | 312万円 |
| 9,000万円 | 1,104万円 | 744万円 | 576万円 | 432万円 |
| 1億円 | 1,464万円 | 924万円 | 755万円 | 588万円 |
| 1億2,000万円 | 2,184万円 | 1,392万円 | 1,116万円 | 948万円 |
| 1億4,000万円 | 2,952万円 | 1,872万円 | 1,487万円 | 1,308万円 |
| 1億6,000万円 | 3,912万円 | 2,568万円 | 1,967万円 | 1,668万円 |
| 1億8,000万円 | 4,872万円 | 3,288万円 | 2,448万円 | 2,064万円 |
| 2億円 | 5,832万円 | 4,008万円 | 2,951万円 | 2,544万円 |
| 2億5,000万円 | 8,316万円 | 5,904万円 | 4,751万円 | 3,744万円 |
| 3億円 | 1億1,016万円 | 8,304万円 | 6,552万円 | 5,496万円 |
| 3億5,000万円 | 1億3,800万円 | 1億704万円 | 8,375万円 | 7,296万円 |
| 4億円 | 1億6,800万円 | 1億3,104万円 | 1億775万円 | 9,096万円 |
| 4億5,000万円 | 1億9,800万円 | 1億5,552万円 | 1億3,176万円 | 1億896万円 |
| 5億円 | 2億2,800万円 | 1億8,252万円 | 1億5,575万円 | 1億3,248万円 |
| 5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
| 6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
| 6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
兄弟姉妹間の相続は、関係性が疎遠になっていることも多く、遺産分割で揉めやすい傾向があります。
被相続人が生前に遺言書を作成しておくなど、事前の対策が特に重要となるケースです。
3. 相続税の計算方法と税率:早見表だけではわからないポイント
早見表で概算を掴んだら、次はより正確な税額を知るための具体的な計算方法を理解しましょう。
実際の計算は、以下の3つのステップで進めます。
ここでは、【遺産総額1億円、相続人は配偶者と子2人】というモデルケースで、実際に計算してみましょう。
3-1. ステップ1:課税遺産総額の算定
まず、相続税の計算の土台となる「課税遺産総額」を確定させます。
課税遺産総額 = ①正味の遺産額 - ②基礎控除額
① 正味の遺産額の計算
正味の遺産額とは、プラスの財産からマイナスの財産や非課税財産を差し引いたものです。
プラスの財産
預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金など
マイナスの財産
借入金、未払金、葬式費用など
非課税財産
墓地・仏具など、一定の生命保険金・死亡退職金(500万円 × 法定相続人の数まで)
さらに注意点として、相続開始前3年(令和6年以降の贈与は7年)以内に被相続人から受けた贈与財産も、原則として相続財産に加算して計算する必要があります(暦年課税の場合)。
【モデルケース計算①】
プラスの財産が1億円で、マイナスの財産や非課税財産がないと仮定します。
正味の遺産額:1億円
② 基礎控除額の計算
次に、先ほど説明した基礎控除額を差し引きます。
【モデルケース計算②】
相続人は配偶者と子2人なので、法定相続人は3人です。
課税遺産総額:1億円 – 4,800万円 = 5,200万円
この5,200万円が、相続税を計算する上での基礎となる金額です。
3-2. ステップ2:相続税率と総額の計算
次に、ステップ1で算出した課税遺産総額を、いったん法定相続分で分割したと仮定して、各人の税額を計算し、それらを合計して「相続税の総額」を算出します。
相続税の速算表
計算には、国税庁が定める以下の速算表を用います。取得金額に応じて税率と控除額が段階的に設定されています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
| 出典: 国税庁 No.4155 相続税の税率 | ||
【モデルケース計算③】
課税遺産総額5,200万円を法定相続分で分けます。
子A:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
子B:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
速算表に当てはめて各人の仮の税額を計算します。
子A:1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
子B:1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
全員の税額を合計します。
相続税の総額:340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
3-3. ステップ3:各相続人への按分と控除・特例の適用
最後に、ステップ2で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に割り振り(按分)、そこから各人が適用できる税額控除を差し引いて、最終的な納税額を確定します。
【モデルケース計算④】
仮に、実際の遺産分割も法定相続分通り(配偶者1/2、子1/4ずつ)だったとします。
相続税の総額630万円を按分します。
子Aの負担額:630万円 × 1/4 = 157.5万円
子Bの負担額:630万円 × 1/4 = 157.5万円
各人の税額控除を適用します。
「配偶者の税額軽減」により、納税額は0円になります。
子A、子B
他に適用できる税額控除がなければ、納税額はそれぞれ157.5万円となります。
このように、早見表の金額(このケースでは約160万円)と、実際の納税額の合計(0 + 157.5 + 157.5 = 315万円)は、計算の仮定が異なるため一致しません。
しかし、早見表が税負担の規模感を掴む上で有効であることがお分かりいただけると思います。
4. 相続税の節税特例:小規模宅地・配偶者控除など
相続税には、納税者の負担を軽減するための様々な特例制度があります。
これらを活用できるかどうかで、納税額が数百万円、場合によっては数千万円単位で変わることもあります。
ここでは特に影響の大きい2つの特例を紹介します。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地や、事業をしていた土地を相続した場合、その土地の評価額を最大80%減額できるという節税にあたり非常に強力な効果がある制度です(租税特別措置法第69条の4)。
対象となる宅地:
特定居住用宅地等
被相続人が住んでいた自宅の敷地(上限面積330㎡)
減額割合80%
特定事業用宅地等
被相続人が事業を営んでいた土地(上限面積400㎡)
減額割合80%
貸付事業用宅地等
被相続人が不動産貸付をしていた土地(上限面積200㎡)
減額割合50%
例えば、評価額が5,000万円の自宅敷地を相続した場合、この特例を適用できれば評価額が1,000万円(80%減)となり、課税遺産総額を大幅に圧縮できます。
ただし、誰が相続するか(同居していた親族か、別居の親族かなど)によって適用要件が細かく定められており、非常に複雑です。
ご自宅を相続する可能性がある場合は、必ず専門家である税理士、弁護士に相談することをおすすめします。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
先ほどの計算例でも登場した、配偶者のための制度です(相続税法第19条の2)。
配偶者が取得した遺産が以下のいずれか多い金額までであれば、相続税はかかりません。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
この制度のおかげで、配偶者が多くの財産を相続しても、相続税の負担はゼロか、あるいは大幅に軽減されることがほとんどです。
ただし、この制度を適用するためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要がある点に注意が必要です。
納税額がゼロになるからといって、何もしなくて良いわけではありません。
また、安易にこの制度を使って配偶者に財産を集中させると、次の「二次相続」で子どもたちの負担が重くなる可能性があるため、長期的な視点での検討が重要です。
5. 早見表で見落としがちな注意点:二次相続や2割加算など
早見表だけを見ていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
5-1. トータルの税負担を増やす「二次相続」
二次相続とは、一次相続(例:父の死亡)で財産を受け継いだ配偶者が亡くなったときに起こる二度目の相続(例:母の死亡)を指します。
一次相続では、配偶者の税額軽減があるため、多くの財産を配偶者に相続させることで目先の税負担をゼロにすることも可能です。
しかし、その結果、二次相続の際には被相続人(母)の遺産額が大きくなるうえ、配偶者がいないため配偶者の税額軽減も使えません。
さらに、法定相続人の数も1人減るため、基礎控除額も少なくなります。
結果として、一次相続と二次相続のトータルの納税額で考えると、一次相続で配偶者が財産をもらいすぎたことが裏目に出て、かえって高額になってしまうケースがあります。
遺産分割を考える際は、二次相続までシミュレーションし、家族全体の税負担が最適になるようなバランスを考えることが大切です。
5-2. 税額が割増になる「相続税額の2割加算」
相続によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者、一親等の血族(子や親)以外である場合、その人の相続税額が2割増しになる制度です(相続税法第18条)。
対象となる主な人
- 兄弟姉妹、甥、姪
- 孫(代襲相続人でない場合)
- 内縁の妻や友人など、第三者
例えば、兄弟姉妹が相続人になる場合、算出された相続税額が100万円であれば、実際に納める額は120万円となります。
遺言によって孫やお世話になった第三者に財産を残したいと考えている場合は、この2割加算も考慮した上で納税資金の準備などを検討する必要があります。
5-3. 相続開始前の贈与財産にも注意
「相続税対策として生前贈与が有効」と聞いたことがあるかもしれません。
しかし、亡くなる直前の贈与は、相続税の課税対象に加算される(持ち戻される)ルールがあります。
暦年課税
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
この期間は、令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降の贈与から段階的に7年に延長されます。
相続時精算課税
2,500万円まで贈与税が非課税になる制度ですが、この制度を使って贈与した財産は、贈与した時期にかかわらず全て相続財産に加算されます。
これらのルールを知らずに駆け込みで贈与をおこなっても、節税効果が得られない可能性があります。
節税対策のために生前贈与を検討する場合は、最新の税制、節税方法について理解している税理士、弁護士への相談が不可欠です。
5-4. 相続税の申告と納税には期限がある
相続税の申告と納税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。
この期限は、遺産分割協議が長引いているなどの事情があっても延長されることは原則ありません。
期限内に申告・納税ができない場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまいます。
相続手続きは、財産の調査・評価、相続人の確定、遺産分割協議など、やるべきことが多く、10か月という期間は決して長くありません。
相続が発生したら、できるだけ早く手続きに着手することが重要です。
6. まとめ
相続税の早見表は、ご自身の相続にかかる税金の規模感を把握し、対策を考えるための非常に有効な出発点です。
しかし、この記事で解説してきた通り、早見表の数字はあくまでひとつの目安に過ぎません。
正確な課税価格を算出するには、不動産や非上場株式などの専門的な財産評価が必要ですし、適用できる特例を漏れなく活用するには、複雑な要件をクリアしなければなりません。
特に、小規模宅地等の特例などの節税に有効な情報は、専門家の知識と経験が不可欠な領域です。
相続税の申告には10か月という期限があります。
漠然とした不安を抱え続けるのではなく、まずは相続に詳しい税理士や弁護士といった専門家に相談し、ご自身の状況を正確に把握することをおすすめします。
たちばな総合法律事務所には、元国税審判官などの経歴を持つ税理士であり弁護士が在籍しています。
相続トラブルのある相続税申告を特に強みにしています。
当事務所では、相続に関する法律相談は初回無料です。
無料相談では、あなたの家族にとって最適な遺産分割案や節税対策を提案し、円満な相続を実現するための具体的なアドバイスをおこなっています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
無料相談は電話(10分)でもおこなっておりますが、相続税額の試算には事情をお伺いし、資料を拝見させていただく必要があります。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説






















































