大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
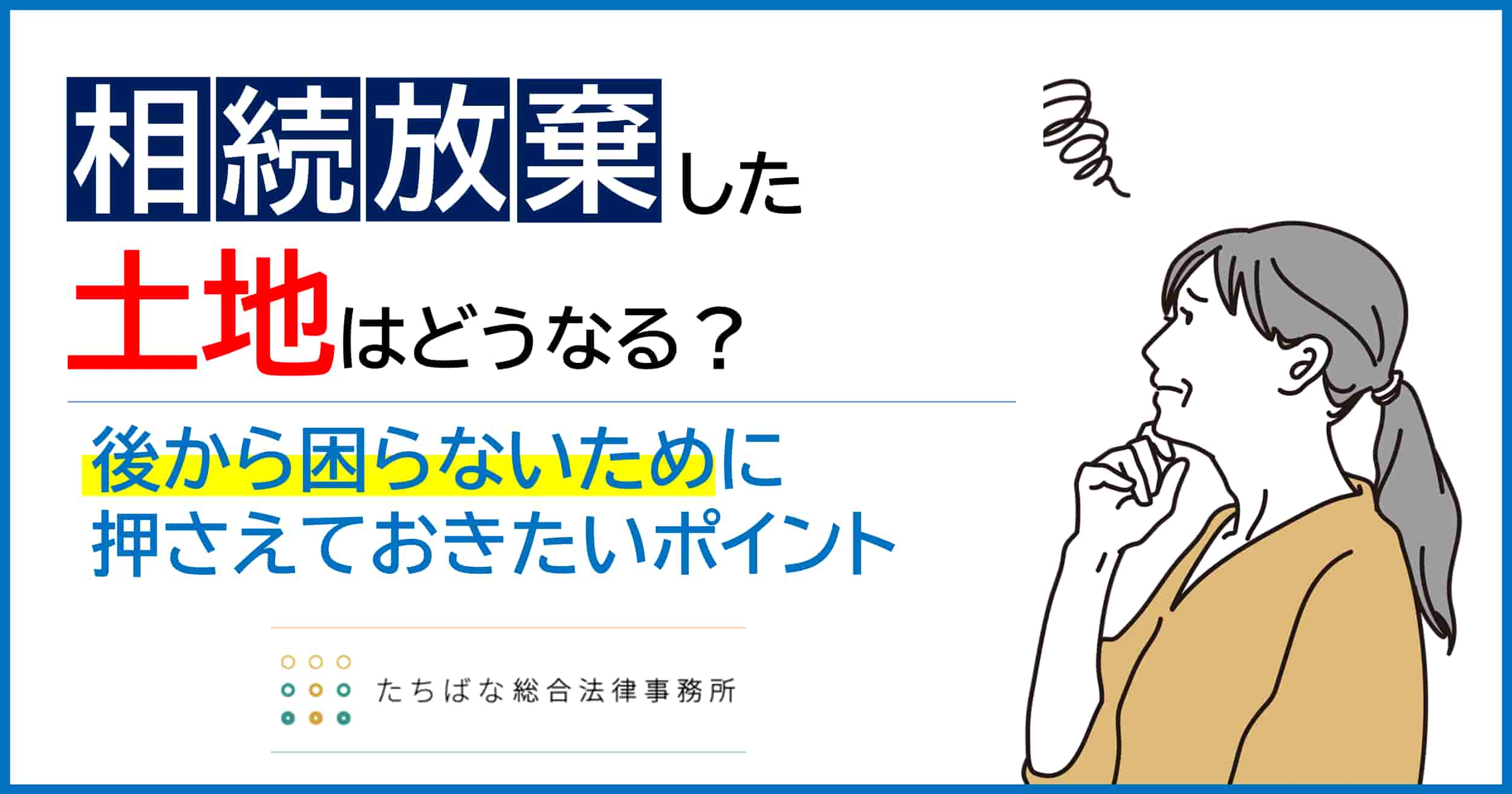
相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
親族が亡くなり相続が発生した際、相続放棄した不要な土地は、最終的に他の相続人、または「相続財産清算人」による処分を経て国庫に帰属します。
しかし、相続放棄は「土地だけ」を対象にすることはできず、預貯金などのプラスの財産もすべて手放すことになります。
さらに、放棄後も土地の「管理義務」が残り、仕組みを正しく理解していないと、思わぬ損害賠償責任を負うリスクがあります。
この記事では、弁護士が以下の点を詳しく解説します。
1. 相続放棄とは?土地だけを放棄することはできるのか
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も、すべてを一切引き継がないための法的手続きです(民法第938条)。
そのため、「土地だけ」を選んで相続放棄することはできません。
相続放棄をするには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法第915条第1項)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(申立て)する必要があります。
この手続きでマイナスの財産リスクを避けられます。
しかし、放棄後にも維持・管理責任が残るケースがあるため、慎重な検討が必要です。
1-1. 相続放棄の基本的な仕組みとメリット・デメリット
相続放棄は、家庭裁判所に必要書類(戸籍謄本や申述書など)を提出し、それが受理されると成立します。
認められると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。
参照 相続放棄のメリット・デメリット比較
メリット
- 負債を引き継がなくてよい
被相続人に多額の借金や連帯保証債務があっても、返済義務を負いません。 - 管理負担の回避
不要な土地や空き家の固定資産税の納税義務、管理費用(草刈り、修繕など)の負担を免れます。 - 相続トラブルからの離脱
他の相続人との遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続関係の争いから離れられます。
デメリット
- プラスの財産も一切相続できない
不要な土地だけでなく、預貯金、株式、自動車、価値のある家財など、すべてのプラスの財産を相続する権利も失います。 - 原則として撤回(取り消し)ができない
一度相続放棄が受理されると、後から「やはり財産が欲しくなった」と思っても、原則として撤回はできません(民法第919条)。
1-2.相続放棄ができなくなるケース(法定単純承認)
以下の行為をすると、相続財産をすべて引き継ぐ意思がある(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなります(法定単純承認、民法第921条)。
相続財産の「処分」
故人の預貯金を引き出して自分のために使う、土地や建物を売却する、株式を現金化するなど。
相続財産の「隠匿・消費」
故人の高価な財産を隠したり、勝手に使ったりする。
熟慮期間(3か月)の経過
期限内に家庭裁判所へ申述しなかった場合。
例えば、「故人の預金から自身の借金を返済した」「故人の車を売却してしまった」「形見分けのつもりで高価な美術品を持ち帰ったが、それが財産処分とみなされた」などが単純承認に当たる場合があります。
条文(民法921条)だけでは、「どこまでの行為がセーフか」分かりにくいです。
「故人の葬儀費用を故人の預金から支払う」など、例外的に許容される範囲もあるため、「うっかり放棄できなくなる」という不安がある場合は、まずは弁護士に相談してください。
1-3. 「遺産分割協議」で土地を相続しないこととの違い
特定の財産(例:不要な土地)だけを選んで相続放棄することはできません。
これは、相続放棄が「遺産全体」を対象とする制度だからです。
複数の相続人がおり、単に「土地だけを相続したくない」場合、「遺産分割協議」で相続しない選択も可能です。
参照 相続放棄と遺産分割協議の比較
相続放棄
- 家庭裁判所の手続き。
- 負債(借金)も含めて一切の権利義務を放棄する。
遺産分割協議
- 相続人全員による話し合い。
- 特定の財産(例:土地)を相続しないと希望すること、合意することは可能です。
- ただし、負債(借金)がある場合、その返済義務は(債権者との関係では)残ります。
1-4. 「限定承認」という選択肢との違い
「負債がどれだけあるか不明だが、プラスの財産もあるかもしれない」という場合、選択肢は「相続放棄(すべて失う)」「単純承認(すべて引き継ぐ)」、そして「限定承認」(民法第922条)の3つです。
1-4-1.限定承認とは?
相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐという制度です。
例えば、調査の結果、プラス財産が500万円、負債が800万円だった場合、500万円分だけ返済義務を負い、残りの300万円は支払う必要がありません。
もしプラス財産が800万円、負債が500万円なら、負債を返済した上で残った300万円を取得できます。
参照 限定承認の注意点
- 相続人全員で共同して申述する必要があります(一人でも反対がいれば不可)。
- 相続放棄と同じく、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所への申述が必要です。
- 手続きが非常に複雑で時間と費用がかかります(財産目録の作成、公告、清算手続きなど)。
限定承認は、手続きが非常に煩雑なため、実務上利用されるケースは相続放棄に比べて非常に少ないです。
2. 相続放棄した土地はどうなる?放棄後の流れと管理義務
相続放棄された土地は、まず同順位の他の相続人が、次に次順位の相続人が管理を引き継ぎます。
相続人全員が放棄した場合は「相続財産清算人」が管理します。
ただし、手続きが完了してもすぐに責任から解放されるわけではなく、特に土地の場合、放棄した人にも一定の管理義務が残る場合がある点に、注意が必要です。
2-1. 相続人が複数いる場合:誰がその土地を引き継ぐのか
相続放棄をすると、その人の相続権は次順位の相続人に移ります。
法定相続人には以下の順位が定められています。
法定相続順位
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第一順位 | 子(子が既に死亡している場合は孫) |
| 第二順位 | 親(父母。既に死亡している場合は祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(既に死亡している場合はその子(甥・姪)) |
(※被相続人の配偶者は、上記の順位とは別枠で、常に相続人となります)
例えば、被相続人に妻と長男、長女、そして被相続人の弟がいたケースで解説します。
1.妻、長男、長女(第一順位)が全員相続放棄した場合
2.相続権は第二順位(被相続人の親)に移ります。
3.もし親も既に亡くなっている、あるいは親も相続放棄した場合
4.相続権は第三順位(被相続人の弟)に移ります。
このように、相続権は次々と移転していきます。
もし次順位の親族(例:叔父や兄弟)に迷惑をかけたくない場合は、相続放棄をした旨を速やかに連絡し、彼らも3か月の熟慮期間内(通常は、自身が相続人になったことを知った時から3か月)に相続放棄を検討できるように配慮する必要があります。
2-2. 相続人全員が放棄したら?相続財産清算人の仕組み
配偶者や子、親、兄弟姉妹といった相続人全員が相続放棄をした場合、その相続財産(土地を含む)は「相続財産法人」(民法第951条)となり、法的に法人として扱われます。
しかし、土地が自動的に国のものになるわけではなく、放置されたままになります。
利害関係人(例:被相続人にお金を貸していた債権者、特定遺贈を受けた人など)や検察官は、家庭裁判所に対し「相続財産清算人」(※2023年4月の民法改正以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)の選任を申し立てることが可能です(民法第952条)。
2-2-1.相続財産清算人の役割
選任された相続財産清算人(通常は弁護士などの専門家が選ばれます)は、法人化された相続財産を管理・清算する役割を担います。
この手続きを経て、土地は初めて正式に国のものとなります。
2-2-2.清算人選任のハードル(予納金)
相続財産清算人の選任を申し立てるには、申立人が予納金(清算人の報酬や管理費用に充てるためのお金)を家庭裁判所に納付する必要があります。
この予納金は、財産の状況によりますが、数十万円(20万円~100万円程度)が一般的です。
3. 相続放棄しても残る管理義務とは?リスクと対処法
相続放棄を検討する上で、最も注意すべき点がこの「管理義務」です。
2023年4月1日の民法改正(施行)により、相続放棄者の管理義務に関する規定が明確化されました。
簡単に言えば、「相続放棄をしたときに、その土地を事実上管理・占有していた人は、次の管理者に引き渡すまで、きちんと管理し続けなさい」ということです。
例えば、被相続人と同居していた相続人が、実家(建物と土地)の相続を放棄した場合や、遠方でも定期的に土地の草刈りなどを行っていた場合、この「占有」に該当する可能性が高いです。
3-1. 放棄後に課される管理責任はいつまで続くのか
この管理責任は、「相続人(次順位の相続人)又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」続きます。
具体的には、以下のどちらかが実現するまで管理義務から解放されません。
管理義務が終了する時期
- 次順位の相続人(親や兄弟)が相続を承認し、管理を引き継いでくれる
- 相続人全員が放棄し、利害関係人(または自分)が申立てを行い、相続財産清算人が選任され、その清算人に管理を引き渡す
相続財産清算人の選任には高額な予納金が必要なため、誰も申立てをしなければ、理論上、管理義務が半永久的に続いてしまうリスクがあります。
放置すると、不法投棄や不審者の侵入、雑草の繁茂、害獣の発生などを招き、近隣住民とのトラブルや、次に説明するペナルティのリスクを高めます。
3-2. 管理義務を怠った場合のペナルティやトラブル
管理義務を怠り、土地の荒廃によって第三者に損害を与えた場合、主に以下の責任を問われるリスクがあります。
管理義務を放棄した場合のリスク
損害賠償責任(民法第709条)
例えば、管理不全が原因で土地のブロック塀が倒壊し、隣家の車や通行人に損害を与えた場合、相続放棄をしていたとしても、管理義務違反(占有者としての責任)を問われ、損害賠償を請求される恐れがあります。
行政からの指導・過料
「空家等対策の推進に関する特別措置法」などに基づき、倒壊の恐れがある危険な状態を放置していると、市町村から修繕や撤去の指導・勧告を受け、従わない場合は過料(罰金)が科される場合もあります。
相続放棄は「財産の取得」を放棄する手続きであり、「管理の責任」まで自動的に免除するものではありません。
3-3. 相続放棄すべきかどうかの判断基準
相続放棄はメリットもありますが、重大なデメリットやリスク(特に管理義務)も伴います。
参照 相続放棄を検討すべきケース
負債 > プラス財産
故人の借金が、預貯金や不動産などのプラス財産を明らかに上回っている。
土地の負担が著しく重い
- 資産価値がゼロ(またはマイナス)で、売却の見込みが全くない。
- 土地が遠方すぎる/管理が不可能
物理的に管理(草刈り、見回り)が不可能で、将来的な管理義務のリスクを負えない。
相続トラブルに関わりたくない
他の相続人との関係が悪く、遺産分割協議に関わること自体を避けたい。
参照 相続放棄を慎重に検討すべきケース(他の選択肢も視野に)
プラス財産 > 負債
負債はあるが、預貯金や株式などで相殺できる。
→ 単純承認などを検討
土地以外の財産は欲しい
土地は不要だが、預貯金や自宅は相続したい。
→相続放棄は不可。遺産分割協議や、国庫帰属制度、売却を検討
負債額が不明
財産調査が完了しておらず、負債がどれだけあるか分からない
→「相続放棄の期間伸長」の申立てなどを検討
判断に迷う場合は、3か月の期限が経過する前に、必ず弁護士などの専門家に相談し、財産調査とリスクの評価についてアドバイスを受けましょう。
また、相続放棄手続きの準備にも時間はかかるため、余裕をもって早めに相談してください。
4. 相続放棄の手続きと期限を知ろう:3ヵ月ルールのポイント
相続放棄は、法律で定められた厳格な手続きと期限(3か月ルール)を守らなければなりません。
参考 相続放棄の期限(熟慮期間)
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法第915条第1項)です。
「知った時」の具体的な意味
- 「知った時」とは、通常「被相続人の死亡を知り、かつ、それによって自分が相続人になったことを知った時」を指します。
- 先順位の相続人(子など)が全員放棄したために相続人になった次順位の相続人(親や兄弟)は、「先順位の相続人が放棄したことを知った時」から3か月となります。
この期間内に相続財産の調査を行い、相続放棄、単純承認、限定承認のいずれかを選択します。
期限を過ぎると、原則として相続財産をすべて引き継ぐ「法定単純承認」(民法第921条第2号)をしたものとみなされます。
もし3か月以内に財産調査が終わらない、または決断ができない正当な理由がある場合は、家庭裁判所に「相続の熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できる場合があります。
なお、延長するかどうか、どれくらい延長するかは裁判所が判断します。
4-1. 家庭裁判所へ届け出る際に必要な書類と費用
相続放棄の申立て(申述)は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
参照 相続放棄の主な必要書類と費用
必要書類
申述する人(相続人)と被相続人との関係によって必要書類が異なります。
- 相続放棄の申述書
家庭裁判所の窓口やウェブサイトで取得できます。 - 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- (配偶者が相続放棄する場合)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (子が放棄する場合)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (直系尊属;父母、祖父母が放棄する場合)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
かかる費用(実費)
- 収入印紙
申述人1人につき 800円 - 連絡用の郵便切手代
数百円程度~
(裁判所により異なるため、事前に確認してください) - 戸籍謄本などの取得費用
1通数百円×必要通数
これらの書類を不備なく揃えるのは時間と手間がかかります。
特に戸籍謄本は、本籍地が遠方だと郵送で取り寄せをしていると、3か月の期限はあっという間に過ぎてしまいます。
手続き自体は自分でも可能ですが、書類の収集が難しい場合や期限が迫っている場合は、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
4-2. 過去の相続(先代名義)の土地も放棄できる?手続き上の注意点
「土地の名義が、亡くなった父ではなく、さらにその前の祖父(先代)のままだった」というケース(いわゆる数次相続)は非常に多く、手続きが複雑になります。
この場合、相続関係は以下のようになっています。
1.祖父が死亡した時点(一次相続)
父が土地を相続する権利を得た。
2.父が死亡した時点(二次相続)
子が「父の財産(一次相続で得た土地の権利含む)」を相続する。
もし子がこの土地の負担を免れたい場合、祖父の相続を放棄すれば、父の相続を放棄しなくとも祖父の所有土地を承継することはなくなります。
ただ、父の相続を先に実行すると祖父の相続を放棄できなくなります(最高裁判所昭和63年6月21日判決・判例タイムズ706号166頁)。
さらに、2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。過去の相続(先代名義)であっても、正当な理由なく登記を怠っていると、過料(10万円以下)が科される場合があります。
先代名義の土地の相続放棄は、法律的な判断が極めて難しいため、必ず相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談してください。
5. 相続土地国庫帰属制度とは?国に引き取ってもらうための要件
「相続放棄をすると預貯金まで失うのは困る。でも、不要な土地だけを手放したい」
こうしたニーズに対応できる、「相続土地国庫帰属制度」(正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)が2023年4月27日に施行されました。
これは、相続や遺贈(遺言による贈与)によって取得した土地で、一定の要件を満たすものについて、国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)制度です。
参照 相続放棄との最大の違い
相続放棄
- 遺産「すべて」を放棄する。
- 3か月の期限あり。
国庫帰属制度
- 不要な土地「だけ」を手放せる。
- 相続発生後、期限の定めはない(ただし相続等で取得した土地に限る)。
6. 相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れと費用
この制度を利用するには、土地の所有者が法務局(管轄の法務局・地方法務局)に承認申請を行います。
6-1. 2023年施行の制度概要と対象となる土地の条件
この制度は、国が引き取れない「却下要件」や「不承認要件」が厳しく定められています。
なぜなら、あくまで「管理しやすい土地」だけを国が引き取るという趣旨の制度だからです(法第2条第3項、法第5条第1項)。
申請が受け付けられない土地(国庫帰属制度)
申請が「却下」される土地(申請自体ができない)
- 建物(家、物置、ビニールハウスなど)が建っている土地
- 担保権(抵当権など)や、使用・収益を目的とする権利(賃借権など)が設定されている土地
- 通路や墓地など、他人の利用が予定されている土地
- 所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地
承認が「不承認」となる(引き取れない)土地
- 崖や擁壁があり、管理に過大な費用・労力がかかる土地
- 土壌汚染や地下埋設物(ガラ、廃棄物など)がある土地
- 隣接地の所有者とトラブルを抱えている土地
- 管理・処分を妨げる動産(車両、農機具など)が放置されている土地
- 境界が不明確な土地
これらの要件をクリアするには、申請前に私費で建物を解体したり、境界を確定させたりする「事前整備」が必要となるケースが多く、ハードルは高いです。
6-2. 審査手数料や負担金など、実際にかかるコスト
制度の利用には以下のコストがかかります。
参照 相続土地国庫帰属制度でかかる費用
審査手数料
申請時に**1筆あたり14,000円**の収入印紙が必要です(不承認でも返金されません)。
事前整備費用
上記の建物の解体費用、境界確定のための測量費用、残置物の撤去費用など(**数十万~数百万円**)。
負担金
審査に通り、承認された場合に納付するお金。
負担金は、その土地の10年分の標準的な管理費用(草刈り、巡回など)と定められています。
金額は土地の種目(宅地、田、畑、山林など)や面積に応じて算定されますが、多くのケースで原則20万円(市街地の宅地など)からです。
管理が難しい山林や、面積が広い土地の場合は、100万円以上の負担金が算定される場合もあります。
7. 相続放棄以外の対策:売却や寄付・土地活用の選択肢
「相続放棄(全部失う)は嫌だ」
「国庫帰属制度(要件が厳しい)も無理そうだ」
この場合、相続財産として一度取得した上で、他の方法を模索します。
相続放棄とは異なり、他のプラス財産(預貯金など)は相続しつつ、不要な土地だけを処分する方法です。
7-1. 不要な土地は売却や寄付できる?利用方法・活用事例
特に地方の土地や山林といった資産価値が低い土地を手放すのは非常に困難です。
実務上、現実的な処分方法として以下が挙げられます。
相続放棄以外の土地の処分・活用方法
隣地所有者への譲渡
農地法上の制限がある土地(農地)は、農業委員会の許可が必要になるなど、売却や宅地への転用は容易ではありません。
隣地で農業を営む所有者の方に、農地の引き取りを交渉するのも一つの方法です。自分の土地が広がる(境界が整理される)メリットがあるため、無償(贈与)または安価な価格(売買)であれば引き受けてくれる可能性があります。
売却
買い手を見つけるのが困難です。不動産仲介業者に依頼しても、査定額がつかない、あるいは仲介自体を断られるケースも多いです。
近年は、こうした土地を専門に扱う不動産会社や「空き家バンク」と呼ばれる仕組みもあります。
寄付
自治体(市町村)やNPO法人などに寄付を打診する方法もありますが、現実にはほとんどのケースで断られます。
自治体も管理コストや将来的なリスクを負いたくないのが実情です。よほど公共利用の価値が高い土地でない限り、受け取ってはくれません。
活用
収益化のため、太陽光発電、駐車場、資材置き場などへの転用も考えられます。
しかし、初期投資や立地条件、法律上の用途制限などが厳しく、実現が困難な場合も多いです。
8. まとめ:相続放棄した土地で後悔しないために
固定資産税や管理コストの負担から逃れたい一心で安易に相続放棄を選ぶと、「預貯金まで失った」「管理義務のリスクが残った」などと後悔しかねません。
本記事で解説した選択肢を整理します。
相続に関する主な選択肢と特徴
相続放棄
3か月の期限あり。
土地も負債も手放せるが、預貯金などのプラス財産もすべて失う。
放棄しても管理義務が残るリスクが最大の問題。
限定承認
3か月の期限あり。
手続きが非常に煩雑だが、プラス財産の範囲で負債を返済し、残れば取得できる可能性。
相続(単純承認)した上で…
-
相続土地国庫帰属制度
期限なし(相続した土地)。土地だけ手放せるが、要件が非常に厳しく、高額な負担金(最低20万円~)が必要。
-
売却・寄付
買い手や引き取り手を見つけるのが極めて困難。
-
隣地所有者への交渉が唯一の現実的な道である場合も。
どの手段を取るか適切に判断するには、相続財産の調査、相続放棄の期限、管理義務のリスク、国庫帰属制度の要件などを検討する必要があり、高度な法的知識と実務的な経験が求められます。
「どうすればいいか分からない」と悩んだら、熟慮期間(3か月)が過ぎる前に、できるだけ早く相続問題に詳しいたちばな総合法律事務所にご相談ください。
税理士実務をおこなう弁護士が、相続税申告、各種相続手続きまでをトータルサポートしています。
また、相続放棄、遺産相続問題の初回無料相談を実施中です。
弁護士が直接お話を伺い、問題解決のためのアドバイスを行います。
まずは、メール、電話、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説
- 2025.10.22
- 生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ






















































