大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
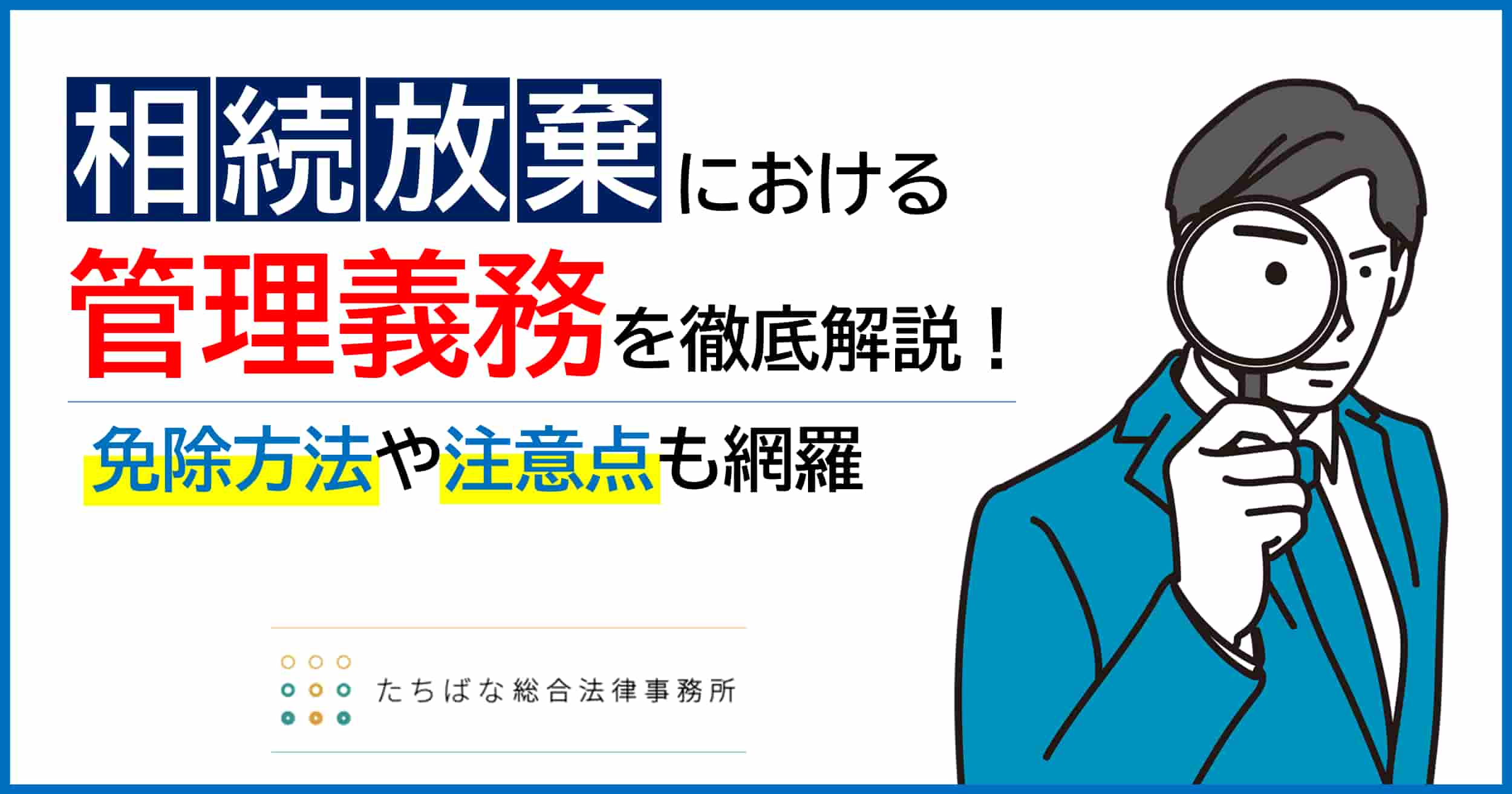
目次
【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人の管理義務(新法では「保存義務」)の発生要件が大きく変わり、「現に占有している」場合に限定されました。
「相続放棄をしたのに、まだ実家の管理をしなければならないの?」
「いつまでこの責任は続くの?費用は?」
本記事では改正民法に基づく新しいルール、義務が発生する具体的なケース、そして義務から解放されるための確実な手順を、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。
1.はじめに:相続放棄と管理義務の基礎知識
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、プラスの財産もマイナスの負債も一切引き継がないとする手続きです。
家庭裁判所に申述し受理されることで、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、「相続放棄をしても、ただちに全ての責任から解放」されないことがあります。
一定の条件に当てはまる場合、次の管理者が決まるまでの間、その財産を適切に管理(保存)し続ける義務が残ります。
これを「保存義務(法改正前は管理義務)」といいます。
特に、相続財産に空き家や山林などの不動産が含まれる場合、この義務を理解せず放置すると、損害賠償請求などの深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
2.相続放棄の管理義務(保存義務)はなぜ存在する?
相続放棄者に管理義務が残るのは、放置された財産によって近隣住民や社会全体が不利益を被ることを防ぐためです。
2-1. 相続放棄の定義と手続き概要
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、管轄の家庭裁判所へ申述する必要があります。
この手続きをおこなうことで借金の相続などを回避できますが、あくまで「相続人としての地位」を手放すものであり、「占有者としての責任」までが自動的に消滅するわけではありません。
2-2. 旧民法940条で定められていた管理義務
2023年3月以前の旧民法第940条では、相続放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められていました。
つまり、遠方に住むなど実際に財産を管理していない人にも責任が及ぶ可能性がありました。
2-3. 新民法940条で変わった点と「保存義務」への呼称変更
2023年4月1日施行の改正民法では、この問題が大きく見直されました。
まず、義務の名称が「管理義務」から「保存義務」へと変更されました。
保存義務では、財産の積極的な活用や改良といった高度な管理は求められません。
財産の現状を維持し、滅失や毀損を防ぐ程度の「保存行為」で足ります。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2-4. 「現に占有」している者が管理義務を負うとは?
改正により、保存義務を負うのは、相続放棄の時点で相続財産を「現に占有している」者に限定されました(民法第940条第1項)。
「現に占有」とは、その財産を事実上支配・管理している状態を指します。
例えば、不動産を現に占有しているかの判断については次のような事例が考えられます。
占有に当たる可能性が高い例:
- 被相続人と同居しており、相続発生後もそのままその家に住み続けている。
- 被相続人の建物の鍵を所持し定期的に訪問し管理している。
占有に当たらない可能性が高い例:
- 実家を出て長年別居しており、鍵も持っておらず、めったに帰省もしていなかった。
- 遠方の山林で、普段全く立ち入っていない。
つまり、これまで財産に関わっていなかった相続人であれば、相続放棄によって管理責任からも解放される可能性が高まりました。
ご自身の状況が「現に占有」にあたるかどうかは、専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けておくと安心です。
3.相続放棄後に管理義務が生じる主なケース
「現に占有している」状態とは、具体的にどのようなケースでしょうか。
相続放棄後も保存義務が続く代表的な状況を解説します。
3-1. 空き家や土地を放置する場合
被相続人が一人暮らしをしていた実家(空き家)の鍵を管理し、時折様子を見に行っていたようなケースでは、「現に占有」していたとみなされる可能性があります。
相続放棄後も、次の管理者が決まるまでは、建物が倒壊して通行人が怪我をしたり、ブロック塀が崩れたりしないよう、最低限の安全管理をおこなう必要があります。
3-2. マンションやアパートに住み続ける場合
被相続人名義のマンションに同居していた場合、まさに「現に占有」している状態です。
相続放棄後も住んでいる間は管理費・修繕積立金の支払い義務や、専有部分の適切な管理をおこなう保存義務を負います。
3-3. 山林や農地など管理コストがかかる不動産を所有している場合
山林や農地も、日常的に手入れをしていたり、柵を設置して他人の立ち入りを制限していたりする場合は「占有」とみなされる可能性があります。
土砂崩れの危険がある擁壁の補修や、危険な枯れ木の伐採など、近隣に危害を加えないための保存行為が求められることがあります。
4.保存義務を怠った場合のリスク
保存義務を無視し放置した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
4-1. 損害賠償責任や訴訟リスク
保存義務を怠ったこと(過失)により、第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
例えば、管理不全の空き家の屋根瓦が落下し、隣家の車を破損させたり、通行人に怪我を負わせたりしたケースです。
相続放棄をしていても、占有者としての責任(土地工作物責任など)は免れません。
4-2. 空き家倒壊や近隣トラブルに発展する可能性
物理的な損害だけでなく、ゴミの不法投棄、害虫・害獣の発生、不審火のリスクなど、近隣住民とのトラブルに発展するケースがあります。
行政から「特定空家」に指定されると、最終的に行政代執行による解体がおこなわれ、その費用を請求されるリスクもゼロではありません。
4-3. 相続放棄の効力が疑われる事態
管理義務を恐れるあまり、財産を勝手に処分(解体や売却、形見分けを超える持ち出し)してしまうと、「法定単純承認」(民法第921条)とみなされる危険があります。
単純承認とみなされると、相続放棄が認められなくなり、被相続人の借金を含む全ての遺産を相続しなければならなくなります。
保存行為の範囲を超えないよう、慎重な対応が必要です。
5.保存義務(管理義務)が免除されるための4つの方法
保存義務から完全に解放されるためには、主に以下の4つの方法があります。
5-1. 他の相続人に相続財産を引き渡す
最もスムーズな方法は、自分以外の相続人(次順位の相続人など)に財産を引き渡すことです。
例えば、子が全員相続放棄をした場合、次は直系尊属(父母・祖父母)、その次は兄弟姉妹が相続人となります。
これらの新たな相続人が相続を承認し、その人に財産を管理できる状態で引き渡せば、あなたの保存義務は消滅します。
5-2. 相続財産清算人(旧・相続財産管理人)を選任する
相続人全員が相続放棄をした場合、財産の引き渡し先がいなくなります。
この場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てます。
選任された清算人に財産を引き渡すことで、ようやく保存義務から解放されます。
ただし、裁判所に納める費用の負担(予納金)が発生するため、資金計画が必要です。
5-3. 保存義務のリスクを減らす対策
これは義務そのものを免れる方法ではありませんが、清算人が選任されるまでの間、遠方などで自ら管理できない場合は、民間の管理サービス(空き家管理サービスなど)を利用するのも一つの手段です。
費用はかかりますが、管理不全による損害賠償リスクを低減できます。
5-4. 保存義務の期間を短縮するための迅速な対応
保存義務を長引かせないためには、相続放棄の申述を迅速におこなうことはもちろん、次順位の相続人への連絡(自分が放棄したことの通知)や、相続財産清算人選任の要否の判断を早めにおこなうことが重要です。
例えば建物であれば、放置する期間が長いほど老朽化が進み、賠償リスクが高まります。
6.相続財産清算人の選任手順と必要書類
全員が相続放棄し、誰も管理する人がいなくなった財産を最終的に国庫に帰属させるためには、相続財産清算人の選任が不可欠です。
6-1. 家庭裁判所への申し立てに必要な書類と費用
必要書類とかかる費用の概要については次の通りです。
申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
主な必要書類
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 被相続人の子や代襲者で死亡している場合、その子や代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)など
- 被相続人の直系尊属(祖父母や曽祖父母など)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)など
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本など
- 代襲者としてのおいめいで死亡している人がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など
- 財産管理人の候補者の住民票(または戸籍附票)
- 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
費用
- 収入印紙(800円分)と連絡用郵便切手
- 予納金(官報公告料含む): これが最大の負担です。財産の内容にもよりますが、管理費用として数十万円〜100万円程度の現金をあらかじめ裁判所に納めるよう求められるケースが一般的です。
6-2. 相続財産清算人が行う主な業務内容
相続財産清算人は、財産の調査、管理をおこないながら、債権者への支払い(弁済)などを進めます。
最終的に残った財産は、国庫に帰属させる手続きを取ります。
清算人が財産を引き継いだ時点で、相続放棄者の保存義務は終了します。
なお、親族や相続放棄者を相続財産清算人の候補者として立てることもできます。
ただし、その手続きは複雑であるため、候補者を採用せず、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士を選任する場合が多いです。
7.保存義務(管理義務)に関するよくある質問(Q&A)
保存義務に関してよせられる質問についてご紹介します。
7-1. Q1:相続人全員が相続放棄した場合、管理義務は誰が負うの?
A. 「現に占有」していた相続放棄者が負い続けます。
全員が放棄しても、財産が自動的に国のものになるわけではありません。
最後に財産を占有していた人が、相続財産清算人に引き渡すまで義務を負います。
誰も占有していなかった場合は、特段の管理者がいない状態となりますが、検察官や利害関係者(被相続人の債権者や自治体など)が清算人を申し立てることもあります。
7-2. Q2:管理義務があっても固定資産税は支払わないといけない?
A. 原則として、相続放棄をすれば固定資産税の納税義務はなくなります。
ただし、1月1日時点の所有者に課税されるため、放棄の時期によっては納税通知書が届くことがあります。
その場合は、役所の税務課に「相続放棄申述受理証明書」のコピーを提出し、納税義務がないことを説明してください。
なお、保存行為として必要な費用(電気代の基本料金や最低限の修繕費など)は、一時的に立て替える必要があるかもしれません。
7-3. Q3:相続放棄後に発生する管理費用はどこから捻出するの?
A. 原則は相続財産から支払うことができますが、注意が必要です。
保存行為に必要な費用は、相続財産(被相続人の預貯金など)から支出することが認められています。
しかし、自分の判断で勝手に使うと「単純承認」とみなされる行為をおこなってしまうリスクがあるため、事前に家庭裁判所や弁護士に確認してから支出するのが安全です。
7-4. Q4:未成年者や認知症の人が相続人の場合、管理義務はどうなる?
A. 事実上、法定代理人(親権者や成年後見人)が代わって義務を負います。
本人が適切な管理をおこなえないため、代理人がその責任を負うことになります。
これらの人が相続放棄をする場合は、特別代理人の選任や成年後見申立など複雑な手続きが必要になることもあるため、専門家にご相談ください。
8.相続放棄の管理義務が生じやすい財産別の注意点
8-1. 空き家や古屋の管理で注意すべき点
「特定空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が急増する可能性があります(相続放棄が完了するまでの間)。
また、火災保険の契約者が死亡している場合、万が一の火災時に補償が受けられないリスクもあるため、保険の継続手続き等も確認が必要です。
なお、火災保険の契約者の名義変更は管理行為に含まれないため、火災保険の必要がある場合には、改めて火災保険契約を締結すると良いでしょう。
8-2. マンションや区分所有物件の管理義務
管理費等の滞納が続くと、管理組合から訴訟を起こされる可能性があります。
相続放棄をしたことを管理組合に速やかに伝え、今後の対応を協議しておく誠実な対応が、トラブル回避につながります。
8-3. 山林・農地など広大な土地を放置するリスク
境界が不明確なケースが多く、隣地所有者とのトラブルになりやすいです。
また、不法投棄された廃棄物の処理責任を問われるリスクもあります。
自分で被相続人名義の不動産の場所を特定できないような場合は、早急に専門家へ調査を依頼することをおすすめします。
9.まとめ
ここまで相続放棄後の管理義務について解説しました。
相続放棄義の保存義務の問題は、法的な判断や手続きが必要となるため、早めに専門家に相談しておくと安心です。
特に弁護士は、士業の中でも唯一、相続トラブル(紛争)の解決を代理することができます。司法書士は、簡易裁判所の代理権を持つこともできますが、その範囲が限られることがあります。
法的な判断や手続きのトータルサポートをおこなえるのは弁護士だけです。
たちばな総合法律事務所では、相続放棄を含め相続問題解決のためのサポートをおこなっています。
また、初回無料相談にて遺産相続問題を解決するためのアドバイスを行っています。
無料相談では、弁護士があなたの事情や希望をお伺いしたうえで、① 解決策の提案、② 解決までの見通し、③ 個別の質問への回答をしています。
相続放棄について、少しでも不安や悩みをお持ちでしたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説
- 2025.10.22
- 生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ






















































