大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説
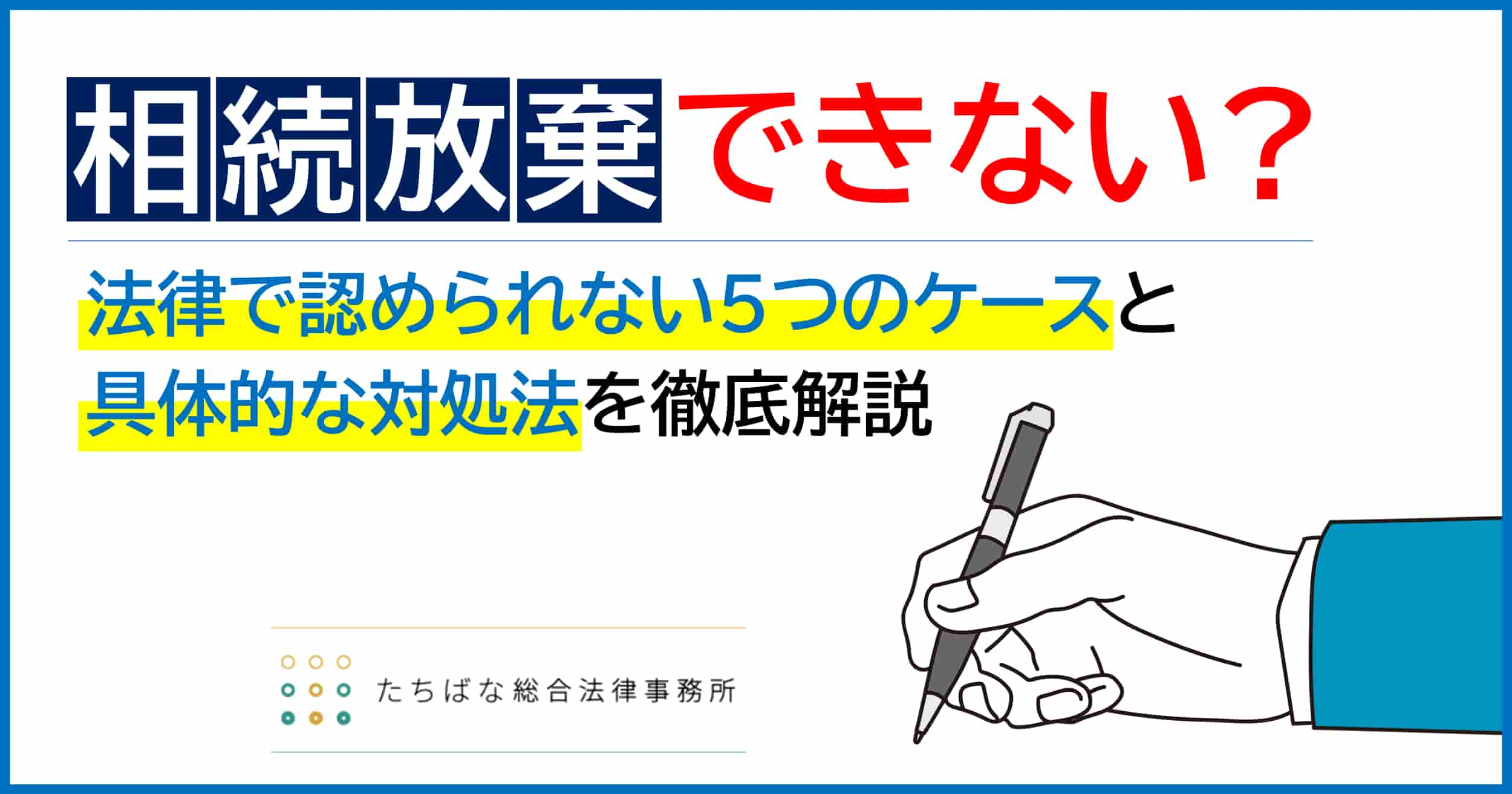
相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切受け継がないための法的な手続きです。
しかし、「手続きをすれば必ず認められる」というわけではありません。
特定の行為をしてしまったり、手続きの期限を過ぎてしまったりすると、相続放棄が認められず、思いがけず多額の借金を背負ってしまうリスクがあります。
特に「法定単純承認」という制度を知らずに遺産に手をつけてしまうと、後から放棄することは原則としてできなくなります。
この記事では、法律の専門家として、相続放棄が認められない代表的なケースを具体的な判例・法律の条文(根拠)や事例を交えながら徹底的に解説します。
また、万が一相続放棄が難しい時の具体的な対処法や、その場合に取るべき行動をお伝えします。
相続に関するトラブルを未然に防ぎ、迅速かつ円滑に問題解決の糸口を見つけたい方は、ぜひご一読ください。
1. まずは基本から|相続放棄とは?押さえておくべき3つのポイント
相続放棄の手続きや意味を理解しておくと、後々のトラブルや判断ミスを防ぐことができます。
1-1. 相続放棄の概要
相続放棄とは、被相続人の遺産(財産や権利、義務)を一切受け継がないという手続きです。
プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がずに済む点が大きなメリットです。
この手続きは、相続放棄の意思表示を家庭裁判所に対しておこないます(相続放棄申述申立)。
1-2. 手続きの期限(熟慮期間)
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」におこなう必要があります(民法第915条第1項)。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
いつから3ヶ月を数え始めるか(起算点)が非常に重要になりますので、注意が必要です。
例えば、疎遠な親族(被相続人)が亡くなり、滞納税金の支払いについて市役所などからの書面が届いた時に初めて1年以上前に被相続人が亡くなったことを知った時には、その通知を受け取った時点が起算点となります(被相続人の死亡日ではありません)。
1-3. 全部か無かの原則
相続放棄は、遺産の一部だけを選んで放棄することはできません。
「この土地だけ放棄して、預貯金は相続する」といった選択は認められず、すべての遺産を放棄するか、すべてを相続するかの二者択一となります。
なお、被相続人の死亡により受取人に指定されている生命保険金(死亡保険金)などは相続財産の対象とならないものもあります。
相続放棄をしても受け取り可能な財産もあります。
相続放棄するべきか判断に迷う場合や複雑な債務が絡む場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
2.相続放棄ができない・認められない5つの代表的ケース
家庭裁判所に相続放棄が認められないと、負債を含めて相続せざるを得ない可能性が高まります。
ここでは、代表的なケースを詳しく解説します。
2-1.法定単純承認が成立してしまった場合
法定単純承認とは、特定の行為をすることで、相続人が「単純承認(すべての遺産を無条件に相続すること)」をしたと法律上みなされる制度です(民法第921条)。
これが成立すると、相続放棄は原則として認められません。
具体的にどのような行為が「法定単純承認」にあたるのか?
法律(民法)で定められている「法定単純承認」に当たる具体的な行為は次の通りです。
① 相続財産の全部または一部を処分したとき(民法第921条第1号)
相続人が自分のために相続財産を使った(処分した)場合です。
「処分」とは、売却や譲渡だけでなく、財産の現状や性質を変える行為(建物の増改築、居宅を更地にするなど)も含まれます。
② 熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき(民法第921条第2号)
前述の「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」という熟慮期間内に家庭裁判所で手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したとみなされます。
多くの方が見落としがちなポイントとして、財産や借金の有無の調査に時間をかけすぎてしまい、気づいたら熟慮期間が過ぎていることが挙げられます。
財産調査が熟慮期間内に終わりそうもない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間内に同期間の延長(伸長)するための手続きをとるようにしましょう。
裁判所の判断で期限が伸びることがあります。
③ 相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、財産目録にわざと記載しなかったりしたとき(民法第921条第3号)
これは、相続放棄や限定承認をした後でも適用されます。
相続放棄をしたにもかかわらず、こっそり遺産を隠し持っていたり、勝手に使ってしまったりすると、その放棄は無効となり、単純承認が成立します。
悪意のある行為に対するペナルティと言えます。
「単純承認」とみなされる行為・みなされない行為の具体例
相続放棄を検討している方が最も迷うのが、「この行為はセーフか、アウトか」という判断です。
以下に具体例をまとめました。
| 行為の具体例 | 単純承認とみなされる可能性 | 解説 |
|---|---|---|
| 被相続人の預貯金の解約・払い戻し | 高い | 預金を解約し、自己の口座に移したり、生活費などに使ったりする行為は典型的な処分行為です。ただし、葬儀費用や、後述の保存行為などに充てるためした払い戻しは単純承認にあたらない可能性認があります。 |
| 被相続人の不動産を売却・賃貸・リフォームする | 高い | 不動産の売却は最も分かりやすい処分行為です。賃貸借契約を結んで家賃収入を得る行為や、資産価値を高めるリフォームも処分とみなされ、単純承認に当たる可能性が極めて高いです。 |
| 被相続人の株式や投資信託を売却する | 高い | 株式や投資信託を売却して現金化する行為も単純承認にあたります。 |
| 被相続人の自動車の名義変更・売却 | 高い | 自動車を自己の名義に変更したり、売却したりする処分行為は単純承認に当たります。 |
| 遺産分割協議に参加し、署名・捺印する | 高い | 遺産分割協議は、相続することを前提とした話し合いです。ご自身が遺産分割を受けることを内容とした協議書に署名・捺印すると、相続を承認したとみなされ、その後の相続放棄は原則認められません。 |
| 被相続人が受け取るはずだった給料や家賃収入を受け取る | 高い | これらは相続財産の一部です。相続人が受け取って自分のために消費すれば処分行為となり、単純承認に当たります。 |
| 被相続人の借金を、相続財産から返済する | 高い | 遺産である預貯金などから借金を返済する行為は、財産の処分と債務の承認の両方にあたり、単純承認とみなされる可能性があります。 |
| 経済的価値のある遺品(骨董品、貴金属など)を売却・処分する | 高い | 形見分けの範囲を超え、明らかに経済的価値のあるものを売却して利益を得る行為は処分とみなされ、単純承認に当たります。 |
| 被相続人の携帯電話の解約 | ケースバイケース | 単なる解約手続き自体は保存行為とみなされることが多いです。しかし、未払料金を遺産から支払ったり、端末を売却したりすると単純承認とみなされるリスクがあります。 |
| 被相続人の葬儀費用を遺産から支払う | 低い | 社会的儀礼として相当な範囲内の葬儀費用を遺産から支払うことは、判例上も認められる傾向にあります(大阪高等裁判所決定 平成14年7月3日)。ただし、あまりに豪華で不相当な葬儀は問題となる可能性があります。 |
| 被相続人の医療費や税金を遺産から支払う | 高い | 被相続人の未払いの医療費や入院費、税金(所得税、住民税、固定資産税など)は、相続債務にあたります。これを遺産から支払う行為は「相続財産の処分」とみなされ、法定単純承認に該当する可能性が高いです。 |
| 故人の住んでいた家の片付け(形見分けや遺品整理) | 低い(ただし注意が必要) | 経済的価値のない衣類や写真などを形見として分ける行為は、通常問題ありません。しかし、価値のあるものを勝手に処分・売却すると法定単純承認とみなされるリスクがあります。 |
| 被相続人の死亡保険金を受け取る | 原則として問題ない | 死亡保険金は、受取人として指定された人の固有の財産であり、相続財産ではありません。したがって、これを受け取っても単純承認にはなりません。ただし、保険金の受取人が「被相続人本人」と指定されている場合は相続財産となるため注意が必要です。 |
| 相続財産の保存行為 | 問題ない | 腐敗しやすい食品を廃棄したり、壊れそうな家屋を応急的に修繕したりする行為、倒木の危険や近隣に枝葉が伸びて迷惑をかけている場合の樹木の剪定や伐採、空き家の定期的な換気や通水などは、財産の価値を維持するための「保存行為」として認められます。 |
2-2. 熟慮期間(3ヶ月)を経過してしまった場合
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月が経過すると、単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります(民法第915条第1項、第921条第2号)。
しかし、例外的に3ヶ月経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。
最高裁判所の判例(最判昭59.4.27)では、次のように判断しています。
1.被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、
2.そのように信じたことに相当な理由がある場合
には、相続人が借金などマイナスの財産の存在を認識した時、または通常認識し得べき時から3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述が受理される可能性がある
と示しています。
この判例の最も重要なポイントは、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある場合」に、熟慮期間の起算点を相続財産の存在を認識した時点に繰り下げたことです。
ただ、当判例によって、熟慮期間を過ぎてからでも相続放棄が認められる可能性はありますが、あくまで例外的なケースです。
また、この例外が認められるには、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること」という要件を満たす必要があります。
単に「知らなかった」というだけでは不十分で、被相続人の生活状況、相続人との関係性、積極的な調査が困難であった事情など、具体的な状況が総合的に考慮されます。
2-3. 相続放棄の申述が「却下」された場合
相続放棄手続き上のミスや、相続放棄の申述人の意思確認ができない場合、家庭裁判所に提出した相続放棄の申述が「却下」されることがあります。
- 書類の不備や手続き上のミス
相続放棄申述書の必要事項の記載漏れ、添付すべき戸籍謄本などの必要書類の不足、収入印紙の貼り忘れなど。
- 家庭裁判所からの照会書に応じなかった
手続きの過程で、家庭裁判所から相続放棄の意思などを確認するための「照会書」が送られてくることがあります。
これは、相続放棄の申述(申し出)が受理されると、相続権を失うという強い効果が認められることになるため、本当に申述人の意思にもとづいておこなわれたものかを確認するためです。
照会に回答しなかったり、期限内に回答書を返送しなかったりすると、申述人の意思が確認できないとして却下される可能性があります。
- 虚偽の申述をした
申述内容に嘘があった場合、当然認められません。
- 申述人に放棄の意思がない
照会書への回答などから、本心では放棄を望んでいないと判断された場合。
一度却下されてしまうと、熟慮期間が残っていない限り、再度の申述は極めて困難です。
2-4.却下された場合の不服申立て(即時抗告)をしなかった場合
家庭裁判所の却下の決定に不服がある場合、その決定を知った日から2週間以内であれば、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申立てができます。
この手続きを行わずに2週間が経過すると、却下の決定が確定してしまいます。
2-5. 土地だけの相続放棄など「一部放棄」をしようとした場合
「借金は放棄したいが、実家は相続したい」といったように、財産を選り好みして相続することはできません。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する制度です。
一部の財産だけを放棄しようとする申述は認められません。
3. 要注意!相続放棄をしても「管理責任」が残るケース
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の管理責任に関するルールが明確化されました。
参照 改正民法 第940条第1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
簡単に言うと、「相続放棄をしても、その時に現に占有(管理)していた財産があるなら、次の管理者が決まるまでは、きちんと管理し続けなければならない」ということです。
特に問題となりやすいのが、空き家です。
相続放棄をしたからといって、誰も住んでいない実家を放置していると、建物が倒壊して隣家や通行人に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われるリスクがあります。
ただ、あなたが相続放棄をおこなう時に被相続人の当該空き家を物理的に占有・管理していなかったのであれば、基本的に民法第940条にもとづく空き家の保存義務は発生しません。
他方、被相続人の自宅に同居していた相続人であれば、その自宅を「現に占有している」と言えます。
この場合、管理責任から解放されるためには、他の相続人や、後述する「相続財産清算人」に財産を引き渡す必要があります。
4. 相続放棄ができない・認められない場合の5つの具体的対処法
「もう相続放棄は無理かもしれない…」と諦めるのはまだ早いです。
状況に応じて、いくつかの対処法が残されています。
なお、「2-4.却下された場合の不服申立てをしなかった場合」のように、相続放棄が認められなかった場合にする即時抗告以外に、事情に応じて次のような対処法があります。
4-1.債務整理の検討をする
被相続人の債権者(相続債権者)との間で、債務整理を検討するのも一つの方法です。
債務整理には、主に次の方法があります。
4-1.債務整理の検討をする
被相続人の債権者(相続債権者)との間で、債務整理を検討するのも一つの方法です。
債務整理には、主に次の方法があります。
- 任意整理
裁判所を利用しない負債整理の方法。
直接債権者と返済条件、返済額について柔軟な交渉をおこなうことができます。
一方で、債権者が交渉に応じるかは任意であり、交渉が決裂する可能性があります。
- 自己破産申立て
地方裁判所の負債整理手続きです。
税金や養育費などの非免責債権を除き、借金返済の免除を受けることができます。
但し、一定の所有財産を処分する必要があり、職業の資格制限を受ける場合もあるため注意が必要です。
- 個人再生手続き
地方裁判所の負債整理手続きです。
大幅に減額された借金を原則3年間(特別な事情があれば最長5年)で返済していきます。
住宅ローンのある自宅不動産を残すことができるのが大きなメリットです。
但し、返済計画(再生計画案)にもとづいて返済をするため、利用には安定した収入があることが必要です。
4-2. 他の相続人との遺産分割協議で調整する
相続人が複数いる場合、相続放棄ができなくても、遺産分割協議の話し合いによって実質的な負担を調整できる可能性があります。
例えば、「借金の返済をすべて引き受ける代わりに、不動産を単独で相続する」といったように、特定の相続人が債務を多く引き継ぐ代わりに、財産も多く取得するという合意をする方法です。
この合意は、あくまで相続人間の内部的な取り決めです。
債権者に対しては、この合意を主張できません。
債権者は、各相続人に対して、法定相続分の割合で返済を請求する権利を持っています。
もし債務を引き継ぐと約束した相続人が返済を怠れば、他の相続人も請求を受けるリスクが残ります。
4-3. 相続土地国庫帰属制度の活用を検討する
「負動産」と呼ばれるように、相続不動産が管理の手間、費用がかかり負担となるケースがあります。
どうしても手放したい「土地」があり、他の対処法が難しい場合、「相続土地国庫帰属制度」の利用も選択肢の一つです。
この手続きは、一定の要件を満たす「土地」を、国に引き取ってもらう制度です。
- メリット
不要な土地の管理責任や固定資産税の負担から解放されます。
- デメリット
- 要件が非常に厳しい
建物がない、担保権が設定されていない、境界が明確であるなど、多くの条件をクリアする必要があります。 - 負担金が必要
審査手数料のほか、承認された場合は10年分の土地管理費相当額(原則20万円~)を納付する必要があります。
4-4. 弁護士や司法書士などの専門家へすぐに相談する
相続放棄ができない状況において、法的に複雑な判断を要することがあります。
独力で進めようとすると、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。
熟慮期間の起算点を間違えていた、家庭裁判所が単純承認であるとされた行為も、実は適切に対応すれば相続放棄が認められる可能性もあります。
現状分析と最適な解決策の提案
専門家は、あなたの状況を法的な観点から正確に分析し、限定承認、遺産分割協議、その他の手続きなど、最も有利な解決策を提示してくれます。
複雑な手続きの代行
家庭裁判所への申立てや、相続債権者との交渉など、負担の大きい手続きを任せることができます。
精神的な安心感
法律のプロが味方についているというだけで、大きな安心感が得られます。
特に、熟慮期間の経過が迫っている場合や、すでに法定単純承認にあたる行為をしてしまったかもしれないと不安な場合は、一刻も早く相談することをお勧めします。
たちばな総合法律事務所では、相続放棄に関する初回相談を無料で受け付けています。
まずは気軽にご相談ください。
5. 相続放棄にまつわるQ&A
相続放棄をめぐっては、様々な疑問が生じます。
よく寄せられる質問について解説します。
Q1. 親の借金は相続放棄できないの?
A1. 相続放棄は可能です。
原則として、相続放棄をすれば親の借金を支払う義務はなくなります。
借金もマイナスの財産として相続放棄の対象となるためです。
ただし、本記事の「2. 相続放棄ができない・認められない5つの代表的ケース」で解説したように、法定単純承認が成立していたり、熟慮期間が過ぎていたりすると放棄できなくなりますので注意が必要です。
Q2. 被相続人が連帯保証人でした。その支払いも相続放棄できる?
A2. はい、できます。
連帯保証人としての地位も相続財産に含まれるため、相続放棄をすれば、その義務を引き継ぐ必要はありません。
ただし、これもQ1と同様に、相続放棄が法的に有効に成立することが前提となります。
Q3. 家財や遺品の整理をすると、本当に相続放棄できなくなる?
A3. 行為の内容によります。
重要なのは、その行為が「財産の処分」にあたるかどうかです。
セーフの可能性が高い行為
- 一般的な衣類や写真などの形見分け
- 明らかに経済的価値のない物の廃棄(ゴミの片付けなど)
- 故人が住んでいた賃貸物件の明け渡しに伴う、家財のやむを得ない搬出・処分(※事前に専門家に相談するのが望ましい)
アウト(単純承認)の可能性が高い行為
- 骨董品、貴金属、ブランド品、まだ使える家電など、少しでも経済的価値のあるものを売却したり、リサイクルショップに持ち込んだりする行為。
- 自動車を処分する行為。
判断に迷う場合は、価値のあるものには一切手を付けず、まず相続放棄の手続きを完了させるのが最も安全です。
Q4. 葬儀費用を遺産から支払うと相続放棄できない?
A4. 社会通念上、分相応の規模の葬儀費用を被相続人の遺産から支払うことは、法定単純承認にはあたらないとされるのが一般的です。
ただし、誰が見ても不相当に豪華な葬儀を行うと、財産の処分とみなされるリスクがあります。
可能であれば、喪主(相続人)自身の財産や、受け取った香典から支払う方がより安全です。
Q5. 熟慮期間の3ヶ月は、いつから数え始めますか?
A5. 民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時」からと定められています。
これは、単に「被相続人が死亡した日」とは限りません。
具体的には、以下の両方を知った時点を指します。
2.自分がその相続人になったという事実
例えば、長年音信不通だった叔父が亡くなり、他の相続人が全員相続放棄した結果、自分に相続権が回ってきた場合、その事実を(例えば家庭裁判所からの通知などで)知った時から3ヶ月を数え始めることになります。
Q6. 相続人全員が相続放棄したら、不動産や借金はどうなりますか?
A6. 最終的に、利害関係者の申立てにより「相続財産清算人」が選任されます。
清算人は、不動産などを売却してお金に換え、その中から借金の返済や未払いの税金の支払いなどをおこないます。
すべての清算が終わった後に財産が残っていれば、それは国庫に帰属します(国のものになります)。
参照 相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任申立て
相続人全員が相続放棄をした場合や、そもそも相続人がいない場合、利害関係者(債権者など)や検察官は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることができます(2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称変更)。
選任された相続財産清算人(通常は弁護士などの専門家)が、相続財産を調査・管理・換価し、債権者への支払いなどをおこないます。
選任を申し立てる際に、予納金(管理費用等に充てるためのお金)として数十万円~100万円程度を裁判所に納める必要があります。また、手続きが完了するまでに時間がかかります。
Q7.遺言で相続放棄を禁止されていた場合、相続放棄できますか?
A7.相続放棄は可能です。
遺言書に「長男には相続放棄を認めない」といった記載があったとしても、法的な効力はありません。 相続放棄は相続人固有の権利であり、被相続人の意思でこれを妨げることはできません。
したがって、このような遺言があっても問題なく相続放棄の手続きは可能です。
Q8.相続人自身が自己破産した場合、相続放棄できますか?
A8.相続人が自己破産の手続き中であっても、相続放棄をすること自体は可能です。
この場合、相続放棄をすべきか、破産管財人に伝え判断を仰ぐか、弁護士と慎重に協議する必要があります。
相続財産がプラスになる場合(借金よりも財産が多い場合)、その財産は破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられる可能性があります。
Q9.相続放棄は、共同相続人全員がしなければいけませんか?
A9.いえ、独自の判断で相続放棄をすることができます。
相続放棄をするのに、他の相続人の同意は必要ありません。
なお、相続放棄をした場合、その人は相続財産を一切承継しないため、相続税の申告義務は基本的にありません。
また、他の共同相続人において基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人数))を超える相続を受ける場合、相続税申告をおこないます。
その際、放棄した相続人も含めて法定相続人の人数に入れることができます。くわしくは税理士に相談すると良いでしょう。
6. まとめ|相続放棄できない状況でも道はある。まずは専門家に相談を
相続放棄は、期限や禁止行為が法律で厳格に定められている手続きです。
軽い気持ちで遺産に手をつけてしまうと、「知らなかった」では済まされない事態におちいる可能性があります。
本記事で解説したように、相続放棄が認められない代表的なケースは以下の通りです。
(遺産を処分・消費してしまったなど)
・熟慮期間(3ヶ月)を経過してしまった
・手続きに不備があった、または却下された
もし、ご自身の状況がこれらのケースに当てはまるかもしれないと不安に感じたら、決して一人で抱え込まないでください。
相続放棄が難しい場合でも、対応次第で認められる可能性があります。
どの方法が最適かは、個々の財産状況や家族関係によって大きく異なります。
最も重要なことは、できるだけ早い段階で、弁護士や司法書士といった相続問題の専門家に相談することです。
専門家は、あなたの状況を的確に判断し、法的なリスクを最小限に抑えながら、最善の解決策へと導いてくれます。
手遅れになる前に、まずは無料相談などを活用し、第一歩を踏み出しましょう。
たちばな総合法律事務所では、相続トラブルについての解決サポートをおこなっています。
相続トラブルは、弁護士が専門とする業務分野です。
弁護士に依頼することで、① 手続きの負担が軽減され、② 他の相続人との代理交渉を任せられるため、精神的な負担を大幅に軽くすることが可能です。
なお、相続問題について初回無料法律相談を実施中です。
弁護士が丁寧にご事情、相続関係などをお伺いし、① 解決方法のアドバイス、② 解決までの見立て、③ 個別の質問への回答など、ご不安・ご心配を少しでも解消できるように努めています。
電話、LINE、メールでご予約を受け付け中です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.22
- 生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ






















































