大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ
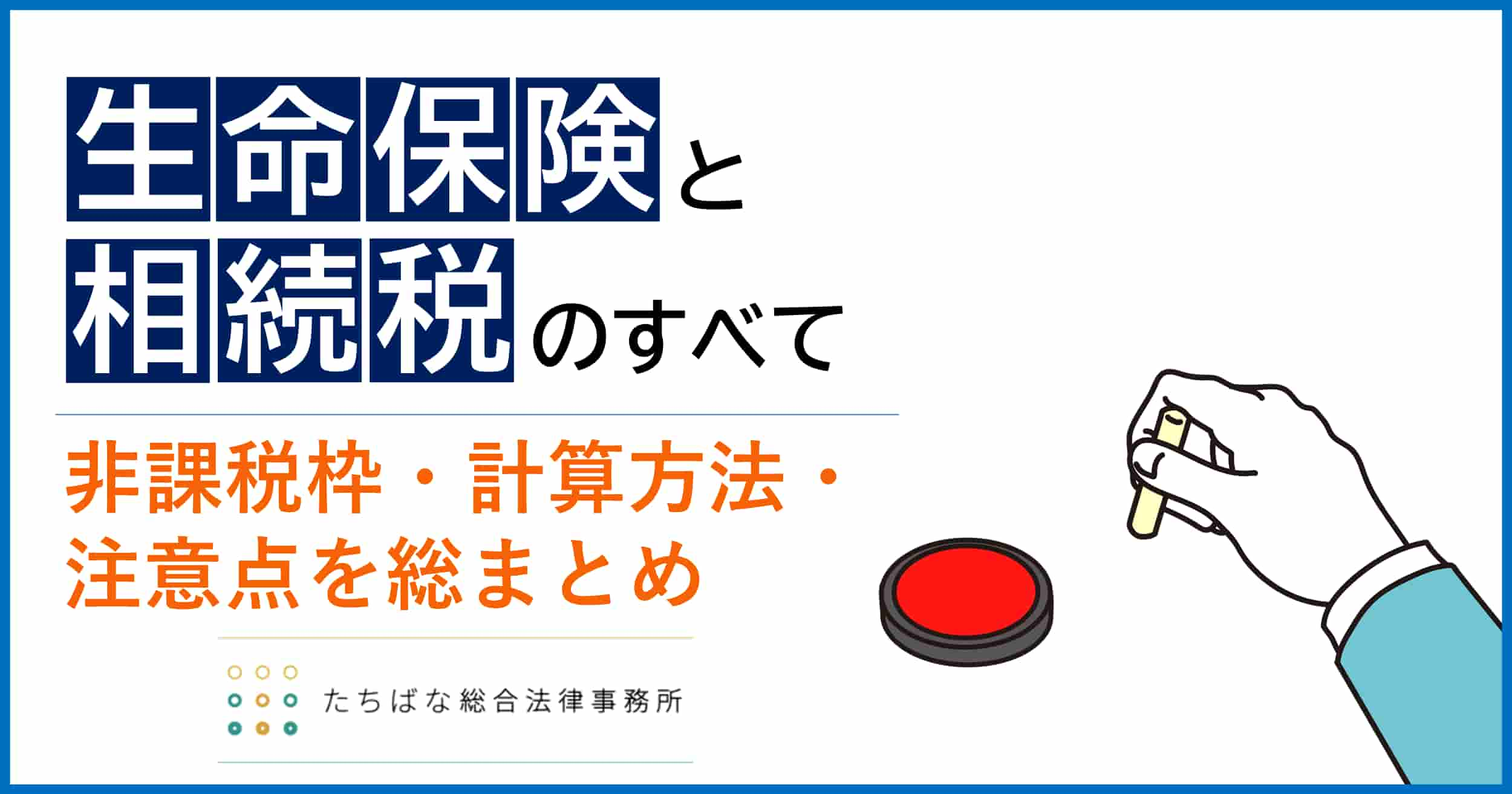
生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ
親御様の年齢を重ね、「もしも」の時に備えたいとお考えではありませんか?
大切なご家族に少しでも多くの財産を遺し、相続を円満に進めるために、生命保険の活用は非常に有効な選択肢です。
しかし、生命保険金には税金がかかる場合があり、その仕組みは複雑です。
「生命保険金は相続税の対象になるの?」
「非課税枠って具体的にいくらまで?」
「どうすれば一番賢く活用できるの?」
こうした疑問や不安を抱える方は少なくありません。
税金の知識がないまま手続きを進めてしまうと、本来払わなくてもよかった税金を納めることになったり、ご家族の間で思わぬトラブルが起きたりする可能性もあります。
この記事は、相続税対策を目的として生命保険を検討されている方々に向けて、法律の専門家が以下の点を分かりやすく、かつ正確に解説します。
- 生命保険金にかかる税金の種類(相続税・所得税・贈与税)とその判断基準
- 相続税の負担を大きく軽減する「非課税枠」の具体的な金額と適用要件
- ご自身のケースに合わせた相続税額の計算シミュレーション
- 相続トラブルを回避し、円満な遺産分割を実現するための活用法
- 知らずに損をしないための重要な注意点
この記事を最後までお読みいただくことで、生命保険を活用した相続対策の全体像を正しく理解し、ご家族にとって最善の選択をするための一歩を踏み出すことができます。
安心して未来の準備を進めるために、ぜひご活用ください。
1. 生命保険金にかかる税金の種類と仕組み
生命保険金を受け取ったときに課税される税金には、相続税、所得税、贈与税の3種類があります。
どの税金が適用されるかは、「契約者(保険料を支払う人)」「被保険者(保険の対象となる人)」「保険金受取人(保険金を受け取る人)」の3者の関係性によって決まります。
この3者の組み合わせを理解することが、適切な相続税対策の第一歩です。
間違った設定をすると、高額な贈与税が課されるなど、予期せぬ税負担が生じる可能性があるため、契約内容をしっかりと確認しましょう。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税される税金 |
|---|---|---|---|
| A(夫) | A(夫) | B(妻・子など相続人) | 相続税 |
| A(夫) | B(妻) | A(夫) | 所得税・住民税 |
| A(夫) | B(妻) | C(子) | 贈与税 |
相続税が適用されるのは、亡くなった方(被保険者)自身が保険料を負担(契約者)し、その保険金を配偶者や子などの相続人が受け取る最も一般的なケースです。
一方で、保険料を負担していた人(契約者)と、被保険者が異なる場合で、かつ保険金を受け取る人(受取人)と保険料を負担していた人(契約者)が同じである場合(例:妻の保険料を夫が払い、妻が亡くなって夫が保険金を受け取る)は所得税の対象となります。
また、保険料負担者、被保険者、受取人がすべて異なる場合(例:夫が妻の保険料を払い、妻が亡くなって子が保険金を受け取る)は、夫から子への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
贈与税は相続税に比べて税率が高くなる傾向があるため、特に注意が必要です。
1-1. 相続税が課税されるケース
被保険者と契約者(保険料負担者)が同一人物で、保険金受取人がその人の相続人(配偶者や子など)である場合、受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(相続税法第3条第1項第1号)。
「みなし相続財産」とは、民法上の相続財産(預貯金や不動産など)ではないものの、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取るため、実質的に相続財産と同じ経済的価値があるとみなされる財産のことを指します。
しかし、生命保険金は、遺された家族の生活保障という重要な役割を担うため、税制上の優遇措置が設けられています。
その代表が「生命保険金の非課税枠」です。
この制度により、取得した保険金のうち一定額までは相続税がかかりません。
非課税枠の控除額は「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で算出されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人いる場合、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。
この場合、受け取った生命保険金のうち1,500万円までは課税価格に算入されず、相続税がかかりません。
一つ重要な注意点として、相続の権利を放棄する「相続放棄」をした人も、非課税枠を計算する際の法定相続人の数には含まれます(相続税法第15条第2項)。
ただし、相続放棄をした人自身が保険金を受け取っても、この非課税枠を適用することはできません。
非課税枠が適用できるのは、あくまで相続放棄をしていない相続人に限られます。
1-2. 所得税・贈与税が課税されるケース
契約者と被保険者が異なる場合など、特定の条件下では相続税ではなく所得税や贈与税が課税されます。
【贈与税が課されるケース】
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
保険金受取人:子
この場合、保険料を負担していない子が保険金という財産を取得するため、実質的に夫から子への贈与があったとみなされ、贈与税の対象となります。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える部分には高率な税金が課されます。
【所得税(一時所得)・住民税が課されるケース】
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
保険金受取人:夫
≪ケース1:夫が保険金を一括で受領した場合≫
この場合、自身が支払った保険料が、妻の死亡により保険金として戻ってきた形になるため、夫の一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(受け取った保険金の総額 - 支払った保険料の総額 - 特別控除額(最高50万円)) × 1/2
この計算結果を他の給与所得などと合算して、最終的な所得税額が決まります。
≪ケース2:夫が保険金を年金型で受領した場合≫
この場合には、夫は一時所得ではなく雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
計算式の例 雑所得=一年の年金受領総額-必要経費の額【※】
【※】 保険料総額÷年金支給期間
この計算結果を他の給与所得などど合算して、最終的な所得税額が決まります。
【注意!】「名義保険」のリスク
形式上の契約者と、実質的な保険料負担者が異なる保険契約を「名義保険」と呼びます。
例えば、契約者が妻になっていても、その保険料が夫の口座から引き落とされているようなケースです。
このような場合、税務調査で実質的な保険料負担者は夫であると判断され、想定していた税金(例:所得税)ではなく、贈与税や相続税が課される可能性があります。
契約時には、誰が保険料を負担するのかを明確にしておくことが重要です。
2. 生命保険金の非課税枠と基礎控除
相続税の計算において、生命保険金には「非課税枠」が、相続財産全体には「基礎控除」が設けられています。
これらは相続税の負担を軽減するための重要な制度です。
両者の違いを正しく理解することが大切です。
簡単に言うと、以下の順番で控除がおこなわれます。
非課税枠での控除の順番
生命保険金の非課税枠
受け取った生命保険金から先に非課税額を差し引く。
▼
相続税の基礎控除
非課税枠を差し引いた後の生命保険金と、その他の相続財産(預貯金、不動産など)を合計した金額から、次に基礎控除額を差し引く。
この2段階の控除により、納税額を抑えることが可能になります。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。
この基礎控除額を、遺産の総額が超えた場合にのみ相続税の申告と納税が必要になります。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。
この場合、生命保険金の非課税枠を適用した後の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
さらに、相続人が配偶者である場合には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という極めて強力な制度があります。
法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからない場合があります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、納税額がゼロになる場合でも必ず相続税の申告が必要ですので、忘れないように注意しましょう。
これらの制度を組み合わせることで、多くのケースで相続税の負担をゼロに、あるいは大幅に軽減することが可能です。
2-1. 非課税制度の適用要件と上限額
生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 要件1
被相続人(亡くなった方)の死亡によって取得した生命保険金であること。
- 要件2
保険料の全部または一部を被相続人が負担していたこと。
- 要件3
保険金の受取人が、被相続人の「相続人」であること。
保険金受取人が相続人でない場合、この非課税枠は一切適用できません。
例えば、被相続人の孫が保険金受取人に指定されている場合、その孫が代襲相続人でない限り、相続人ではないため非課税枠は使えません(詳細は後述の「5-3. 孫への保険金は2割加算になるケース」で解説)。
同様に、内縁の妻やお世話になった友人など、相続人以外を受取人にした場合も適用対象外となります。
また、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
これは、相続税対策のためだけに安易に養子縁組をおこなうことを防ぐための規定です(相続税法第15条第2項)。
これらのルールを正しく理解していないと、想定外の相続税額が発生するリスクがあるため注意が必要です。
2-2. 基礎控除・配偶者控除・法定相続人の考え方
相続税の計算の土台となる「法定相続人」とは誰なのか、その範囲と順位を正しく把握しましょう。
民法では、法定相続人の順位を以下のように定めています。
| 区分 | 相続人 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 民法第890条 |
| 第1順位 | 子 (子が既に亡くなっている場合は孫などの直系卑属が代襲相続) |
民法第887条 |
| 第2順位 | 父母 (父母が既に亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属) |
民法第889条 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 (兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲相続) |
民法第889条 |
配偶者は、他の相続人の順位に関係なく、常に相続人となります。
第1順位から第3順位は、先の順位の相続人がいない場合に、初めて後の順位の方が相続人となります。
例えば、子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が既に死亡などの理由で相続権を失っている場合、その子(孫や甥・姪など)が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が認められるのは、直系卑属(第1順位)と兄弟姉妹の子(第3順位)のみです。
上記の法定相続人の人数が、生命保険の非課税枠や相続税の基礎控除額を計算する際の基準となります。
3. 相続税の計算方法とステップ
実際に相続税を計算するにはいくつかのステップがあります。
ステップ1:課税対象となる財産の総額を算出する
まず、亡くなった方のすべての財産(預貯金、不動産、有価証券など)を評価し、合計額を算出します。
ここに、みなし相続財産である生命保険金も加えます。
また、借入金や未払金などの債務や、葬儀費用は財産総額から差し引くことができます。
▼
ステップ2:生命保険金の非課税枠を差し引く
ステップ1で算出した生命保険金の金額から、非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を差し引きます。
▼
ステップ3:相続税の基礎控除額を差し引く
ステップ2までの計算結果の合計額から、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引き、「課税遺産総額」を確定します。
▼
ステップ4:相続税の総額を計算する
課税遺産総額を、いったん法定相続分で分割したものと仮定して、各相続人の取得金額を計算します。
そして、それぞれの取得金額に相続税の税率を掛けて税額を算出し、それらを合計して「相続税の総額」を求めます。
▼
ステップ5:各相続人の納税額を計算する
ステップ4で算出した相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に割り振ります。
そこから、各相続人の状況に応じて「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」「障害者控除」などを適用し、最終的な各人の相続税額が決定します。
▼
ステップ6:申告と納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ相続税の申告と納税をおこないます。
3-1. 遺産総額の算出から申告までの流れ
相続発生からの手続きは、時間との勝負です。
大まかな流れは以下の通りです。
ステップ1:死亡届の提出・葬儀
▼
ステップ2:遺言書の有無の確認
▼
ステップ3:保険会社への連絡と保険金の請求手続き
他の手続きと並行して早めに着手しましょう。保険金の請求には、保険証券、死亡診断書、受取人の戸籍謄本などが必要です。
▼
ステップ4:相続人の調査・確定
▼
ステップ5:相続財産の調査と評価
預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もすべてリストアップし、財産目録を作成します。
▼
ステップ6:遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。
▼
ステップ7:相続税の計算と申告書の作成
▼
ステップ8:相続税の申告・納税
3-2. 具体的シミュレーション例
ここでは、具体的なモデルケースで相続税額をシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 被相続人:夫
- 相続人:妻、長男、長女(法定相続人3人)
- 相続財産:
- 死亡保険金:3,000万円(受取人は妻)
- 預貯金・不動産など:7,000万円
- 遺産総額:1億円
- 債務・葬儀費用:なし
- 遺産分割:法定相続分通り(妻1/2、長男1/4、長女1/4)
【計算ステップ】
- ① 生命保険金の非課税枠を計算
500万円 × 3人(法定相続人) = 1,500万円 - ② 相続税の課税対象となる生命保険金額を計算
3,000万円(保険金) - 1,500万円(非課税枠) = 1,500万円 - ③ 相続税の課税価格の合計額を計算
1,500万円(課税対象の保険金)+ 7,000万円(その他財産) = 8,500万円 - ④ 相続税の基礎控除額を計算
3,000万円 +(600万円 × 3人) = 4,800万円 - ⑤ 課税遺産総額を計算
8,500万円(課税価格) - 4,800万円(基礎控除額) = 3,700万円 - ⑥ 相続税の総額を計算
✔ 課税遺産総額(3,700万円)を法定相続分で按分 妻:3,700万円 × 1/2 = 1,850万円
長男:3,700万円 × 1/4 = 925万円
長女:3,700万円 × 1/4 = 925万円
✔ 各人の税額を計算(国税庁の速算表に基づく)
妻:1,850万円 × 15% - 50万円 = 227.5万円
長男:925万円 × 10% = 92.5万円
長女:925万円 × 10% = 92.5万円
✔ 相続税の総額:227.5万円 + 92.5万円 + 92.5万円 = 412.5万円 - ⑦ 各人の最終的な納税額を計算
相続税の総額(412.5万円)を実際の取得割合(法定相続分と同じ)で按分
妻:412.5万円 × 1/2 = 206.25万円
長男:412.5万円 × 1/4 = 103.125万円
長女:412.5万円 × 1/4 = 103.125万円
妻は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、納税額は0円になります。
最終的な納税額:長男 約103万円、長女 約103万円
【シミュレーションからの考察】
このケースでは、生命保険の非課税枠1,500万円を活用することで、課税対象となる遺産を圧縮できています。
もし生命保険がなく、すべて預貯金だった場合、課税遺産総額は5,200万円となり、相続税の総額は約630万円まで増加します。
生命保険が相続対策において有効な手段であることがお分かりいただけたかと思います。
4. 生命保険を活用した相続税対策のメリット
生命保険は、非課税枠の他にも、相続手続き全体を円滑に進めるための多くのメリットを持っています。
【生命保険活用の主なメリット】
- ① 納税資金の準備に充てることができる
- ② 特定の人に確実に財産を遺せる
- ③ 遺留分対策として活用できる
これらのメリットは、預貯金や不動産にはない生命保険ならではの特性から生まれます。
特に、生命保険金が「受取人固有の財産」 とされる点が大きなポイントです。
これは、保険金が遺産分割協議の対象外となり、受取人が他の相続人の同意なしに、単独で速やかに保険金を請求・受領できることを意味します。
4-1. 納税資金の確保や代償分割への活用
相続財産が不動産ばかりで、すぐに現金化できる資産が少ない場合、相続税の納税資金に困ることがあります。
相続税は原則として、申告期限までに現金一括納付が必要です。
納税のために自宅を売却せざるを得ないといった事態も起こり得ます。
生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、死亡後すぐにまとまった現金を確保できます。
これにより、遺産を焦って売却することなく、期限内に納税することが可能になります。
4-2. 受取人の自由設定で相続トラブルを回避
生命保険は、契約者が保険金受取人を自由に指定できるため、「特定の人に確実に財産を遺したい」という意思を反映させやすい金融商品です。
例えば、家業を継ぐ長男や、特に介護でお世話になった長女など、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合、遺言書と合わせて生命保険を活用することが有効です。
先述の通り、生命保険金は受取人固有の財産です。
分割協議で揉めたとしても、基本的に指定された受取人が確実に現金を受け取ることができます。
4-2-1.遺留分との関係
ただし、注意点として「遺留分」があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分(権利)のことです。
他の相続人の遺留分を侵害するほど極端に多額の生命保険金を特定の相続人に遺した場合、例外的にその保険金が遺留分侵害額請求の対象となるという判例(最高裁決定平成16年10月29日)も存在します。
生命保険金が常に遺留分の対象外となるわけではないため、高額な保険を検討する際は法律の専門家である弁護士への相談が不可欠です。
5. 生命保険金受取り時の注意点
生命保険は有効な相続対策ですが、いくつかの注意点を押さえておかないと、せっかくのメリットを活かせない可能性があります。
特に、契約内容の定期的な見直しは不可欠です。
家族の状況は、結婚、出産、離婚、死別などのライフイベントにより年月とともに変化します。
こうしたライフイベントに合わせて保険契約を見直さなければ、いざという時に「こんなはずではなかった」という事態になりかねません。
ここでは、特に見落としがちな3つのポイントを解説します。
5-1. 受取人が先に死亡していた場合の対応
もし指定していた保険金受取人が、被保険者よりも先に亡くなってしまった場合、どうなるのでしょうか。
受取人を変更しないまま被保険者が亡くなると、保険金は元の受取人の相続人ではなく、保険契約の約款に基づいて被保険者の法定相続人が受け取ることになるのが一般的です。
しかし、場合によっては、意図しない人物に保険金が渡ってしまったり、相続人間での新たなトラブルの原因になったりする可能性があります。
このような事態を避けるため、受取人が亡くなった場合は、速やかに保険会社に連絡し、「死亡保険金受取人の変更」手続きをおこなってください。
また、契約時にあらかじめ「予備的受取人」を指定できる保険商品もあります。
家族構成の変化があった際には、保険証券を確認し、契約内容を見直すようにしましょう。
5-2. リビングニーズ特約の非課税枠への影響
リビングニーズ特約とは、医師から余命6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる制度です。
治療費や残された家族との時間に使うための資金として活用できます。
ここで注意したいのは、生前に受け取ったリビングニーズ特約による保険金には、死亡保険金の非課税枠は適用されないという点です。
生前に受け取った保険金は、その時点で被保険者本人の財産(現金・預金)となり、亡くなった時点では預貯金などと同じ本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
つまり、非課税の恩恵を受けることはできません。
この特約を利用するかどうかの判断は、非課税メリットとの比較も考慮して慎重におこなう必要があります。
5-3. 孫への保険金は2割加算になるケース
「子どもを飛び越えて、孫に直接財産を遺したい」という意向から、保険金受取人を孫に指定するケースがあります。
ただし、法定相続人ではない孫は、生命保険の非課税枠が適用されません。
また、相続税法では、財産を取得した人が、被相続人の配偶者、一親等の血族(子や父母)以外である場合、その人の相続税額が2割加算されるというルールがあります(相続税法第18条)。
したがって、受取人に指定された孫は、原則としてこの2割加算の対象となります。
ただし、例外があります。
被相続人の子が既に亡くなっており、その子に代わって孫が相続人となる「代襲相続」の場合、その孫は一親等の血族である子と同じ立場とみなされるため、2割加算の対象にはなりません。
孫を受取人に設定することは、ご自身の意思を反映できる有効な手段ですが、税負担が増える可能性を理解した上で、慎重に検討することが重要です。
6. まとめ
生命保険は、正しく理解し活用することで、相続税の負担を軽減し、希望する相続の実現に非常に有力な手段となります。
準備は決して早すぎることはありません。
ご自身の家族構成や財産状況を把握し、生命保険がどのように役立つか、一度シミュレーションしてみましょう。
たちばな総合法律事務所には、元国税審判官の経歴を持ち、税理士登録もしている弁護士が在籍しています。
そのため、遺産分割でトラブルになっている複雑な案件でも、税務と法務の両面からワンストップで最適なサポートをご提供できるのが大きな強みです。
当事務所は、こうした相続トラブルが絡む相続税申告に特に強みがあり、弁護士と税理士、両方の視点から最適な解決策をアドバイス・サポートいたします。
また、初回無料で、相続問題の法律相談をおこなっています。
ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、電話での相談も実施しておりますが、相続税に関してはご事情、資産状況などをお伺いしなければアドバイスが難しいため、相続税額のシミュレーションなどについては来所でのご相談をお願いしております。
事前のご予約を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続 に関する解決事例
- 2025.11.14
- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント
- 2025.11.12
- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅
- 2025.11.6
- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】
- 2025.11.5
- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで
- 2025.10.30
- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説






















































